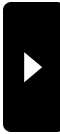2022年12月24日
ソロキャンプデビューを目指してる方々へ
こんにちわ、Masada556です。
いよいよ年の瀬も押し迫りました。
東北三県では殆どのキャンプ場が10月から11月いっぱいで今年の営業を終えてしまいました。
特に今年も雨の多い年だったので、終盤のキャンプくらいは仲の悪い天候の神様にゴマをすってでも出掛ける覚悟を決めていましたが、何とか12月の頭に一泊キャンプが出来ました。
何とも物寂しい気持ちでキャンプ場を後にしました。
では今回は、ソロキャンプデビューを考えている皆様へ、ちょっとしたアドバイスとお節介な話をしていきます。
人生最初のキャンプでソロを目指すという人も中々居ないでしょうから、皆さんそれなりのキャンプ経験は積んでいるかと思います。
家族や仲間達との楽しいキャンプから一歩踏み出そうとしているあなた
は、キャンプの新たな一面を見出したと考えても間違いは無いでしょう。
人間とは集団の力で文明を築き上げてきた生き物です。
それを敢えて本来現代人が恐れる自然の中の孤独に身を置きたいと考えている訳ですから、自分でも気がつかないうちに気持ちの変化があったのでしょう。
個人的には ”ようこそ、こちら側へ” と言った感じなのですが、その裏側と言いますか、見えない何かの事が今回のお話という認識で読んでいただけると幸いです。
また以前書き込みました、ソロキャンプの魅力 から繋がっていく話であると理解していただけると分かりやすいかと思います。
今回は多少非難めいた表現も出てきますが、他のキャンパーの方々を攻撃非難するような意図ではないことを最初に明記しておきます。
どうか誤解無きようお願い致します。
では、本題に入ります。
一体何を言いたくてこんな回りくどい事を書いているのかと言うと、自然の中にたった一人で入り込んで行くことに、
”できるだけしっかりした準備と心構えを持ってください”
そうお願いしたいのです。
野山の中で過ごすキャンプと言う趣味では当然ですが、自然の優しい面だけ見ている訳にはいきません。
1、自然があなたに与える脅威
2、最近ネットでも見かける事が多くなってきました、他のキャンパーや得体の知れない人間の脅威。
3、人里離れた地での不可思議なモノの脅威。
今回はこの三つについて自分の体験や他の色々な方々から伺った体験談等を交えながらお話していきます。
1、皆さんは深い森の中を散策したことがありますか?
それはとても気持ちの良いものです。
地上に光の波を作り出す木漏れ日の中、森が作り出す新鮮な大気を胸いっぱいに深呼吸してみれば、その素晴らしさに驚く事と思います。
こんな場所で一杯の珈琲を味わおうと、驚くほど冷たい沢の水を汲み上げている時に、五メートル程の対岸の向こうの茂みの中に、何かが動きました。
ホンの十秒程で真っ黒な四つ足の動物が姿を現しました。
そう、熊です。
体長1、2メーター程、体重は恐らく自分より重いでしょう?
その時の自分は渓流の岩に四つん這いになって右手で水を汲んでいる体勢です。
小型の月ノ輪熊とは言え、全くの無防備な体勢、あり得ない程の至近距離の遭遇に身が凍りました。
恐らく沢に水を飲みに降りてきたのでしょう、たまたま風下側だったので熊も自分に気がつかなかったかと思います。
意識が恐怖だけで埋めつくされるなか、水筒代わりのペットボトルを離し、ゆっくりと腰のナイフに手を伸ばしたのは覚えています。
もちろん視線は熊に釘付けです。
微かに感じる獣臭さ、熊はこちらを見るでもなく岩の間をほじくっていましたが直ぐに向きを変え茂みの中に消えていきました。
感覚が人間等とは比較にならない熊が、目の前で無様な姿を晒している自分に気がつかない訳がないのです。
ドッカリと岩の上に座り込んで呆けたように息を整えていたのですが、
急に押し潰されそうな恐怖が背筋を走り、沢の小道を車に戻ります。
絶対に走ってはいけません。
対岸の熊は確実に自分を観察しているはずです。
野生動物は他の生き物の気配に敏感なのです。
自分の目の前に這いつくばるような、間抜けな生き物に恐怖の臭いを感じたら、この危うい均衡が崩れるかもしれないのです。
ゆったりと、散歩を楽しんでいるかのように、ゆったりと足を運びます。
数十メーター先に見えているJeepの姿がこれほど遠いものかと感じ、全身にビッショリと嫌な汗が吹き出し、直ぐ後ろに熊が着いてきているという幻想に絶叫を上げて走り出しそうになります。
結局のところ何事も起こらず、Jeepに戻って何キロか走った後小さなパーキングに車を止め、クーラーボックスから取り出した冷えたペプシを一気飲みしてから、現実に戻ってきました。
ゲンキンなモノで、ついさっきまでの恐怖は全く感じません。
ヤバかった。
ただそれだけが残りました。
いずれ熊と直に遭遇する事態に、自分なりにシュミレーションしていたつもりでしたが、あんな無防備な体勢での近距離遭遇は思い付きませんでした。
思い返せば、シースから抜きかけていたナイフを、途中で右手が止めた事が、助かった要因のひとつだったと考えます。
周囲に漂った微かな鉄の匂いに、面倒事を嫌った熊が身を退いたのでしょう。
もし引き抜いて身構えていたなら、攻撃の気配を感じ取った熊と、命のやり取りとなったかもしれません。
体勢が不利、渓流の中足元も不備、そして命懸けの戦いに突入する気構えが全く成っていない自分が、恐怖に駆られて抜いたナイフなど、怒りモードに入った熊にとってはつま楊枝程度のモノだったでしょう。
自分の見通しの甘さを痛感した一日でした。
これは特殊な例でもなんでもありません。
実際にキャンプ場で熊に教われる被害がニュースや全国紙で報道されています。
また熊に限らず様々な野生動物との遭遇は当たり前のようにあり得ることと考えてください。
特にここ東北ではちょっと山に入れば熊に注意の看板はいくらでも目にします。
それだけ熊との遭遇は珍しい事ではないのです。
それらに対して、しっかりとした対策と心構えは怠らない事です。
なんと言っても、今ここにいるのはあなた一人なのですから・・・
2、ここ数年残念なことにキャンプ場での盗難、女性キャンパーへの暴行事件、キャンプ場からの女児の失踪事件などがニュースやネットでも大きく取り上げられるようになりました。
そのうちにキャンプ場に交番の設置やガードマンのパトロールが必要になるのではないでしょうか?
残念なことです。
しかし嘆いていても事は始まりません。
これからもキャンプという趣味を続けていくからには、しっかりした対策をとらなければいつか自分が被害者の立場に立たされるかも知れないのです。
ここからは自分個人が行っている対策方法なども織り混ぜたお話になります、ちょっと刺激が強めな事例などもありますのでどうかご容赦を。
まずキャンプ場に入り込んでくる犯罪者を、気の迷いでたまたまやってしまったのではないか。とか、解放感や酒が行きすぎてうっかりとやらかしてしまったのだろう。などと良心的な解釈で見ない事です。
確かに酒が過ぎて問題を起こす者もいますが、計画的にキャンプ場に入り込んでくる犯罪者は、そんな甘いものではありません。
彼らは、自分達の犯罪が十分遂行可能、あるいは成功する可能性が高い、そして怪しまれたり逮捕される可能性が低いこと。
それらを冷静に計算して、都市から離れたキャンプ場にワザワザ足を運んでいるのです。
当然それに対応した心構えで不審者に対処しなければならない訳です。
例えば、”あの人はあの木陰でいったい何をしているのだろう?”
そんな感覚を覚えたら、その感覚を気のせいだろう。などと決して考えない事です。
大きな街中の公園であれば、木陰のベンチで一休みしている人もいるでしょう。
公園の奥でひとときを楽しんでいるカップルがいても、何の不思議もありません。
ただキャンプ場、特に人気の少ない野営場で不可解な行動をしている人物を目にしたら、決して不用意に目を離さない事です。
例えば、その人物の服装や雰囲気に違和感を感じないか?
行動や態度に不振なものや粗暴な感じがしないかなど、キャンプを楽しむというような感覚から何か外れているような違和感を覚えるかも知れません。
管理人のいるキャンプ場なら、どの辺りの場所にこんな服装で何かを覗き込んでいるような不振な者がいる。
出きるだけ具体的に管理人に報告することです。
ただ漫然と、変な人がいる。だけでは報告された管理人も”何かの勘違いなのでは”から物事を考えるので、初動が遅れたりして結局見失ってしてしまえばワザワザ報告した意味が無くなってしまいます。
逆に適切な報告であれば、ヒトは動いてくれます。
あそこのキャンプ場は不審者がウロウロしていて怖い。
そんな噂でもネットに流れてしまえば、確実に利用者の減少に繋がるからです。
さらに一歩進めて”自分の身を守る”事を最優先とします。
その不審者が何を求めているかを考えて見ることが必要です。
例えばファミリーが多く、混雑しているようなキャンプ場であれば、キャンプギアや貴重品の盗難を目的としている可能性が高いでしょう。
逆に人気の少ない山奥の野営場などでは、ソロキャンプ中の婦女子への暴行や駐車場に停めてある車の車両荒しや盗難等が考えられます。
したがって、そのような犯罪者の傾向を見定め、自分のキャンプサイトの状況をしっかり把握することです。
例えば自分のテントのすぐ側に深い茂みがあって、その奥は良く見えない。
あるいはソロを楽しみたくて。周囲に誰もいないような場所にテントを張っている。
など、犯罪目的で接近してくる不審者から自分とテントサイトはどのように見えているのか?
この辺りの判断から始めてみましょう。
そしてしっかりと対策も考えて見るべきです。
もしキャンプサイトから、何かギヤを盗まれた。としたら、それはあなたに犯罪者がつけこむ隙があったと考えてください。
今回は助かったのだと。
次はあなた自身が犯罪に巻き込まれる可能性が高いということです。
私利私欲で物を考える日本人が増え、爆発的に外国人犯罪者が増加している今の日本。
これが現実です。
3、今までの書き込み等からお分かりいただけるかと思いますが、自分はキャンプ以前に野山をJeepで走り回る事が大好きです。
しかしここ何十年かの違法投棄やどこにでも車を停めたりゴミを捨てていくマナーの悪い釣り人や山菜採りのおかげで、立ち入り禁止の看板と道を塞ぐロープに、趣味の範囲は狭められ続けています。
そのような狭められた状況のなかで、素晴らしい景色や美しい景観を目にすると、とても感動を覚えるものです。
そしてそんな景色に出会える時はなぜかいつも一人なのです。
そんな素晴らしい瞬間を少しでもとどめようとシャッターを切るのですが、所詮素人の写メです。
あとで画像を確認してもそのときの感動を半分も覚えないのです。
しかしその時の状況だけは目の奥にしっかりと焼き付いています。
そんな自分が今まで体験した不可思議な事や体験談をうかがった不思議なお話をいくつか紹介します。
○携帯電話が普及し始めたころと記憶しています。
フラッと出掛けた岩手の奥地で道路脇に車を止め、体を伸ばしながらマップを確認していました。
秋晴れの昼前で、珈琲片手に一服していた時、
カランカラン・・・カランカラン・・・
遠くから熊鈴の音が微かに聞こえるのどかな風景でした。
タバコを揉み消してその林道と思われる(地図には載っていないため正確な場所は不明)細い道を30分ほど走ると道路が二股に別れます。
どちらも同じくらいの広さで、どちらを選ぶか判断できません。
また車を脇に寄せ、少しばかり道を歩いて見ます。
路面に残っているタイヤ痕の多さとタイヤパターンの違いで見当をつけます。
左の道は大型トラックが走ったようなゴツいタイヤ痕が多く、造林業者さんの使っている作業道路と判断、左の道に入ろうと車に戻ろうとしたときでした。
カランカラン・・・カランカラン・・・
また熊鈴の音色が聞こえてきました。
たぶんさっきと同じ音です。
熊鈴の音は特徴あるものも多く、聞き分けることも難しくはありません。
カラン・・・カランカラン・・・
しかも、
”近いな・・・”
熊鈴の聞こえる場所とは大体決まっていて、要するに登山道か何かのハイキングコースでなければ聞こえてくるという事はありません。
ここは山間部の峠道です。
”こいつは、サッサと離れた方がいいな。”
車に乗り込み数分走ると、ガードレールや注意標識が見えたので間違っていなかったことがわかります。
標識があるという事は、その道路は少なくとも市町村が管理していることになり、廃道でもない限りどこかの道に繋がります
逆にガードレールも何もない道路は、個人が作った作業用の私道である可能性が高いのです。
走っていると山道は沢沿いの細い道に繋がりました。
とうに昼を過ぎていたので飯にしようと脇道にそれ、道路脇にシートを広げて蚊取り線香に火をいれ、湯を沸かしカップ麺とおにぎりを堪能したあと、少し横になります。
自分は昼食後必ず仮眠をとることにしています。
秋晴れの中、意識が遠退いていきます。
カランカラン・・・カラン・・・カランカラン・・・
跳ね起きました。
ものすごく近い! ヘタするとすぐ側!!
車の中にシートと細々とした道具類蚊取り線香を放り込み、アクセルをおもいっきり踏み込みます。
・・・・・人家が見え始め、販売機の前に車を止めてコーラを買い込み、一服しながら考えました。
”あれはいったい何だったのか?”
今でもわかりません。
○真冬の冬山に友人と猟に出掛けた時の事です。
狩猟というのはあてずっぽうに山を歩いても、そう簡単には獲物に出会うことはありません。
猟期以外に山を調べて走ったり、川の位置、餌場の場所、隠れる事ができる藪の位置など地形を読んで当たりをつける訳です。
自分達二人もそんな場所の側に車を止め、装備を身に着けていたときです。
すぐ目の前の小道を鞄を持った中学生程度の男の子が歩いていきました。
サクサクと雪を踏みしめながら自分達の前を通りすぎ、下り道を曲がっていきます。
「どこに行くってンだ?」
「おかしいな・・・?」
自分達は不可思議に顔を見合わせます。
そして、手早く装備を身に着けて彼の後を辿ります。
30メーターも歩いたでしようか。
彼には追い付けませんでした。
自分達が追いかけた雪道に残る一対の足跡、それはろくに除雪もしていない山奥に通じる道です。
そもそもここは道路ですらないのです。
自分達が車を止めるために分け行った、猟場の側の田んぼか畑に通じる畦道で、50メーターも戻れば普通に道路が通じているのです。
そんな畦道を、山に向かって中学生が歩いていく理由がわかりません。
さらに言えばこの周囲数キロ以内で人家を見かけた記憶はありません。
自分達二人は雪が降りしきるなか、足跡が続く山道を無言で見つめるだけでした。
○これは日本海側に遊びに行った時の事です。
出発がすっかり遅れてしまい、目標としていた十二湖から帰ろうとしたときには辺りも薄暗くなり出した午後6時過ぎ。
駐車場にもほとんど車はなく誰も人はいませんでした。
十二湖とは青森県を跨いでここ八戸市から反対方向にある深浦町にある風光明媚な観光地で片道200キロ以上、およそ4時間以上のドライブとなります。
途中の休息時間も考えると今日中に自宅にたどり着けるか微妙なところです。
当時はまだ若かったのであまり気にもせず、最短ルートと考えた十和田八幡平国立公園の山の中を夜間にたった一台で突っ切るルートを選択したのです。
何度も走っているルートなので、自分にとっては明るいか暗いか程度の違いでしかありません。
むしろ危なっかしいサンデードライバーや追い越せない観光バスなどが居ない分走りやすい位です。
そして快調に山道を走っているとき訪れるべきものが下半身に訪れ、公衆トイレなどはもちろんないので、道路脇に車を止め、天空の素晴らしい星空を堪能しながら用を足していると、
真っ黒い何かが頭の上を通過していきました。
それは何の音もせず、木々の梢の上を掠める位の高さを飛行していきました。
恐らく鳥でしょう。
しかし翼端から翼端まで、4メートルから6メートル?
何の目標物のない空中の物体の大きさですから、ハッキリとはわかりません。
もっと大きいかも、逆に小さかったかもしれません。
羽ばたきひとつせず目の前を滑空して木々の間に消えていきました。
その間恐らく数秒。降ってきそうな星空を背景に、黒い影は確かに存在していました。
○この話は野営場で親しくなったベテランキャンパーからうかがったお話です。
その方は家族と何回か行ったキャンプ以外は、30年以上全てソロと言う筋金入りのソロキャンパーで、足の向くまま行けるところならどこにでも行ってソロキャンプするという大先輩のようなお方でした。
ただし設備の整った今風のキャンプ場と、混雑は苦手。
という方だったので自分と話が合い、お互い話が弾んだのです。
その方が、
「一度だけキャンプしてて逃げ出した事がある」
そう言い出しました。
「何か問題でも起きましたか?」
「いや、馬鹿馬鹿しいかもしれないが・・・」
話はこうです。
コロナによるキャンプブームなんてものが起きるはるか以前の話。
その方を仮にBさんとします。
仕事が立て込んで中々まとまった休みが取れなかったBさんは、秋の初め頃ようやく3連休を取って山中の野営場にテントを張ったそうです。
ご存じの通り、野営場と言うのは、トイレと炊事場ががあるだけの最低限の施設だけを備えたキャンプ場の事。
平日だったそうで、まだキャンプブームなんてものが無かった時代なので、キャンプ場には誰もおらず、静かなソロキャンプを楽しんでいたそうです。
初日の夕方、晩飯の準備に入る前にトイレに行ったらトイレのドアが開いていたそうなので、用を済ませたあとしっかりとドアを閉めて、テントに戻りました。
そして寝る前にトイレに行くと、またドアが開いている。
・・・?
そのドアはどこでも良く見る、握り玉と呼ばれる真ん中に鍵穴がついた取っ手を回して開閉するドアで、建て付けてまだ新しい物で、閉じてしまえば簡単に開く物では無かったそうです。
そのトイレは炊事場から少しばかり離れた所に建っており、炊事場の灯りで周囲を見回しても人の気配は全く無く、違和感を感じながらテントに戻ったそうです。
そして、その夜・・・・
深夜のこと、ビールを飲み過ぎたせいでしょう。
下半身に切迫した危機を感じた彼は、何となく嫌なものを感じながらもライト片手にトイレに向かいました。
その時トイレのドアは閉まっていたそうです。
ホッとしてトイレのドアに手を伸ばした瞬間、
バンッ!!
誰かが内側から蹴飛ばしたような勢いで、ドアが開いたそうです。
薄暗いトイレの中には誰もいなかった事だけは間違いなかったと本人は言っています。
うを!
悲鳴をあげて彼は車に飛び乗り、何もかも投げ出して逃げ出したそうです。
M「それは怖いですね」
B「う~ん、あれは何だったんだろう。
・・・あなたにはそんな体験はないのかい?」
M「俺ですか・・・俺はそう言うモノを見る事はあまりできないみたいですけど、幾つか不思議なモノを見たり聞いたりしたことはあります」
B「ほう、聞きたいね」
M「いいですよ。
これは観光地のトイレで知り合いが体験した話なんですが・・・」
地名は伏せますが、そこは岩手県、地元では知らぬ者などいない有名な観光地です。
数100メーターは切り立った岩山の崖から巨大な岩棚が突きだし、そこから下を覗き込めば、どんな強心臓の持ち主でも身がすくむ思いをするでしょう。
そしてその突端のは小さな祠が祭ってあり、お酒などが供えてあります。
実際はその場所に行くには危険が伴うので、小道の入り口には簡単な柵で塞がれています。
そこには大きな展望台が設置されているので、どなたでも見晴らしのよい景色を楽しむことができます。
車も数台駐車が可能で、最近は整備された小綺麗なトイレも設置されてるようです。
人気もほとんどなく、落ち着いた雰囲気の観光名所です。
そこに平成の最初の辺りでしょうか?
知り合いが訪れたそうです。
もう夕方で缶コーヒーとタバコをお供に風景を楽しんだあと、車に乗る前に大きい方を処理しようと個室に入ったそうです。
本当に小さなトイレで、男性用小がひとつ、個室がひとつ。
幸いロールペーパーは供えてあったので、ゆっくりと用を足していると、
バタン
隣の女性用トイレに誰か入って来ました。
そして、
「おかあさん、おかあさんっ」
入ってきたのは少女らしく、母親を探しているらしいのです。
「おかあさん、どこ、おかあさん」
ドンドンとドアを叩く音が聞こえてきます。
「おかあさん、おかあさんっ!」
半ベソ状態の少女がトイレを飛び出して行きました。
ようやく爆撃が完了し、後始末を終えた彼はジーンズを引き上げ、下半身をチェックしてからトイレを飛び出したそうです。
いかに緊急事態とは言え、ズボンをずり下げた状態で少女を追いかけていたのでは、どのような理由があろうと、問答無用で逮捕されます。
蹴飛ばすようにドアを開け、周囲を見回し少女の姿を探します。
見当たらなかったそうです。
「・・・?」
展望台に戻ると自分の車が止まっているだけ。
当然あるはずのもう一台の車はありません。
ここは山の中、人家は15分も細い山道を下った下です。
そのまま道を上っていってもただ山奥に踏み込んで行くだけで、車でも走行困難になるような道です。
「どこにいった・・・?」
なんとも言えない違和感を感じながらも、夕暮れの中10分程度辺りを探したそうですが、とうとうその姿を見つけ出すことはできなかったそうです。
少女がトイレを出てから、後を追うまでの時間は30秒程度。
駐車場に車が無いいじょう、少女は徒歩でこんな山奥に母親を探して単独で来たのか。
道を挟んで反対側は急な法面、展望台側はそれこそ崖で、探すところはどこにもないのです。
そこまで考えてから彼はとある噂を思い出しました。
その岩棚は有名な自殺の名所であるという、真偽の疑わしい話を。
もし、本当に、あそこから親子が無理心中を計ったとしたら、とてつもない高さからの落下です。
途中何かにぶつかって親子の手が離れ、別々の場所に落ちてしまえば・・・
そんなことを考えながら彼は車のキーを捻り、慎重に暗い山道を下ったそうです。
B「もしその女の子が死んだ事に気づいてなくて、いつまでも母親を探しているのなら、なんとも哀れな話だな」
M「死人に同情するのは厳禁だそうですが、可愛そうな話です」
B「・・・テレビのバラエティ番組やネットに乗っているような心霊話の大半は、見間違いや暇な若者の戯言なんだろうが、不思議なことってのは、あるからねぇ」
M「ありますよね」
そうして、彼のテントの前で焚き火とランタンの明かりの中、色々な話が深夜まで続き、翌朝、いつかどこかでの再開を約束し、さっぱりとお別れしたのでした。
希に出会う、このような一期一会も、ある意味ソロキャンプの魅力なのかもしれませんね。
今回はいつもと少しばかり毛色の違った話になりました。
自分的には女性のソロキャンパーが増えてくださるのは良いことだと思います。
技術的にも精神的にもシッカリと自分の面倒を見れる方であれば、老若男女を問わないのがこの世界です。
ただ、インスタ映えするからとか、友人に自慢したいからと言った、何か勘違いしているような理由でのソロキャンプは、”もしもの時”自分と周囲にどのような結果をもたらすか今一度良く考える事です。
今年の投稿はこれで終わりたいと思います。
来年もまたよろしくお願いします。
皆様良いお年を
では、また、
いよいよ年の瀬も押し迫りました。
東北三県では殆どのキャンプ場が10月から11月いっぱいで今年の営業を終えてしまいました。
特に今年も雨の多い年だったので、終盤のキャンプくらいは仲の悪い天候の神様にゴマをすってでも出掛ける覚悟を決めていましたが、何とか12月の頭に一泊キャンプが出来ました。
何とも物寂しい気持ちでキャンプ場を後にしました。
では今回は、ソロキャンプデビューを考えている皆様へ、ちょっとしたアドバイスとお節介な話をしていきます。
人生最初のキャンプでソロを目指すという人も中々居ないでしょうから、皆さんそれなりのキャンプ経験は積んでいるかと思います。
家族や仲間達との楽しいキャンプから一歩踏み出そうとしているあなた
は、キャンプの新たな一面を見出したと考えても間違いは無いでしょう。
人間とは集団の力で文明を築き上げてきた生き物です。
それを敢えて本来現代人が恐れる自然の中の孤独に身を置きたいと考えている訳ですから、自分でも気がつかないうちに気持ちの変化があったのでしょう。
個人的には ”ようこそ、こちら側へ” と言った感じなのですが、その裏側と言いますか、見えない何かの事が今回のお話という認識で読んでいただけると幸いです。
また以前書き込みました、ソロキャンプの魅力 から繋がっていく話であると理解していただけると分かりやすいかと思います。
今回は多少非難めいた表現も出てきますが、他のキャンパーの方々を攻撃非難するような意図ではないことを最初に明記しておきます。
どうか誤解無きようお願い致します。
では、本題に入ります。
一体何を言いたくてこんな回りくどい事を書いているのかと言うと、自然の中にたった一人で入り込んで行くことに、
”できるだけしっかりした準備と心構えを持ってください”
そうお願いしたいのです。
野山の中で過ごすキャンプと言う趣味では当然ですが、自然の優しい面だけ見ている訳にはいきません。
1、自然があなたに与える脅威
2、最近ネットでも見かける事が多くなってきました、他のキャンパーや得体の知れない人間の脅威。
3、人里離れた地での不可思議なモノの脅威。
今回はこの三つについて自分の体験や他の色々な方々から伺った体験談等を交えながらお話していきます。
1、皆さんは深い森の中を散策したことがありますか?
それはとても気持ちの良いものです。
地上に光の波を作り出す木漏れ日の中、森が作り出す新鮮な大気を胸いっぱいに深呼吸してみれば、その素晴らしさに驚く事と思います。
こんな場所で一杯の珈琲を味わおうと、驚くほど冷たい沢の水を汲み上げている時に、五メートル程の対岸の向こうの茂みの中に、何かが動きました。
ホンの十秒程で真っ黒な四つ足の動物が姿を現しました。
そう、熊です。
体長1、2メーター程、体重は恐らく自分より重いでしょう?
その時の自分は渓流の岩に四つん這いになって右手で水を汲んでいる体勢です。
小型の月ノ輪熊とは言え、全くの無防備な体勢、あり得ない程の至近距離の遭遇に身が凍りました。
恐らく沢に水を飲みに降りてきたのでしょう、たまたま風下側だったので熊も自分に気がつかなかったかと思います。
意識が恐怖だけで埋めつくされるなか、水筒代わりのペットボトルを離し、ゆっくりと腰のナイフに手を伸ばしたのは覚えています。
もちろん視線は熊に釘付けです。
微かに感じる獣臭さ、熊はこちらを見るでもなく岩の間をほじくっていましたが直ぐに向きを変え茂みの中に消えていきました。
感覚が人間等とは比較にならない熊が、目の前で無様な姿を晒している自分に気がつかない訳がないのです。
ドッカリと岩の上に座り込んで呆けたように息を整えていたのですが、
急に押し潰されそうな恐怖が背筋を走り、沢の小道を車に戻ります。
絶対に走ってはいけません。
対岸の熊は確実に自分を観察しているはずです。
野生動物は他の生き物の気配に敏感なのです。
自分の目の前に這いつくばるような、間抜けな生き物に恐怖の臭いを感じたら、この危うい均衡が崩れるかもしれないのです。
ゆったりと、散歩を楽しんでいるかのように、ゆったりと足を運びます。
数十メーター先に見えているJeepの姿がこれほど遠いものかと感じ、全身にビッショリと嫌な汗が吹き出し、直ぐ後ろに熊が着いてきているという幻想に絶叫を上げて走り出しそうになります。
結局のところ何事も起こらず、Jeepに戻って何キロか走った後小さなパーキングに車を止め、クーラーボックスから取り出した冷えたペプシを一気飲みしてから、現実に戻ってきました。
ゲンキンなモノで、ついさっきまでの恐怖は全く感じません。
ヤバかった。
ただそれだけが残りました。
いずれ熊と直に遭遇する事態に、自分なりにシュミレーションしていたつもりでしたが、あんな無防備な体勢での近距離遭遇は思い付きませんでした。
思い返せば、シースから抜きかけていたナイフを、途中で右手が止めた事が、助かった要因のひとつだったと考えます。
周囲に漂った微かな鉄の匂いに、面倒事を嫌った熊が身を退いたのでしょう。
もし引き抜いて身構えていたなら、攻撃の気配を感じ取った熊と、命のやり取りとなったかもしれません。
体勢が不利、渓流の中足元も不備、そして命懸けの戦いに突入する気構えが全く成っていない自分が、恐怖に駆られて抜いたナイフなど、怒りモードに入った熊にとってはつま楊枝程度のモノだったでしょう。
自分の見通しの甘さを痛感した一日でした。
これは特殊な例でもなんでもありません。
実際にキャンプ場で熊に教われる被害がニュースや全国紙で報道されています。
また熊に限らず様々な野生動物との遭遇は当たり前のようにあり得ることと考えてください。
特にここ東北ではちょっと山に入れば熊に注意の看板はいくらでも目にします。
それだけ熊との遭遇は珍しい事ではないのです。
それらに対して、しっかりとした対策と心構えは怠らない事です。
なんと言っても、今ここにいるのはあなた一人なのですから・・・
2、ここ数年残念なことにキャンプ場での盗難、女性キャンパーへの暴行事件、キャンプ場からの女児の失踪事件などがニュースやネットでも大きく取り上げられるようになりました。
そのうちにキャンプ場に交番の設置やガードマンのパトロールが必要になるのではないでしょうか?
残念なことです。
しかし嘆いていても事は始まりません。
これからもキャンプという趣味を続けていくからには、しっかりした対策をとらなければいつか自分が被害者の立場に立たされるかも知れないのです。
ここからは自分個人が行っている対策方法なども織り混ぜたお話になります、ちょっと刺激が強めな事例などもありますのでどうかご容赦を。
まずキャンプ場に入り込んでくる犯罪者を、気の迷いでたまたまやってしまったのではないか。とか、解放感や酒が行きすぎてうっかりとやらかしてしまったのだろう。などと良心的な解釈で見ない事です。
確かに酒が過ぎて問題を起こす者もいますが、計画的にキャンプ場に入り込んでくる犯罪者は、そんな甘いものではありません。
彼らは、自分達の犯罪が十分遂行可能、あるいは成功する可能性が高い、そして怪しまれたり逮捕される可能性が低いこと。
それらを冷静に計算して、都市から離れたキャンプ場にワザワザ足を運んでいるのです。
当然それに対応した心構えで不審者に対処しなければならない訳です。
例えば、”あの人はあの木陰でいったい何をしているのだろう?”
そんな感覚を覚えたら、その感覚を気のせいだろう。などと決して考えない事です。
大きな街中の公園であれば、木陰のベンチで一休みしている人もいるでしょう。
公園の奥でひとときを楽しんでいるカップルがいても、何の不思議もありません。
ただキャンプ場、特に人気の少ない野営場で不可解な行動をしている人物を目にしたら、決して不用意に目を離さない事です。
例えば、その人物の服装や雰囲気に違和感を感じないか?
行動や態度に不振なものや粗暴な感じがしないかなど、キャンプを楽しむというような感覚から何か外れているような違和感を覚えるかも知れません。
管理人のいるキャンプ場なら、どの辺りの場所にこんな服装で何かを覗き込んでいるような不振な者がいる。
出きるだけ具体的に管理人に報告することです。
ただ漫然と、変な人がいる。だけでは報告された管理人も”何かの勘違いなのでは”から物事を考えるので、初動が遅れたりして結局見失ってしてしまえばワザワザ報告した意味が無くなってしまいます。
逆に適切な報告であれば、ヒトは動いてくれます。
あそこのキャンプ場は不審者がウロウロしていて怖い。
そんな噂でもネットに流れてしまえば、確実に利用者の減少に繋がるからです。
さらに一歩進めて”自分の身を守る”事を最優先とします。
その不審者が何を求めているかを考えて見ることが必要です。
例えばファミリーが多く、混雑しているようなキャンプ場であれば、キャンプギアや貴重品の盗難を目的としている可能性が高いでしょう。
逆に人気の少ない山奥の野営場などでは、ソロキャンプ中の婦女子への暴行や駐車場に停めてある車の車両荒しや盗難等が考えられます。
したがって、そのような犯罪者の傾向を見定め、自分のキャンプサイトの状況をしっかり把握することです。
例えば自分のテントのすぐ側に深い茂みがあって、その奥は良く見えない。
あるいはソロを楽しみたくて。周囲に誰もいないような場所にテントを張っている。
など、犯罪目的で接近してくる不審者から自分とテントサイトはどのように見えているのか?
この辺りの判断から始めてみましょう。
そしてしっかりと対策も考えて見るべきです。
もしキャンプサイトから、何かギヤを盗まれた。としたら、それはあなたに犯罪者がつけこむ隙があったと考えてください。
今回は助かったのだと。
次はあなた自身が犯罪に巻き込まれる可能性が高いということです。
私利私欲で物を考える日本人が増え、爆発的に外国人犯罪者が増加している今の日本。
これが現実です。
3、今までの書き込み等からお分かりいただけるかと思いますが、自分はキャンプ以前に野山をJeepで走り回る事が大好きです。
しかしここ何十年かの違法投棄やどこにでも車を停めたりゴミを捨てていくマナーの悪い釣り人や山菜採りのおかげで、立ち入り禁止の看板と道を塞ぐロープに、趣味の範囲は狭められ続けています。
そのような狭められた状況のなかで、素晴らしい景色や美しい景観を目にすると、とても感動を覚えるものです。
そしてそんな景色に出会える時はなぜかいつも一人なのです。
そんな素晴らしい瞬間を少しでもとどめようとシャッターを切るのですが、所詮素人の写メです。
あとで画像を確認してもそのときの感動を半分も覚えないのです。
しかしその時の状況だけは目の奥にしっかりと焼き付いています。
そんな自分が今まで体験した不可思議な事や体験談をうかがった不思議なお話をいくつか紹介します。
○携帯電話が普及し始めたころと記憶しています。
フラッと出掛けた岩手の奥地で道路脇に車を止め、体を伸ばしながらマップを確認していました。
秋晴れの昼前で、珈琲片手に一服していた時、
カランカラン・・・カランカラン・・・
遠くから熊鈴の音が微かに聞こえるのどかな風景でした。
タバコを揉み消してその林道と思われる(地図には載っていないため正確な場所は不明)細い道を30分ほど走ると道路が二股に別れます。
どちらも同じくらいの広さで、どちらを選ぶか判断できません。
また車を脇に寄せ、少しばかり道を歩いて見ます。
路面に残っているタイヤ痕の多さとタイヤパターンの違いで見当をつけます。
左の道は大型トラックが走ったようなゴツいタイヤ痕が多く、造林業者さんの使っている作業道路と判断、左の道に入ろうと車に戻ろうとしたときでした。
カランカラン・・・カランカラン・・・
また熊鈴の音色が聞こえてきました。
たぶんさっきと同じ音です。
熊鈴の音は特徴あるものも多く、聞き分けることも難しくはありません。
カラン・・・カランカラン・・・
しかも、
”近いな・・・”
熊鈴の聞こえる場所とは大体決まっていて、要するに登山道か何かのハイキングコースでなければ聞こえてくるという事はありません。
ここは山間部の峠道です。
”こいつは、サッサと離れた方がいいな。”
車に乗り込み数分走ると、ガードレールや注意標識が見えたので間違っていなかったことがわかります。
標識があるという事は、その道路は少なくとも市町村が管理していることになり、廃道でもない限りどこかの道に繋がります
逆にガードレールも何もない道路は、個人が作った作業用の私道である可能性が高いのです。
走っていると山道は沢沿いの細い道に繋がりました。
とうに昼を過ぎていたので飯にしようと脇道にそれ、道路脇にシートを広げて蚊取り線香に火をいれ、湯を沸かしカップ麺とおにぎりを堪能したあと、少し横になります。
自分は昼食後必ず仮眠をとることにしています。
秋晴れの中、意識が遠退いていきます。
カランカラン・・・カラン・・・カランカラン・・・
跳ね起きました。
ものすごく近い! ヘタするとすぐ側!!
車の中にシートと細々とした道具類蚊取り線香を放り込み、アクセルをおもいっきり踏み込みます。
・・・・・人家が見え始め、販売機の前に車を止めてコーラを買い込み、一服しながら考えました。
”あれはいったい何だったのか?”
今でもわかりません。
○真冬の冬山に友人と猟に出掛けた時の事です。
狩猟というのはあてずっぽうに山を歩いても、そう簡単には獲物に出会うことはありません。
猟期以外に山を調べて走ったり、川の位置、餌場の場所、隠れる事ができる藪の位置など地形を読んで当たりをつける訳です。
自分達二人もそんな場所の側に車を止め、装備を身に着けていたときです。
すぐ目の前の小道を鞄を持った中学生程度の男の子が歩いていきました。
サクサクと雪を踏みしめながら自分達の前を通りすぎ、下り道を曲がっていきます。
「どこに行くってンだ?」
「おかしいな・・・?」
自分達は不可思議に顔を見合わせます。
そして、手早く装備を身に着けて彼の後を辿ります。
30メーターも歩いたでしようか。
彼には追い付けませんでした。
自分達が追いかけた雪道に残る一対の足跡、それはろくに除雪もしていない山奥に通じる道です。
そもそもここは道路ですらないのです。
自分達が車を止めるために分け行った、猟場の側の田んぼか畑に通じる畦道で、50メーターも戻れば普通に道路が通じているのです。
そんな畦道を、山に向かって中学生が歩いていく理由がわかりません。
さらに言えばこの周囲数キロ以内で人家を見かけた記憶はありません。
自分達二人は雪が降りしきるなか、足跡が続く山道を無言で見つめるだけでした。
○これは日本海側に遊びに行った時の事です。
出発がすっかり遅れてしまい、目標としていた十二湖から帰ろうとしたときには辺りも薄暗くなり出した午後6時過ぎ。
駐車場にもほとんど車はなく誰も人はいませんでした。
十二湖とは青森県を跨いでここ八戸市から反対方向にある深浦町にある風光明媚な観光地で片道200キロ以上、およそ4時間以上のドライブとなります。
途中の休息時間も考えると今日中に自宅にたどり着けるか微妙なところです。
当時はまだ若かったのであまり気にもせず、最短ルートと考えた十和田八幡平国立公園の山の中を夜間にたった一台で突っ切るルートを選択したのです。
何度も走っているルートなので、自分にとっては明るいか暗いか程度の違いでしかありません。
むしろ危なっかしいサンデードライバーや追い越せない観光バスなどが居ない分走りやすい位です。
そして快調に山道を走っているとき訪れるべきものが下半身に訪れ、公衆トイレなどはもちろんないので、道路脇に車を止め、天空の素晴らしい星空を堪能しながら用を足していると、
真っ黒い何かが頭の上を通過していきました。
それは何の音もせず、木々の梢の上を掠める位の高さを飛行していきました。
恐らく鳥でしょう。
しかし翼端から翼端まで、4メートルから6メートル?
何の目標物のない空中の物体の大きさですから、ハッキリとはわかりません。
もっと大きいかも、逆に小さかったかもしれません。
羽ばたきひとつせず目の前を滑空して木々の間に消えていきました。
その間恐らく数秒。降ってきそうな星空を背景に、黒い影は確かに存在していました。
○この話は野営場で親しくなったベテランキャンパーからうかがったお話です。
その方は家族と何回か行ったキャンプ以外は、30年以上全てソロと言う筋金入りのソロキャンパーで、足の向くまま行けるところならどこにでも行ってソロキャンプするという大先輩のようなお方でした。
ただし設備の整った今風のキャンプ場と、混雑は苦手。
という方だったので自分と話が合い、お互い話が弾んだのです。
その方が、
「一度だけキャンプしてて逃げ出した事がある」
そう言い出しました。
「何か問題でも起きましたか?」
「いや、馬鹿馬鹿しいかもしれないが・・・」
話はこうです。
コロナによるキャンプブームなんてものが起きるはるか以前の話。
その方を仮にBさんとします。
仕事が立て込んで中々まとまった休みが取れなかったBさんは、秋の初め頃ようやく3連休を取って山中の野営場にテントを張ったそうです。
ご存じの通り、野営場と言うのは、トイレと炊事場ががあるだけの最低限の施設だけを備えたキャンプ場の事。
平日だったそうで、まだキャンプブームなんてものが無かった時代なので、キャンプ場には誰もおらず、静かなソロキャンプを楽しんでいたそうです。
初日の夕方、晩飯の準備に入る前にトイレに行ったらトイレのドアが開いていたそうなので、用を済ませたあとしっかりとドアを閉めて、テントに戻りました。
そして寝る前にトイレに行くと、またドアが開いている。
・・・?
そのドアはどこでも良く見る、握り玉と呼ばれる真ん中に鍵穴がついた取っ手を回して開閉するドアで、建て付けてまだ新しい物で、閉じてしまえば簡単に開く物では無かったそうです。
そのトイレは炊事場から少しばかり離れた所に建っており、炊事場の灯りで周囲を見回しても人の気配は全く無く、違和感を感じながらテントに戻ったそうです。
そして、その夜・・・・
深夜のこと、ビールを飲み過ぎたせいでしょう。
下半身に切迫した危機を感じた彼は、何となく嫌なものを感じながらもライト片手にトイレに向かいました。
その時トイレのドアは閉まっていたそうです。
ホッとしてトイレのドアに手を伸ばした瞬間、
バンッ!!
誰かが内側から蹴飛ばしたような勢いで、ドアが開いたそうです。
薄暗いトイレの中には誰もいなかった事だけは間違いなかったと本人は言っています。
うを!
悲鳴をあげて彼は車に飛び乗り、何もかも投げ出して逃げ出したそうです。
M「それは怖いですね」
B「う~ん、あれは何だったんだろう。
・・・あなたにはそんな体験はないのかい?」
M「俺ですか・・・俺はそう言うモノを見る事はあまりできないみたいですけど、幾つか不思議なモノを見たり聞いたりしたことはあります」
B「ほう、聞きたいね」
M「いいですよ。
これは観光地のトイレで知り合いが体験した話なんですが・・・」
地名は伏せますが、そこは岩手県、地元では知らぬ者などいない有名な観光地です。
数100メーターは切り立った岩山の崖から巨大な岩棚が突きだし、そこから下を覗き込めば、どんな強心臓の持ち主でも身がすくむ思いをするでしょう。
そしてその突端のは小さな祠が祭ってあり、お酒などが供えてあります。
実際はその場所に行くには危険が伴うので、小道の入り口には簡単な柵で塞がれています。
そこには大きな展望台が設置されているので、どなたでも見晴らしのよい景色を楽しむことができます。
車も数台駐車が可能で、最近は整備された小綺麗なトイレも設置されてるようです。
人気もほとんどなく、落ち着いた雰囲気の観光名所です。
そこに平成の最初の辺りでしょうか?
知り合いが訪れたそうです。
もう夕方で缶コーヒーとタバコをお供に風景を楽しんだあと、車に乗る前に大きい方を処理しようと個室に入ったそうです。
本当に小さなトイレで、男性用小がひとつ、個室がひとつ。
幸いロールペーパーは供えてあったので、ゆっくりと用を足していると、
バタン
隣の女性用トイレに誰か入って来ました。
そして、
「おかあさん、おかあさんっ」
入ってきたのは少女らしく、母親を探しているらしいのです。
「おかあさん、どこ、おかあさん」
ドンドンとドアを叩く音が聞こえてきます。
「おかあさん、おかあさんっ!」
半ベソ状態の少女がトイレを飛び出して行きました。
ようやく爆撃が完了し、後始末を終えた彼はジーンズを引き上げ、下半身をチェックしてからトイレを飛び出したそうです。
いかに緊急事態とは言え、ズボンをずり下げた状態で少女を追いかけていたのでは、どのような理由があろうと、問答無用で逮捕されます。
蹴飛ばすようにドアを開け、周囲を見回し少女の姿を探します。
見当たらなかったそうです。
「・・・?」
展望台に戻ると自分の車が止まっているだけ。
当然あるはずのもう一台の車はありません。
ここは山の中、人家は15分も細い山道を下った下です。
そのまま道を上っていってもただ山奥に踏み込んで行くだけで、車でも走行困難になるような道です。
「どこにいった・・・?」
なんとも言えない違和感を感じながらも、夕暮れの中10分程度辺りを探したそうですが、とうとうその姿を見つけ出すことはできなかったそうです。
少女がトイレを出てから、後を追うまでの時間は30秒程度。
駐車場に車が無いいじょう、少女は徒歩でこんな山奥に母親を探して単独で来たのか。
道を挟んで反対側は急な法面、展望台側はそれこそ崖で、探すところはどこにもないのです。
そこまで考えてから彼はとある噂を思い出しました。
その岩棚は有名な自殺の名所であるという、真偽の疑わしい話を。
もし、本当に、あそこから親子が無理心中を計ったとしたら、とてつもない高さからの落下です。
途中何かにぶつかって親子の手が離れ、別々の場所に落ちてしまえば・・・
そんなことを考えながら彼は車のキーを捻り、慎重に暗い山道を下ったそうです。
B「もしその女の子が死んだ事に気づいてなくて、いつまでも母親を探しているのなら、なんとも哀れな話だな」
M「死人に同情するのは厳禁だそうですが、可愛そうな話です」
B「・・・テレビのバラエティ番組やネットに乗っているような心霊話の大半は、見間違いや暇な若者の戯言なんだろうが、不思議なことってのは、あるからねぇ」
M「ありますよね」
そうして、彼のテントの前で焚き火とランタンの明かりの中、色々な話が深夜まで続き、翌朝、いつかどこかでの再開を約束し、さっぱりとお別れしたのでした。
希に出会う、このような一期一会も、ある意味ソロキャンプの魅力なのかもしれませんね。
今回はいつもと少しばかり毛色の違った話になりました。
自分的には女性のソロキャンパーが増えてくださるのは良いことだと思います。
技術的にも精神的にもシッカリと自分の面倒を見れる方であれば、老若男女を問わないのがこの世界です。
ただ、インスタ映えするからとか、友人に自慢したいからと言った、何か勘違いしているような理由でのソロキャンプは、”もしもの時”自分と周囲にどのような結果をもたらすか今一度良く考える事です。
今年の投稿はこれで終わりたいと思います。
来年もまたよろしくお願いします。
皆様良いお年を
では、また、
2022年11月13日
独り言・・・・これからのキャンプ
みなさん、こんにちわ。
Masada556です。
11月も半ばに入り、東北のキャンプ場は殆どが冬ごもりに入りました。
これから来年の5月ころまで長く暗いシーズンオフとなります。
はぁ~、つらい季節の始まりです。
今回は少しばかり、いつもとは違ったお話をしてみたいと思います。
このブログにいらしておられる読者の方々、ほとんどの方々は、キャンプ又は何かアウトドアを趣味にしている方達と思います。
なん10年とキャンプを続けておれられるようなベテランから、今始めたばかりというような、初心者の方、又はキャンプデビュー目前の方まで様々な方達がこの小さなブログに目を通していただけるのは大変嬉しく思っております。
自分も他のブロガーのサイトを覗いてみたり、時間があればYOUtubeの動画を色々と拝見したりすることはよくあります。
去年くらいの事でしたか、とある書き込みが目につきました。
「YOUtubeにキャンプ動画を公開しているのだが、視聴者数がぜんぜん延びない」
その投稿動画に行ってみましたが、当日の視聴者が自分を含めて10人前後、もちろん、いいねマークには1つも入っていません。
一応最後まで拝見させていただきましたが、ごく普通のキャンプ動画でした。
某キャンプ場に到着、テントを立てサイトの設営、火を起こし晩御飯とお楽しみの一杯、寝袋に潜り込み、朝を迎えて軽い食事、撤収・・・良いキャンプでした、完。
ここからは、あくまで自分の感想に過ぎませんので、もし不快に感じられた方がおられましたら、どうかご容赦を。
はっきり言わせていただければ、このような動画をいくら作っても視聴数は延びないと自分は考えます。
動画の一本も作ったこともない者が知ったようなことを書き込むのも、動画制作者の方々から見ればちょっと腹の立つ事かもしれません。
自分の古い友人に広告業界の人間がいるので、動画を作ることが非常に根気のいる大変な作業であることは、それなりに理解はしています。
しかし、視聴者数の問題はYOUtubeに投稿している方ならば誰でもいずれ突き当たる問題だと思います。
自分のように道楽で文を書いている人間でも、やはり視聴者数は気になるものです。
ましてやアフリエイトの収入を期待している方等にとっては、無視できない問題でしょう。
では何が視聴者数の妨げになっているのででしょうか?
それは、「当たり前の事をわざわざ動画にしている」
自分はそのように考えます。
確かに初心者やこれから始めようと考えている方達には、最初は興味を持たれるかも知れません。
しかし初心者もいつかは経験を積み、成長して自分のキャンプスタイルを作っていくでしょう。
その辺りになっていくとキャンプ動画そのものに興味を感じなくなるかと思います。
つまりは、自分が実際にキャンプ場でやっている事を、他人が時と場所を変えただけで、おんなじ事を繰り返しているわけで、それを再度動画で見て面白いと感じるかと言うことです。
なんと言うか、出来立てのアツアツラーメンを味わった後に、のびてしまった同じ味のラーメンを晩飯のテーブルに乗せられる気分なのです。
それも物凄い数のブロガー達が凌ぎを削っている世界ですから、その中から上位に昇っていくには、並みならぬ努力と才能、時代や空気を捉えてリアルタイムで投稿していく先読み感覚が必須でしょう。
それは他のブロガーの方達も感じているのだと思います。
動画の中に、豪雨の中の・・・、可愛い訪問者が・・・、恐怖の一夜・・・等と言うような、人の目を引くようなタイトルを見かける事が多くなりました。
最近ブログを書いている時、少しばかり考える事があります。
このキャンプブームと言う奴はいったいいつまで続くのだろう?
ここ東北のキャンプ場ですと、それほど極端にはキャンプ人口が増えたと言うような感じはあまりしません。
もっとも辺鄙な野営場ばかり狙ってキャンプを楽しんでいるような自分と現代のキャンパーとでは、目指すものが違いすぎるのかもしれませんが・・・
ただ最近はキャンプに出掛ける時は同じ方向にもう1つ、つまり候補のキャンプ地を2つ考えてから向かうようにしています。
今年、あまりにも人が多く、二度ほど撤退した経験があります。
そんなことは今まで無かったことです。
人の多いキャンプ場を観察しながら歩くと、色々なモノが見えてきます。
大きなワンボックスに家族からペットまで連れて、大荷物をサイトに広げるファミリーキャンパー。
2~3人の少人数グルキャン、特に別々のテントを設営、食事の時だけ一緒にいるようなスタイルも見かけるようになりました。
また本当に簡素な装備で一晩を楽しみ、朝方には素早く撤収、風のように消えてしまうキャンパー。
キャンプ場を渡り歩き、長く旅を続ける、渡り鳥のようなキャンパーもいます。
いずれも各々のスタイルを持ち、楽しそうにアウトドアを満喫されています。
しかしその中に違和感を感じさせるキャンパーが混ざっている事が多くなりました。
例えば、バイクでフラりと訪れて、サイトを設営後、ずっとスマホを弄っているだけで特に何をするわけでなく、食事もカップ麺などの軽いもので済ませ、夜はまたスマホを弄り何か音楽を聞いているだけ・・・
バイクのナンバーを見れば県内です。
いったい何をしにキャンプ場に来ているのだろう?
もちろんキャンプスタイルなど十人十色で自分のようなものが何か文句をつけるような筋も無いわけですが、彼からはキャンプやアウトドアを楽しもうと言うような雰囲気が、全く感じられないのです。
彼のやっていることは、ワザワザキャンプ場まで足を運んですることなのか?
カップ麺を食べてスマホをいじり、音楽を聞く。
これなら自宅でやっていれば良いことで、未だ収まらぬコロナ騒ぎの中、そとに足を運んでまでやらなければならない必然性は無いのです。
つまり自分のように、アウトドアが好きではなく、他の理由でキャンプをしている訳です。
流行っているから。みんながやっているから。コロナで他のことができなくなっているから。
おそらくこのような理由でキャンプ場に足を運んでいるのではないでしようか。
では、このコロナ騒ぎが終息したらどうなるのでしょう?
今現在、規制状況もどんどん緩和され、移動規制もほぼ撤廃されました。
屋外でのマスク使用も大幅に緩和され、海外への旅行も規制緩和が進んでいます。
この3年間、押し固められるようだった逃げ場の無い社会生活が、徐々に元に戻り始めているのです。
コロナ対策の基本であった3密を避けることが可能な、アウトドアレジャーの代表格だったキャンプが注目を集めただけ。
他にも色々と理由があるのでしょうが、現状のキャンプブームを、業界の方々は概ねこのように評論しています。
自分もその通りであろうと考えます。
たまにキャンプ特集などと銘打った雑誌などに目を通すと、冒頭はキャンプの魅力といった感じで始まっています。
つまりはアウトドア、特にキャンプ等に全く興味の無かった方々にイチイチ魅力とか面白さなどを説明しなければならない程社会的な認知度が低い、極限られた人間が楽しんでいた趣味だったのです。
そこにコロナの影響で一気に人が流れ込んできたのです。
小さかったマーケットは膨れ上がり、キャンプ沼なんて言葉まで作られました。
キャンプ場も増設、拡大され、それでも追い付かず、予約は3ヶ月前でないと取れない状況であると聞いています。
規制が緩和されつつある今が、キャンプブームのピークであると自分は考えます。
元々キャンプと言われる趣味は近代文明の対極に位置するもので、極端な話、初歩的な文明しか無かった紀元前の時代や大陸の遊牧民のような生活を再現しているようなものであって、当時それがあまりにも不自由だったために研究と開発がなされて現代に至った訳です。
それを大金をかけて道具を集め、大昔の生活をワザワザ野山に出掛けて再現しなければならないのか、興味の無い人には全く理解できないのは当然のことでしょう。
バーベキューをやりたいのなら、どこかのバーベキューハウスに出掛ければ良いのです。
設営の手間暇は要らず、設備の整った専門店で食べるバーベキューは美味しいに決まっています。
仲間同士で集まって呑みたいのであれば、居酒屋に予約の電話を入れれば良いのです。
エアコンの効いた快適な店舗に集まり、予算に見合った料理が提供され、誰憚ること無く好きなだけ呑み明かし、帰りはタクシーで自宅に戻り、そのままベッドに潜り込めば良いのです。
無限に集ってくる虫に悩まされる事もなく、暗い山道で転んで怪我をする心配もありません。
このままさらにコロナ対策が充実していけば、ほぼ以前と同じ社会生活を取り戻せるでしょう。
その日がくれば嫌でも気がつくはずです。
自分はこんな山奥に来て、たった一人で何をやっているのだろう・・・?
キャンプ仲間たちがどんどん離れていき、ある日雨の中ずぶ濡れになって撤収している時、はっと気がつく自分がいるかもしれません。
おそらくコロナ騒ぎ以降にキャンプを始めた方々の2/3は、このような理由でキャンプ場から去って行くかと思います。
近い将来必ず訪れるであろうその時に、これほどまでに膨らんだ業界がどう変化していくのか、興味深いところでもあります。
逆にブームが過ぎ去った後にもキャンプという趣味から離れなっかった方々には、良い環境が残されていくかと思います。
予約が取りやすくなった静かなキャンプ場。
本当のキャンプの面白さを理解しているキャンパー達なので、以前のようなマナー問題も少なくなって行くでしょう。
またキャンプを止めてしまった人々の出品で、中古市場が大分賑わうでしょう。
もちろん規模の縮小してしまう業界ですから、良いことばかりではありませんが、自分に言わせれば、単に元に戻るだけの話なのです。
もし、これからキャンプ、またはソロキャンプに挑戦しようかと考えている方がこのブログを読んでくださったいるのであれば、流行りなどに流されることなく、
「なぜ、自分はキャンプという世界に足を踏み入れようとしているのか?」
もう一度じっくりと考える良い時期だと思います。
特に数度のグルキャンで経験を積み、いよいよソロキャンに挑戦というかたには少しだけアドバイスを。
人によって多少の違いはありますが、
最終的には、殆ど人気のない野山で、一言も話さず、何日か一人で生きていく事が当たり前な感覚になっていきます。
大雨のタープの下で珈琲を飲みながら本を読み、浄水器を通した川の水で食事を作り、全く人工的な照明が辺りに無い夜の山野で、灯油ランタンのとぼしい灯りの中、木々のざわめきと虫たちのコンサートに耳を傾けながら美味い酒を味わい、寒い季節には落ちて来そうな星空の下、炭火で凍え気味の手足を暖め、夜明けには凍っているコップの水を横目に寝袋から無理矢理這い出すようなキャンプが、楽しいと感じる人間に変わってしまいますよ。
では、また。
Masada556です。
11月も半ばに入り、東北のキャンプ場は殆どが冬ごもりに入りました。
これから来年の5月ころまで長く暗いシーズンオフとなります。
はぁ~、つらい季節の始まりです。
今回は少しばかり、いつもとは違ったお話をしてみたいと思います。
このブログにいらしておられる読者の方々、ほとんどの方々は、キャンプ又は何かアウトドアを趣味にしている方達と思います。
なん10年とキャンプを続けておれられるようなベテランから、今始めたばかりというような、初心者の方、又はキャンプデビュー目前の方まで様々な方達がこの小さなブログに目を通していただけるのは大変嬉しく思っております。
自分も他のブロガーのサイトを覗いてみたり、時間があればYOUtubeの動画を色々と拝見したりすることはよくあります。
去年くらいの事でしたか、とある書き込みが目につきました。
「YOUtubeにキャンプ動画を公開しているのだが、視聴者数がぜんぜん延びない」
その投稿動画に行ってみましたが、当日の視聴者が自分を含めて10人前後、もちろん、いいねマークには1つも入っていません。
一応最後まで拝見させていただきましたが、ごく普通のキャンプ動画でした。
某キャンプ場に到着、テントを立てサイトの設営、火を起こし晩御飯とお楽しみの一杯、寝袋に潜り込み、朝を迎えて軽い食事、撤収・・・良いキャンプでした、完。
ここからは、あくまで自分の感想に過ぎませんので、もし不快に感じられた方がおられましたら、どうかご容赦を。
はっきり言わせていただければ、このような動画をいくら作っても視聴数は延びないと自分は考えます。
動画の一本も作ったこともない者が知ったようなことを書き込むのも、動画制作者の方々から見ればちょっと腹の立つ事かもしれません。
自分の古い友人に広告業界の人間がいるので、動画を作ることが非常に根気のいる大変な作業であることは、それなりに理解はしています。
しかし、視聴者数の問題はYOUtubeに投稿している方ならば誰でもいずれ突き当たる問題だと思います。
自分のように道楽で文を書いている人間でも、やはり視聴者数は気になるものです。
ましてやアフリエイトの収入を期待している方等にとっては、無視できない問題でしょう。
では何が視聴者数の妨げになっているのででしょうか?
それは、「当たり前の事をわざわざ動画にしている」
自分はそのように考えます。
確かに初心者やこれから始めようと考えている方達には、最初は興味を持たれるかも知れません。
しかし初心者もいつかは経験を積み、成長して自分のキャンプスタイルを作っていくでしょう。
その辺りになっていくとキャンプ動画そのものに興味を感じなくなるかと思います。
つまりは、自分が実際にキャンプ場でやっている事を、他人が時と場所を変えただけで、おんなじ事を繰り返しているわけで、それを再度動画で見て面白いと感じるかと言うことです。
なんと言うか、出来立てのアツアツラーメンを味わった後に、のびてしまった同じ味のラーメンを晩飯のテーブルに乗せられる気分なのです。
それも物凄い数のブロガー達が凌ぎを削っている世界ですから、その中から上位に昇っていくには、並みならぬ努力と才能、時代や空気を捉えてリアルタイムで投稿していく先読み感覚が必須でしょう。
それは他のブロガーの方達も感じているのだと思います。
動画の中に、豪雨の中の・・・、可愛い訪問者が・・・、恐怖の一夜・・・等と言うような、人の目を引くようなタイトルを見かける事が多くなりました。
最近ブログを書いている時、少しばかり考える事があります。
このキャンプブームと言う奴はいったいいつまで続くのだろう?
ここ東北のキャンプ場ですと、それほど極端にはキャンプ人口が増えたと言うような感じはあまりしません。
もっとも辺鄙な野営場ばかり狙ってキャンプを楽しんでいるような自分と現代のキャンパーとでは、目指すものが違いすぎるのかもしれませんが・・・
ただ最近はキャンプに出掛ける時は同じ方向にもう1つ、つまり候補のキャンプ地を2つ考えてから向かうようにしています。
今年、あまりにも人が多く、二度ほど撤退した経験があります。
そんなことは今まで無かったことです。
人の多いキャンプ場を観察しながら歩くと、色々なモノが見えてきます。
大きなワンボックスに家族からペットまで連れて、大荷物をサイトに広げるファミリーキャンパー。
2~3人の少人数グルキャン、特に別々のテントを設営、食事の時だけ一緒にいるようなスタイルも見かけるようになりました。
また本当に簡素な装備で一晩を楽しみ、朝方には素早く撤収、風のように消えてしまうキャンパー。
キャンプ場を渡り歩き、長く旅を続ける、渡り鳥のようなキャンパーもいます。
いずれも各々のスタイルを持ち、楽しそうにアウトドアを満喫されています。
しかしその中に違和感を感じさせるキャンパーが混ざっている事が多くなりました。
例えば、バイクでフラりと訪れて、サイトを設営後、ずっとスマホを弄っているだけで特に何をするわけでなく、食事もカップ麺などの軽いもので済ませ、夜はまたスマホを弄り何か音楽を聞いているだけ・・・
バイクのナンバーを見れば県内です。
いったい何をしにキャンプ場に来ているのだろう?
もちろんキャンプスタイルなど十人十色で自分のようなものが何か文句をつけるような筋も無いわけですが、彼からはキャンプやアウトドアを楽しもうと言うような雰囲気が、全く感じられないのです。
彼のやっていることは、ワザワザキャンプ場まで足を運んですることなのか?
カップ麺を食べてスマホをいじり、音楽を聞く。
これなら自宅でやっていれば良いことで、未だ収まらぬコロナ騒ぎの中、そとに足を運んでまでやらなければならない必然性は無いのです。
つまり自分のように、アウトドアが好きではなく、他の理由でキャンプをしている訳です。
流行っているから。みんながやっているから。コロナで他のことができなくなっているから。
おそらくこのような理由でキャンプ場に足を運んでいるのではないでしようか。
では、このコロナ騒ぎが終息したらどうなるのでしょう?
今現在、規制状況もどんどん緩和され、移動規制もほぼ撤廃されました。
屋外でのマスク使用も大幅に緩和され、海外への旅行も規制緩和が進んでいます。
この3年間、押し固められるようだった逃げ場の無い社会生活が、徐々に元に戻り始めているのです。
コロナ対策の基本であった3密を避けることが可能な、アウトドアレジャーの代表格だったキャンプが注目を集めただけ。
他にも色々と理由があるのでしょうが、現状のキャンプブームを、業界の方々は概ねこのように評論しています。
自分もその通りであろうと考えます。
たまにキャンプ特集などと銘打った雑誌などに目を通すと、冒頭はキャンプの魅力といった感じで始まっています。
つまりはアウトドア、特にキャンプ等に全く興味の無かった方々にイチイチ魅力とか面白さなどを説明しなければならない程社会的な認知度が低い、極限られた人間が楽しんでいた趣味だったのです。
そこにコロナの影響で一気に人が流れ込んできたのです。
小さかったマーケットは膨れ上がり、キャンプ沼なんて言葉まで作られました。
キャンプ場も増設、拡大され、それでも追い付かず、予約は3ヶ月前でないと取れない状況であると聞いています。
規制が緩和されつつある今が、キャンプブームのピークであると自分は考えます。
元々キャンプと言われる趣味は近代文明の対極に位置するもので、極端な話、初歩的な文明しか無かった紀元前の時代や大陸の遊牧民のような生活を再現しているようなものであって、当時それがあまりにも不自由だったために研究と開発がなされて現代に至った訳です。
それを大金をかけて道具を集め、大昔の生活をワザワザ野山に出掛けて再現しなければならないのか、興味の無い人には全く理解できないのは当然のことでしょう。
バーベキューをやりたいのなら、どこかのバーベキューハウスに出掛ければ良いのです。
設営の手間暇は要らず、設備の整った専門店で食べるバーベキューは美味しいに決まっています。
仲間同士で集まって呑みたいのであれば、居酒屋に予約の電話を入れれば良いのです。
エアコンの効いた快適な店舗に集まり、予算に見合った料理が提供され、誰憚ること無く好きなだけ呑み明かし、帰りはタクシーで自宅に戻り、そのままベッドに潜り込めば良いのです。
無限に集ってくる虫に悩まされる事もなく、暗い山道で転んで怪我をする心配もありません。
このままさらにコロナ対策が充実していけば、ほぼ以前と同じ社会生活を取り戻せるでしょう。
その日がくれば嫌でも気がつくはずです。
自分はこんな山奥に来て、たった一人で何をやっているのだろう・・・?
キャンプ仲間たちがどんどん離れていき、ある日雨の中ずぶ濡れになって撤収している時、はっと気がつく自分がいるかもしれません。
おそらくコロナ騒ぎ以降にキャンプを始めた方々の2/3は、このような理由でキャンプ場から去って行くかと思います。
近い将来必ず訪れるであろうその時に、これほどまでに膨らんだ業界がどう変化していくのか、興味深いところでもあります。
逆にブームが過ぎ去った後にもキャンプという趣味から離れなっかった方々には、良い環境が残されていくかと思います。
予約が取りやすくなった静かなキャンプ場。
本当のキャンプの面白さを理解しているキャンパー達なので、以前のようなマナー問題も少なくなって行くでしょう。
またキャンプを止めてしまった人々の出品で、中古市場が大分賑わうでしょう。
もちろん規模の縮小してしまう業界ですから、良いことばかりではありませんが、自分に言わせれば、単に元に戻るだけの話なのです。
もし、これからキャンプ、またはソロキャンプに挑戦しようかと考えている方がこのブログを読んでくださったいるのであれば、流行りなどに流されることなく、
「なぜ、自分はキャンプという世界に足を踏み入れようとしているのか?」
もう一度じっくりと考える良い時期だと思います。
特に数度のグルキャンで経験を積み、いよいよソロキャンに挑戦というかたには少しだけアドバイスを。
人によって多少の違いはありますが、
最終的には、殆ど人気のない野山で、一言も話さず、何日か一人で生きていく事が当たり前な感覚になっていきます。
大雨のタープの下で珈琲を飲みながら本を読み、浄水器を通した川の水で食事を作り、全く人工的な照明が辺りに無い夜の山野で、灯油ランタンのとぼしい灯りの中、木々のざわめきと虫たちのコンサートに耳を傾けながら美味い酒を味わい、寒い季節には落ちて来そうな星空の下、炭火で凍え気味の手足を暖め、夜明けには凍っているコップの水を横目に寝袋から無理矢理這い出すようなキャンプが、楽しいと感じる人間に変わってしまいますよ。
では、また。
2022年10月09日
なぜ、ソロキャンプ その2
皆さんこんにちはMASADA556です。
秋も深まる9月後半に、降ったりやんだりの雨のなか、岩手の海岸沿いの野営場で藪蚊と戦い、完ソロを楽しみながら原稿を書いています。
今回はキャンプ、そしてソロキャンプの魅力と言ったものを掘り下げてみましょう。
もう10年以上前の事でしょうか?
とある趣味仲間から、
「何でキャンプなんてやるんだ。
いったいどこが面白いんだ?」
そう問いかけられた事があります。
もちろん彼に悪気があった訳ではなく、年に何回か他の仲間たちとアウトドアを楽しんでいる事が理解できないのでした。
んー・・・?
意外と答えずらい質問ですよね。
自分的には好きなことを追求することで、精神的な充足感を得ることが趣味だと認識しているのですが、何故キャンプと言われると、余りにっ直球過ぎて返事に困った記憶があります。
皆さんはどうでしょう、何でキャンプに行くのですか?
おそらく、一口では中々言い表せないのではないですか?
自分は子供時代の経験が、大きく関わっているようです。
父の趣味が、渓流釣り、狩猟、山菜採り等の山歩きだったので、一年中父にくっついては、山歩きをしていた時代があります。
ただ
銃は自分の性格と相性がバッチリだったようで、物心がついてからもう50年近く趣味としてきました。
一方釣りはと言うと、からっきしダメで全く興味がわかず、間違って何かが釣れても全然面白いとは感じませんでした。
んじゃあ銃はどうなのだ。と言われるとこれもまた中途半端で、結局いまに至るまで銃砲の免許は取りませんでした。
自分がやりたいのは、プリンキングと呼ばれる、原っぱに物を並べて好きなように撃つ遊びや、ハンドがンやアサルトライフルを使ったスピード競技などを楽しみたいのであって、野山の獣を一方的に撃つような真似に興味を覚えなかったのです。
あとは競技射撃しかお堅いこの日本で銃を撃つ趣味は許されておらず、クレー射撃と呼ばれる競技射撃しかできません。
これはクレー射撃場で射場に射出される、クレーと呼ばれる10センチ程の皿を撃ち落とす競技で、オリンピックなどにも採用されている世界的にもメジャーな競技射撃です。
これも自分には合いません。
最初は面白いのでしょうが、クレーを撃つ以外の事は一切許されず、型にハマりきった競技射撃など、いずれ飽きてしまうのは目に見えていたのです。
結局、狩猟、渓流釣り、山菜採りなどに共通しているアウトドアの世界だけが自分に一番しっくりくる趣味として、飽きることなく途切れ途切れではありましたが、未だに続いているわけです。
では皆さんにうかがいます。
アウトドアの様々な趣味、そしてスポーツの中から、なぜ敢えてキャンプを選んだか?
更にはソロキャンプの楽しみなど、ご意見があれば是非書き込んでください。
「キャンプのどこが楽しいんだ?」
これについての皆様のご意見も聞きたいものです。
自分の考え的には、ハッキリした答えは出ていません。
但し、自分が考えるソロキャンプの理想と言うのがありまして、
第一に海でも山でも景色が最高なこと。
自分がキャンプ場を選ぶ基準のほとんどがこれに尽きます。
後はトイレと炊事場だけあれば何もいりません。


9月の海です。
キャンプの帰りに海を見たくなって寄り道しました。
二つ目は、誰も居ないことです。
いわゆる完ソロと言うやつで、穏やかな天候の中、ランタンの明かりの下で珈琲を飲みながら好きな本を読んでみたり、バーボンを一杯やりながら満天の星空を眺める時間に、何とも言えない魅力を感じます。


静かなキャンプ場と美しい朝焼けはキャンプに欠かせない物の一つです。
三つ目は、山で食べるご飯の美味しい事でしょうか。
チマチマした不便な道具類を使って、火力の安定しない野外での料理は中々に難しいものです。
例えばご飯1つ炊くにもそれなりのテクニックが必要で、どのタイミングで炭火の上に飯盒を乗せるか見極めが肝心です。
どれだけ高温を維持できるかがご飯の味を大きく左右します。
最高の環境下でできたご飯は、もう匂いが違うのです。
コンロから下ろし、出来上がりから大体5分~8分蒸します。
これもその時のコンディションで変わります。
そして恐る恐る蓋を開けたとき、お米が立っている状態を確認できれば90%以上の成功率であり、美味いご飯であることは間違いありません。
口に入れた瞬間幸せを感じる事でしょう。

いつの年だったか忘れてしまいましたが、秋の終わりころだった事は覚えています。
山のキャンプ場で肌寒い中、オデンを煮込んでいる最中です。
最後は自然の空気です。
奥深い野営場で感じる少し湿ったような独特な空気。
明け方の朝靄のなか、思いっきり深呼吸した時の空気の香り。
フィトンチッドに包まれて、眠気の残った身体がゆっくりと活動を開始します。
目覚まし時計に叩き起こされる日常がいかに不自然な物なのか、実感出来るひとときでもあります。
日が暮れれば周囲は闇に沈み、月と星空以外の明かりは自分のサイトだけになります。
虫達の演奏会に耳を傾け、清々しい夜風に当たりながらゆっくり酒を口に運び本を読んでいると、自然とアクビが出てきます。
そろそろ眠る時間でしょう。
サイト周辺を軽く片付け、柔らかなベットに身を横たえると、自然に体から力が抜け、意識が沈んでいきます。
おそらくは、これが「人」という動物の、自然なライフサイクルなのでしょう。

とある山の中腹にある野営場での二泊三日のキャンプです。
天候不順なため、タープのみ設営して車中泊の予定でしたが、風が気持ちいいので、そのままタープの下で眠ることにしました。
たまにこんなタープ泊をするのですが、虫の少ない時期場所を選ばないと、顔が虫刺されでとんでもない事になるので余りお勧めはしません。
気分的には最高なんですが・・・
以前、大ファンだったとある漫画家の作品が3Dアニメ化されたとき、その物語の重要な位置を占めるキャラクターが呟いた言葉が、今でも耳に残っています。
「人とは、自分から進んで檻の中に入りたがる、変わった生き物だな」
高度に集積化した社会に生きている現代人とは、檻の中の動物なのかもしれませんね。
そんな檻の中の生活に絶えられなくなった時、Jeepにキャンプ道具を満載して本来あるべき自然の生活に飛び込んで行くための手段が、ソロキャンプなのでしょう。
皆さんはいかがでしょう?
では、また。
秋も深まる9月後半に、降ったりやんだりの雨のなか、岩手の海岸沿いの野営場で藪蚊と戦い、完ソロを楽しみながら原稿を書いています。
今回はキャンプ、そしてソロキャンプの魅力と言ったものを掘り下げてみましょう。
もう10年以上前の事でしょうか?
とある趣味仲間から、
「何でキャンプなんてやるんだ。
いったいどこが面白いんだ?」
そう問いかけられた事があります。
もちろん彼に悪気があった訳ではなく、年に何回か他の仲間たちとアウトドアを楽しんでいる事が理解できないのでした。
んー・・・?
意外と答えずらい質問ですよね。
自分的には好きなことを追求することで、精神的な充足感を得ることが趣味だと認識しているのですが、何故キャンプと言われると、余りにっ直球過ぎて返事に困った記憶があります。
皆さんはどうでしょう、何でキャンプに行くのですか?
おそらく、一口では中々言い表せないのではないですか?
自分は子供時代の経験が、大きく関わっているようです。
父の趣味が、渓流釣り、狩猟、山菜採り等の山歩きだったので、一年中父にくっついては、山歩きをしていた時代があります。
ただ
銃は自分の性格と相性がバッチリだったようで、物心がついてからもう50年近く趣味としてきました。
一方釣りはと言うと、からっきしダメで全く興味がわかず、間違って何かが釣れても全然面白いとは感じませんでした。
んじゃあ銃はどうなのだ。と言われるとこれもまた中途半端で、結局いまに至るまで銃砲の免許は取りませんでした。
自分がやりたいのは、プリンキングと呼ばれる、原っぱに物を並べて好きなように撃つ遊びや、ハンドがンやアサルトライフルを使ったスピード競技などを楽しみたいのであって、野山の獣を一方的に撃つような真似に興味を覚えなかったのです。
あとは競技射撃しかお堅いこの日本で銃を撃つ趣味は許されておらず、クレー射撃と呼ばれる競技射撃しかできません。
これはクレー射撃場で射場に射出される、クレーと呼ばれる10センチ程の皿を撃ち落とす競技で、オリンピックなどにも採用されている世界的にもメジャーな競技射撃です。
これも自分には合いません。
最初は面白いのでしょうが、クレーを撃つ以外の事は一切許されず、型にハマりきった競技射撃など、いずれ飽きてしまうのは目に見えていたのです。
結局、狩猟、渓流釣り、山菜採りなどに共通しているアウトドアの世界だけが自分に一番しっくりくる趣味として、飽きることなく途切れ途切れではありましたが、未だに続いているわけです。
では皆さんにうかがいます。
アウトドアの様々な趣味、そしてスポーツの中から、なぜ敢えてキャンプを選んだか?
更にはソロキャンプの楽しみなど、ご意見があれば是非書き込んでください。
「キャンプのどこが楽しいんだ?」
これについての皆様のご意見も聞きたいものです。
自分の考え的には、ハッキリした答えは出ていません。
但し、自分が考えるソロキャンプの理想と言うのがありまして、
第一に海でも山でも景色が最高なこと。
自分がキャンプ場を選ぶ基準のほとんどがこれに尽きます。
後はトイレと炊事場だけあれば何もいりません。
9月の海です。
キャンプの帰りに海を見たくなって寄り道しました。
二つ目は、誰も居ないことです。
いわゆる完ソロと言うやつで、穏やかな天候の中、ランタンの明かりの下で珈琲を飲みながら好きな本を読んでみたり、バーボンを一杯やりながら満天の星空を眺める時間に、何とも言えない魅力を感じます。
静かなキャンプ場と美しい朝焼けはキャンプに欠かせない物の一つです。
三つ目は、山で食べるご飯の美味しい事でしょうか。
チマチマした不便な道具類を使って、火力の安定しない野外での料理は中々に難しいものです。
例えばご飯1つ炊くにもそれなりのテクニックが必要で、どのタイミングで炭火の上に飯盒を乗せるか見極めが肝心です。
どれだけ高温を維持できるかがご飯の味を大きく左右します。
最高の環境下でできたご飯は、もう匂いが違うのです。
コンロから下ろし、出来上がりから大体5分~8分蒸します。
これもその時のコンディションで変わります。
そして恐る恐る蓋を開けたとき、お米が立っている状態を確認できれば90%以上の成功率であり、美味いご飯であることは間違いありません。
口に入れた瞬間幸せを感じる事でしょう。
いつの年だったか忘れてしまいましたが、秋の終わりころだった事は覚えています。
山のキャンプ場で肌寒い中、オデンを煮込んでいる最中です。
最後は自然の空気です。
奥深い野営場で感じる少し湿ったような独特な空気。
明け方の朝靄のなか、思いっきり深呼吸した時の空気の香り。
フィトンチッドに包まれて、眠気の残った身体がゆっくりと活動を開始します。
目覚まし時計に叩き起こされる日常がいかに不自然な物なのか、実感出来るひとときでもあります。
日が暮れれば周囲は闇に沈み、月と星空以外の明かりは自分のサイトだけになります。
虫達の演奏会に耳を傾け、清々しい夜風に当たりながらゆっくり酒を口に運び本を読んでいると、自然とアクビが出てきます。
そろそろ眠る時間でしょう。
サイト周辺を軽く片付け、柔らかなベットに身を横たえると、自然に体から力が抜け、意識が沈んでいきます。
おそらくは、これが「人」という動物の、自然なライフサイクルなのでしょう。
とある山の中腹にある野営場での二泊三日のキャンプです。
天候不順なため、タープのみ設営して車中泊の予定でしたが、風が気持ちいいので、そのままタープの下で眠ることにしました。
たまにこんなタープ泊をするのですが、虫の少ない時期場所を選ばないと、顔が虫刺されでとんでもない事になるので余りお勧めはしません。
気分的には最高なんですが・・・
以前、大ファンだったとある漫画家の作品が3Dアニメ化されたとき、その物語の重要な位置を占めるキャラクターが呟いた言葉が、今でも耳に残っています。
「人とは、自分から進んで檻の中に入りたがる、変わった生き物だな」
高度に集積化した社会に生きている現代人とは、檻の中の動物なのかもしれませんね。
そんな檻の中の生活に絶えられなくなった時、Jeepにキャンプ道具を満載して本来あるべき自然の生活に飛び込んで行くための手段が、ソロキャンプなのでしょう。
皆さんはいかがでしょう?
では、また。
2022年09月27日
小物の使い方、あると便利な小物達
こんにちは、MASADA556です。
今回は、自分がキャンプで良く使っている道具類、余り使うことはないけれど常に持ち歩いている道具類の紹介です。
以前も同じようなブログを書きましたが、今回はその使用目的と取り扱いについてまで、少し突っ込んだお話をしてみようかと考えております。
書き出しは、秋田県中里町白神山中の某野営場にて原稿を書いております。
このキャンプ場は人里に出るまで車で40分、スマホが繋がるまで30分は走ろうかという山奥の渓流横の空き地にポツンと存在しています。
キャンプ場に至る道も白神山地の奥地に向かって行く道で、反対側からは基本的にここには誰も入って来ないのです。
設備もトイレに炊事場と東屋が1つあるだけで、電線が通っていないので照明設備すらありません。
したがって日が落ちれば周囲は真の闇に包まれます。
トイレはふ釣り合いなほど立派なバイオトイレなので、これは有り難いですね。
但し夜は真っ暗ですよ。
炊事場も残念ながら水が出ません。(以前は出ていたような気がするのですが・・・)
まあ、目の前に綺麗な渓流が流れているので、その水を使え。
と言う分かりやすい話なのかも知れませんね。
東屋は8畳程の立派なもので、そこにテーブルを広げてブログを書いている訳です。
山にはそれなりに馴れているつもりですが、これ程ひとけの無い野営場を自分は他に知りません。

熊に注意という看板は当たり前に見かけますが、遭難注意という看板は初めてです。
休日の日中はソコソコ、釣り人や何か山に用がある車がポツポツ通るのですが、日が落ちれば無人地帯と化します。
ハイシーズンにはそれなりにキャンパー達が集まっているようですが、天候のせいかタイミングのせいなのか、自分は一度も見かけたことはありません。
おまけにこの前の豪雨で、青森県側からのルートが落石と川の増水で通行止め状態となっております。

たまたまスマホのナビ機能をいれっぱなしにして走っていたところ、どうしても弘前側から入るルートを拒否してくるので、変だなと感じていたのです。
ですが、自分にとって、ドライブ=キャンプは同義語なので、片道3時間半のドライブとなったわけです。
ところが近づくにつれ、「崖崩れ、注意」「豪雨時通行止め」
等の余り芳しくない注意看板が目立つようになり、とうとう「25キロ先、完全通行止め」
なんて看板までが出始め、いきなりとどめを刺しにきました。
ナビが示す距離は26キロ。
何とも微妙なところです。
今までの経験上、Jeepにとっては通行止めではなかった。
と言う道が何回かあったので、本当に通れないのか?
確かめてみたくなるおかしな癖がついているので、看板はガン無視です。
通れなければ戻れば良いだけの事。
いつもの事です。

ヤバい注意看板がいたるところで目につきます。
午後4時半、無事にキャンプ場に到着です。
今回は良い方に運が傾いたようです。
しかし、あちこちに豪雨災害の爪痕が残っており、明日大雨に見舞われれば帰れなくなる可能性もあります。
こうなってくると、キャンプなのか災害訓練なのか訳が分からなくなってきます。

白神山地の奥につながるルートです。
何ヶ所かでがけ崩れの跡を見かけました。
午後10時を過ぎました。
気温17℃、ポツポツと小雨が時おり降ってくる以外は、辺りは静まり返っており、真後ろの渓流の流れる音と、秋の虫達の奏でる演奏会だけが自分を包んでいます。
今年のキャンプシーズンも後半戦に入りましたね。
このキャンプ場に心当たりのある方は一度いらしてみてください。
ソロキャンプ、中上級者向けの、落ち着いた静かな野営場です。
但し、対熊戦装備と、ランタンやフラッシュライトはしっかりした物を準備してください。
自分はキャンプ中も熊鈴とペッパースプレーは、腰から離しませんでした。
ここ何年か、本当に熊を見かける事が多くなりました。
今日も来る途中、迷ケ平頂上の牧場ど真ん中で見かけました。
それも真っ昼間、牧場の中を突っ切るルートで乗用車や大型車が頻繁に走っている道路沿いです。
一般的に考えて、臆病な熊は日中に牧場のような原っぱなどに出ては来ません。
更には、その辺りはあの凄惨な獣害事件のあった十和利山のすぐそばです。
現在でも、その時かかわった熊全てを処分出来ているとは、けして言えないのです。
背筋が寒くなるような感覚を覚えるのは、自分だけでしょうか?
これから秋の行楽シーズンに入っていきます。
山やキャンプ場を訪れる方達は十分な注意と装備、そして現場の熊出没情報をけして軽んじないことです。
全く根拠のない、「自分は大丈夫、問題ない」
このような軽挙な考えでの行動は、サメがウヨウヨと泳いでいる海に入っていくような愚かな行為だと認識すべきです。
さて本題に入りましょう。
まずはいつも持ち歩いている12品目を挙げてみました。
1、ターボライター
突き詰めれば火がつけばどんなライターでもいいだろ?
そんな身も蓋もない話になってしまう訳ですが、少しばかり考えてみましょう。
キャンプ場で何かに火を着ける時は、着火物を下に置いた状態での使用が殆どではないですか?
普通の100円ライターやジッポライターに代表されるようなオイルライターだと、下に向ければ指を焼くばかり、ちょっと風があれば役には立たずでウンザリしてきます。
その点ターボライター、更に首長のライターであれば、他にもランタンに火をいれる時など様々なシーンで活躍してくれます。
2、ファイヤースターター
以前とあるキャンプ系の掲示板を見ていたら、「何でワザワザファイヤースターターなんてメンドウなモノで火を起こすの?
ライターでいいんじゃね」
こんな投稿がありまして、苦笑いしたことがあります。
確かに投稿者様の書き込みは間違っていません。
しかし・・・ファイヤースターターで火を起こす。
これは一種の儀式のようなモノで、映画とポップコーン、トンカツにカラシ、ビールに枝豆とでも言いますか?
何とも切っても切れない問題なのです。
キャンプを知らない方々には理解しがたい話ではありますが、そう言うモノであります。
本気で入れ込めば入れ込む程、遊びは面白い。
そのように理解して頂きたい。
3、手斧、小鉈、ナイフ
焚き火を楽しむキャンパーには必須でしょう。
ワンピース構造の頑丈なナイフは、薪を割るだけではなく工夫次第でいくらでも役立ってくれます。
特にクラフトキャンプを目指している方々には当たり前の装備ですね。
4、水筒
自分はサーモスの水筒を使っていますが、これが実に多彩に役立ちます。
暑い季節には氷だけを入れておき、お茶からビールまで、飲みたくなった様々な飲み物を注いで飲み干すわけです。
寒い季節には販売機で仕入れたホットドリンクを継ぎ足ししながら飲んでいれば、常に温かい珈琲が手元にあるわけです。
ホット、コードどちらにも使える万能のギアです。
5、銀マット
100円ショップで扱っているような、薄く大きめのマットが一番使いやすいですね。
様々な物に応用がききます。
当然断熱性を備えた敷物から始まって、車中泊時には窓の断熱とカーテンに、テントのグラウンドシートに、暑い時期にはテントの天井をカバーしたり、テープで張り合わせれば簡易的なタープに、寒い時期には寝袋の中に入れれば優れた断熱性を発揮してくれます。
6、除菌アルコール
本来の目的以外にも、水が乏しい時に食器類を拭き取ったり、傷口の簡易消毒に、ベトついた顔、手足の拭き取り、厄介な羽虫にはちょっとした殺虫剤替わりに、幾らでも応用がききます。
7、長座布団
キャンプのレギュラーメンバーですね。
Jeepに積みっぱなしです。
最近は170センチ位の大判の物もありますので、そちらはマット替わりに使っています。
小型の物は椅子のマット替わりにも使え、腰の調子が悪いときは車のシートに敷いたりしてます。
安価で幾らでも買い換えがききますので、惜しみ無く使えます。
8、パラシュートコード
パラコードも国外から手頃な価格で良いものが入ってくるようになりました。
自分は50メーター単位で買い込んで使っています。
殆どがタープ、テントのガイロープに使っているのですが、物がロープですから、思い付く限りあらゆる応用が可能です。
但し、コードの結びかたをそれなりに習熟しなければ使い物にはならないのでしっかり覚えてください。
自分は2種類の結びかたしか知りませんが、困ったことはありません。
基本、絞り結びと止め結びの応用を覚えれば大丈夫です。
9、浄水器
一泊か二泊のキャンプに何を大袈裟な。
なんて言われるかも知れません。
しかし自分の経験上から言わせていただけるのなら、非常に便利な道具です。
最近キャンプ場で目につくようになったのは「この水は飲めません」
又は「この水は飲用に適していません」
このような看板が炊事場に張り付けられていることです。
皆さんもどこかで目にした事がありませんか?
ご家族で休みを合わせ、長時間のロングドライブの末にようやく到着した山奥の静かな野営場。
殆ど人気がなく絶好の場所にサイトを設営、
さあ!、いよいよ晩御飯の準備だ!!
炊事場に食材を持ち込んだ奥さまと子供達の悲鳴が・・・
パパ、この水飲めないよ、どうするの!!
正に絶望的な状況です。
飲料水の準備がなければ、キャンプ自体を諦めなくてはならないほどの緊急事態と言えます。
飲めない原因としては、施設の老朽化や、何らかの理由で保健所の水質検査を受けていない。あるいは検査を通らなかった。
という事でしょう。
特に沢の水を利用している野営場では、大雨のあと炊事場の水に泥が混入して濁ったりすることはよくあることです。
そのようなあまり衛生的ではない生水を、殺菌環境に慣れきった日本人が口にするには少しばかりリスクが大きいと感じます。
皆さんも検討してはいかがでしょうか?
10、ビーチベット
以前自分は、就寝用のコッドとタープの下で寝転がるための折り畳み式のビーチベットを積んで、あちこちのキャンプ場に通っていたわけですが、ドライブ中に疲れてくれば適当なパーキングの端にJeepを止めてビーチベットを引っ張り出して仮眠したり、気候が穏やかな時はテントに入らず、タープ下のビーチベットで眠ったりもしていました。
そのうちコッドを二つも積んで移動することにバカバカしさを感じた自分は、ビーチベット1つに纏めることにしました。
ビーチベットってどこが違うのよ?
当然そのように考えますよね。
自分の使っているベットはいつ頃買い求めたのか思い出せない程昔の物です。
確か千円か2千円程度の安物だったのですが、余りの便利さに驚いた記憶があります。
現在主流のコットは組立式が殆どで小型軽量さがメインのものです。
但し組み立てにはこれといった統一性がなく、結構メンドウだったりもします。
また組み立てにかなりの力が必要な物もあるようで、女性では組み立てできないようなコッドもあるようです。
ところが、ビーチベットというのは折り畳みベットと言われるもので、小学生でも簡単にセットできます。
畳んでいる両足を左右に広げ、3分割の本体の頭側と足側をこれも左右に展開するだけで完成です。
実に10秒もかかりません。
さらには両端側の角度も自由に動かせるので非常に快適です。
もっとも、少しばかり狭いとか、足が2ヶ所しか無いので多少安定性に欠けるとかの問題もありますが、最近は寝心地の良い物も出ているので、選ぶとなれば、自分的には今後も折り畳みベッド1択ですね。
11、ツールナイフ
スイス製、ビクトリノックスとウェンガーのナイフが業界の2代巨頭ですね。
自分が初めて手に入れたのは20代の頃で、24得ナイフと呼ばれる物でした。
真っ赤なボディにスイスの国旗、小さいながらも精密に作られたその多機能なツールナイフは男のロマンそのものです。
正にポケットの中の工具箱で現場で、必要な工具は殆ど付いていると言う優れものでした。
今でこそ競合他社から様々なツールナイフが出てはいますが、自分はやはりビクトリノックス製のモデルをお奨めします。
物凄い種類のモデルが製品化されているので、必ず自分の目的に合ったモデルが見つかるはずです。
また信頼性においても、他の廉価版のナイフとは比べ物になりません。

12、ファーストエイドキット
実は前回のキャンプの時に火起こしの焚き付けにと、松の枝祓いをしている時、左手人差し指と中指をざっくりとやってしまいました。
こんなに手酷く切ったのは久しぶりで、特に人差し指は幅深さ共に1センチ程もカットしてしまいました。さらには縦ではなく関節方向に横向きにスライスしてしまい、一気に大量の出血に見舞われました。
すぐさま消毒しガーゼを当てて止血したのですが、指を動かすたびに出血するのでどうにもならず、液体絆創膏を使って止血するまでに1時間程も要しました。
原因は言うまでもなく馴れと気の弛みです。
通常枝を祓う時は枝の根本側を持ってその下方向に向かって切り落としていきます。
それを何を考えていたのか枝の真ん中辺りを持って上から祓っていったのです。
当然グローブ何て物も履いていません。
ちょうど手の上の枝を祓おうと力をいれた瞬間あっけなく枝が落ち、勢い余った刃先が指を掠め・・・
分厚いブレードを持つ、頑強なアタックナイフだったので、あと何センチか深ければ人差し指が落ちていたたかも知れません。
この程度で済んだのは正に僥倖でした。
ソロキャンプでとにかく気を付けたいのはこのような怪我です。
状況によっては辺りに誰もおらず、スマホの電波も届かない時もあるわけですから、己の行動に十分な配慮が必要です。
と言う訳で、最低限のファーストエイドキットは常に持ち歩いてください。
自然の物は全て雑菌に汚染されているので、最低限消毒と傷口の保護をしないと、何らかの感染症にかかるリスクが非常に高くなります。
当たり前ですが、手から血を吹き出したままでは、設営も撤収もできません。
さて、ここからは道具の使い方のコツと言ったモノをお話していきます。
何にせよ道具と言うものはただ持っているだけではその役割を充分に果たせません。
使い方に習熟が必要です。
1、ハンマーの使い方、ペグの立てかた
ペグ打ち用のハンマーは必須です。
たまに、その辺りに落ちている石で打てば良い。なんて記事を見かけたりしますが、自分の経験から言うと、キャンプ場にそんな石が都合良く落ちている事などありません。
またあったにしろ、そんな不適当な代物でペグを叩いたりしたら、テントを壊したり指を潰す羽目にもなりかねません。
良くキャンプ場で見かけるのは、小刻みにペグにハンマーを打ち込んでいる姿です。
この打ち方だとペグが入って行かず、はっきり言って疲れます。
まず、左手に持ったペグの打ち込み角度を決め、そのまま手で押し込んで見てください。
ある程度刺さったら軽く打ち込み、手を離します。
ここからがコツです。
何時もより少しばかり大きく振り上げ、落とすときには力まずハンマーの重さをそのままペグの頭に打ち下ろすような感じでやってみてください。
要領に馴れてくれば、少しばかり固い地面にも容易に打ち込むことができます。
とにかく、ハンマーを振るときは力まない事です。
2、ファイヤースターターの使い方
自分はオモチャ感覚で当たり前に使っていますが、他のキャンパーさんが使っているのはまだ、見たことがありません。
もし興味があるなら買い求めてみてはいかがでしょう。
購入するのであれば大きいモノの方が使いやすいです。

100均で売っているようなシロモノでは、達人的なスキルが必要です。
着火の要領はこうです。
まず適当な火口(ほくち、最初に火を起こす着火材)を準備します。
自分的には良く乾燥したティッシュペーパーが簡単で良いです。
これを細かく千切り、軽く固めてテーブルの端に置きます。
この上にファイヤースターターを乗せ、ストライカーで10回ばかり軽く削ります。
白いティッシュの上に黒い粉が見えてくるでしょう。
そうしたら先端ではなく、ストライカーを持っている指の辺りでスターターを削り落とします。
良い具合に火花が散れば下の粉に着火して大きな火花が飛び、簡単に火が着きます。
勘違いしないでほしいのは、飛ばした火花で火をつけるのではなく、削った粉に火をつけるのです。
粉が燃焼する過程で1000度以上の熱を発し、着火物に火をつけると言う理屈です。
これを間違うと、火がつくまで大汗をかくことになります。
またちょっと風があったり、火口が湿っていたりすると着火に手こずる事になります。
たかが火起こしですが、現代人にとっては意外と難しいモノです。
楽しんでください。
3、刃物の使い方
21世紀の現代の日本人にとって、包丁以外の刃物など、もっとも縁遠いモノの1つではないでしょうか?
さらにはスーパーコンビニなどで、加工済みの食材が当たり前のように手に入る時代となってきました。
こうなると、いずれ包丁まな板も台所から姿を消していくのかも知れません・・・?
IHクッキングヒーターの普及で、徐々にガスコンロが駆逐されつつあります。
つまりは火ですね。
何かうすら寒いものを感じます。
このまま行けば、いずれスイッチを押す以外には何も出来ない人類というものが、誕生するのではないでしょうか。
話を戻しましょう。
まずは自分が扱いきれる必要最小限の物を手にいれましょう。
そしてそれを何のために必要とするかで、選択枝が大きく変わります。
バトニング、調理器具の1つ、野外の雑務に使うため・・・・
しっかりした目的意識を持ってから購入すべきでしょう。
自分も何だかんだで10本以上持っています。
まあ半分は趣味のようなものなのですが、1つで全ての作業ををこなせるような万能のナイフというモノが未だ存在しない事も原因の1つです。

上のナイフはフルタングと呼ばれる一本の鋼の板から削り出されたナイフで頑丈な作りになっています。
下のナイフはスイッチナイフと呼ばれるモノでブレードが折りたためることが大きな特徴です。
どちらも野外の雑務用に手にいれたもので、上のナイフはもう10年以上もアウトドアのお供です。


試しに枝から火口を削っている画像です。
固いものを削るような時、又はリンゴの皮を剥く時は、先端ではなくグリップに近い部分で削ると力が入りやすく、細かい作業が楽にできます。
ナイフは包丁と逆で引きながらモノを切る刃物です。
したがって何かを切るとき、例えば撃ち倒した獲物を解体するときは刃先から差し込ようにして手前に切っていきます。
つまり刃先の鈍いナイフは、例え他の部分が鋭くとも、切れないナイフと感じてしまう訳です。
ポイントと呼ばれる先端部分はナイフの命であり、乱暴に扱って刃先を欠いてしまえば、そのナイフは使い物にならなくなります。
興味のある方は調べてみてはいかがでしょう。
非常に奥深く難しくもある世界です。
4、洗い物の基本
この話であれば奥様方の独壇場ですが、それは設備の整った一般家庭の台所であればと言う条件付きです。
アウトドアでの調理、洗浄は少しばかり勝手が違う事になります。
まず調理であればせせこましい道具であってもそれなりの経験則があれば何とかなります。
特にバーベキューなんかは切る程度の調理しかしないので、味の良し悪し以外はさして問題とはなりません。
そしてその後です。
バーベキューの後、こびりついた食材とギトギトの油にまみれた食器類と鉄板、焼き網をどのように処理するかです。
オイルに漬け込んだような鉄板をいきなり炊事場に持ち込んで、力任せにタワシでガシガシ・・・・と言うのは最悪です。
皆さんもどこかのキャンプ場で見かけたことがありませんか?
ドロドロの油と食材のカスで排水溝が詰まり、そこに汚水が溜まって下水のようになった炊事場を。
ハッキリ言ってキャンプ場の公害の1つです。
こんなことをされては、この後のキャンプができなくなります。
こんなことにならないように、ちゃんと段取りがあります。
まずは、大量の油をキッチンペーパーで拭き取る事から始めましょう。
他の食器類も同じです。
これをやるだけで作業の手間が1/3も無くなります。
続いてスクレーパー等を使って鉄板にこびりついた食材をこ削ぎ落とします。
要は残渣で排水口が詰まるのを防ぐ目的です。
これでまた1/3作業が楽になります。
ここまで下準備をしてから、初めて洗い物を炊事場に持って行くのです。
その時事前に沸かしておいたお湯も持って行きましょう。
そして洗い物にお湯をかけて軽く流します。
これだけで驚くほど油が落ちるはずです。
後は洗い流していくだけですが、必ず汚れの少ない物から洗っていくことです。
鉄板などの大物から手を付けたい気持ちは分かりますが、そんなことをしてしまうとキツい油がスポンジに染み付いてしまうので他の洗い物がベトベトになってしまいます。
そんな時でもお湯を上手く使えばキレイに落ちるので、熱いお湯を多めに用意しておけば洗浄は楽に進められます。
後は30分も日に当てておけば問題なく梱包できるはずです。
試してみてください。
5、ペグを無くさないようにするには。
キャンプでの遺失物のトップは今も昔もペグがトップなのではないでしょうか?
自分もたまにサイトで見つけます。
殆んどが付属品に付いてくるような細いピンペグです。
おそらくはまだ経験浅い方達が撤収の際に忘れて行った物だと思います。
キャンプの時に一番疲れを感じているのは最後の撤収の時でしょう。
楽しかった一時が終わり、嫌でも現実の世界に戻って行かなくてはなりません。
その現実世界への第一歩がサイトの撤収です。
それも連泊の疲れが重く残っていたり、サイトの引き渡し時間が迫っていたり、雨風の吹く悪天候時の撤収などサイトの設営よりも撤収時の方が大変だったりします。
そんな時につい忘れ物をしてしまうのは良くあることです。
そしてそんな時に最も忘れてしまうのがペグと言う事になるのでしょう。
では無くさないようにするコツをお話しましょう。

設営の時に一本、撤収の時にもう一本です。
どちらも付属品のペグのようです。
まずは使っているペグの本数を数えておくのが基本です。
テントに何本タープに何本と使用数を覚えておけば撤収時にペグを洗いながらカウントすれば良い訳です。
まあこの程度の事はどなたでも理解している話です。
それでもキャンプ場に寄付していく方々が絶えないのは次の理由があるからでしょう。
一番多いのは地面に刺したまま忘れていく事です。
これはテントやタープのガイロープに使っていたペグでしょう。
これを防ぐ方法は1つです。
ペグを抜き取るまで絶対にガイロープは外さないことです。
ペグを抜いてからロープを外し、まとめて結わえる癖をつけましょう。
そうすればロープとペグの本数が合わない時はすぐに気がつくかと思います。
次は、いかにも置き忘れて行きました。と言う感じでサイトに落ちているペグです。
これは抜いたペグを一ヶ所にまとめて置かない事が原因でしょう。
抜いたペグをその場に置いてタープ等を畳んだりしていくと、このような置き忘れに繋がると思います。
ペグを抜くときは抜く作業だけに専念し、他の作業を挟まない事です。
そして、ペグは必ず一ヶ所に纏めて置きましょう。
なぜかペグという無くしやすい道具は、目立たないよう、黒に塗装されているので、少し目を離しただけで見失ってしまいます。
また抜きながら数えていけばまず無くすことはないでしょう。
自分が目安にしているのは、抜いた数が偶数になることを目算しながら作業することです。
自分が今まで作ったキャンプサイトで、ペグの使用本数が奇数になったことはありません。
少しばかり長くなってしまいました。
ベテランの方々には基本的なお話ばかりでしたが、キャンプを初めてまだ日の浅い方々に、何かのお役にたてれば幸いです。
しっかし、今年は雨の年です。
いまブログを書いている某野営場も午前中は霧、午後は予報通り雨になりました。
今日は終日雨のようです。
9月最後の3連休に有給をくっつけて5連休という暴挙にでています。
生憎の滑り出しですが・・・
では、また。
今回は、自分がキャンプで良く使っている道具類、余り使うことはないけれど常に持ち歩いている道具類の紹介です。
以前も同じようなブログを書きましたが、今回はその使用目的と取り扱いについてまで、少し突っ込んだお話をしてみようかと考えております。
書き出しは、秋田県中里町白神山中の某野営場にて原稿を書いております。
このキャンプ場は人里に出るまで車で40分、スマホが繋がるまで30分は走ろうかという山奥の渓流横の空き地にポツンと存在しています。
キャンプ場に至る道も白神山地の奥地に向かって行く道で、反対側からは基本的にここには誰も入って来ないのです。
設備もトイレに炊事場と東屋が1つあるだけで、電線が通っていないので照明設備すらありません。
したがって日が落ちれば周囲は真の闇に包まれます。
トイレはふ釣り合いなほど立派なバイオトイレなので、これは有り難いですね。
但し夜は真っ暗ですよ。
炊事場も残念ながら水が出ません。(以前は出ていたような気がするのですが・・・)
まあ、目の前に綺麗な渓流が流れているので、その水を使え。
と言う分かりやすい話なのかも知れませんね。
東屋は8畳程の立派なもので、そこにテーブルを広げてブログを書いている訳です。
山にはそれなりに馴れているつもりですが、これ程ひとけの無い野営場を自分は他に知りません。
熊に注意という看板は当たり前に見かけますが、遭難注意という看板は初めてです。
休日の日中はソコソコ、釣り人や何か山に用がある車がポツポツ通るのですが、日が落ちれば無人地帯と化します。
ハイシーズンにはそれなりにキャンパー達が集まっているようですが、天候のせいかタイミングのせいなのか、自分は一度も見かけたことはありません。
おまけにこの前の豪雨で、青森県側からのルートが落石と川の増水で通行止め状態となっております。
たまたまスマホのナビ機能をいれっぱなしにして走っていたところ、どうしても弘前側から入るルートを拒否してくるので、変だなと感じていたのです。
ですが、自分にとって、ドライブ=キャンプは同義語なので、片道3時間半のドライブとなったわけです。
ところが近づくにつれ、「崖崩れ、注意」「豪雨時通行止め」
等の余り芳しくない注意看板が目立つようになり、とうとう「25キロ先、完全通行止め」
なんて看板までが出始め、いきなりとどめを刺しにきました。
ナビが示す距離は26キロ。
何とも微妙なところです。
今までの経験上、Jeepにとっては通行止めではなかった。
と言う道が何回かあったので、本当に通れないのか?
確かめてみたくなるおかしな癖がついているので、看板はガン無視です。
通れなければ戻れば良いだけの事。
いつもの事です。
ヤバい注意看板がいたるところで目につきます。
午後4時半、無事にキャンプ場に到着です。
今回は良い方に運が傾いたようです。
しかし、あちこちに豪雨災害の爪痕が残っており、明日大雨に見舞われれば帰れなくなる可能性もあります。
こうなってくると、キャンプなのか災害訓練なのか訳が分からなくなってきます。
白神山地の奥につながるルートです。
何ヶ所かでがけ崩れの跡を見かけました。
午後10時を過ぎました。
気温17℃、ポツポツと小雨が時おり降ってくる以外は、辺りは静まり返っており、真後ろの渓流の流れる音と、秋の虫達の奏でる演奏会だけが自分を包んでいます。
今年のキャンプシーズンも後半戦に入りましたね。
このキャンプ場に心当たりのある方は一度いらしてみてください。
ソロキャンプ、中上級者向けの、落ち着いた静かな野営場です。
但し、対熊戦装備と、ランタンやフラッシュライトはしっかりした物を準備してください。
自分はキャンプ中も熊鈴とペッパースプレーは、腰から離しませんでした。
ここ何年か、本当に熊を見かける事が多くなりました。
今日も来る途中、迷ケ平頂上の牧場ど真ん中で見かけました。
それも真っ昼間、牧場の中を突っ切るルートで乗用車や大型車が頻繁に走っている道路沿いです。
一般的に考えて、臆病な熊は日中に牧場のような原っぱなどに出ては来ません。
更には、その辺りはあの凄惨な獣害事件のあった十和利山のすぐそばです。
現在でも、その時かかわった熊全てを処分出来ているとは、けして言えないのです。
背筋が寒くなるような感覚を覚えるのは、自分だけでしょうか?
これから秋の行楽シーズンに入っていきます。
山やキャンプ場を訪れる方達は十分な注意と装備、そして現場の熊出没情報をけして軽んじないことです。
全く根拠のない、「自分は大丈夫、問題ない」
このような軽挙な考えでの行動は、サメがウヨウヨと泳いでいる海に入っていくような愚かな行為だと認識すべきです。
さて本題に入りましょう。
まずはいつも持ち歩いている12品目を挙げてみました。
1、ターボライター
突き詰めれば火がつけばどんなライターでもいいだろ?
そんな身も蓋もない話になってしまう訳ですが、少しばかり考えてみましょう。
キャンプ場で何かに火を着ける時は、着火物を下に置いた状態での使用が殆どではないですか?
普通の100円ライターやジッポライターに代表されるようなオイルライターだと、下に向ければ指を焼くばかり、ちょっと風があれば役には立たずでウンザリしてきます。
その点ターボライター、更に首長のライターであれば、他にもランタンに火をいれる時など様々なシーンで活躍してくれます。
2、ファイヤースターター
以前とあるキャンプ系の掲示板を見ていたら、「何でワザワザファイヤースターターなんてメンドウなモノで火を起こすの?
ライターでいいんじゃね」
こんな投稿がありまして、苦笑いしたことがあります。
確かに投稿者様の書き込みは間違っていません。
しかし・・・ファイヤースターターで火を起こす。
これは一種の儀式のようなモノで、映画とポップコーン、トンカツにカラシ、ビールに枝豆とでも言いますか?
何とも切っても切れない問題なのです。
キャンプを知らない方々には理解しがたい話ではありますが、そう言うモノであります。
本気で入れ込めば入れ込む程、遊びは面白い。
そのように理解して頂きたい。
3、手斧、小鉈、ナイフ
焚き火を楽しむキャンパーには必須でしょう。
ワンピース構造の頑丈なナイフは、薪を割るだけではなく工夫次第でいくらでも役立ってくれます。
特にクラフトキャンプを目指している方々には当たり前の装備ですね。
4、水筒
自分はサーモスの水筒を使っていますが、これが実に多彩に役立ちます。
暑い季節には氷だけを入れておき、お茶からビールまで、飲みたくなった様々な飲み物を注いで飲み干すわけです。
寒い季節には販売機で仕入れたホットドリンクを継ぎ足ししながら飲んでいれば、常に温かい珈琲が手元にあるわけです。
ホット、コードどちらにも使える万能のギアです。
5、銀マット
100円ショップで扱っているような、薄く大きめのマットが一番使いやすいですね。
様々な物に応用がききます。
当然断熱性を備えた敷物から始まって、車中泊時には窓の断熱とカーテンに、テントのグラウンドシートに、暑い時期にはテントの天井をカバーしたり、テープで張り合わせれば簡易的なタープに、寒い時期には寝袋の中に入れれば優れた断熱性を発揮してくれます。
6、除菌アルコール
本来の目的以外にも、水が乏しい時に食器類を拭き取ったり、傷口の簡易消毒に、ベトついた顔、手足の拭き取り、厄介な羽虫にはちょっとした殺虫剤替わりに、幾らでも応用がききます。
7、長座布団
キャンプのレギュラーメンバーですね。
Jeepに積みっぱなしです。
最近は170センチ位の大判の物もありますので、そちらはマット替わりに使っています。
小型の物は椅子のマット替わりにも使え、腰の調子が悪いときは車のシートに敷いたりしてます。
安価で幾らでも買い換えがききますので、惜しみ無く使えます。
8、パラシュートコード
パラコードも国外から手頃な価格で良いものが入ってくるようになりました。
自分は50メーター単位で買い込んで使っています。
殆どがタープ、テントのガイロープに使っているのですが、物がロープですから、思い付く限りあらゆる応用が可能です。
但し、コードの結びかたをそれなりに習熟しなければ使い物にはならないのでしっかり覚えてください。
自分は2種類の結びかたしか知りませんが、困ったことはありません。
基本、絞り結びと止め結びの応用を覚えれば大丈夫です。
9、浄水器
一泊か二泊のキャンプに何を大袈裟な。
なんて言われるかも知れません。
しかし自分の経験上から言わせていただけるのなら、非常に便利な道具です。
最近キャンプ場で目につくようになったのは「この水は飲めません」
又は「この水は飲用に適していません」
このような看板が炊事場に張り付けられていることです。
皆さんもどこかで目にした事がありませんか?
ご家族で休みを合わせ、長時間のロングドライブの末にようやく到着した山奥の静かな野営場。
殆ど人気がなく絶好の場所にサイトを設営、
さあ!、いよいよ晩御飯の準備だ!!
炊事場に食材を持ち込んだ奥さまと子供達の悲鳴が・・・
パパ、この水飲めないよ、どうするの!!
正に絶望的な状況です。
飲料水の準備がなければ、キャンプ自体を諦めなくてはならないほどの緊急事態と言えます。
飲めない原因としては、施設の老朽化や、何らかの理由で保健所の水質検査を受けていない。あるいは検査を通らなかった。
という事でしょう。
特に沢の水を利用している野営場では、大雨のあと炊事場の水に泥が混入して濁ったりすることはよくあることです。
そのようなあまり衛生的ではない生水を、殺菌環境に慣れきった日本人が口にするには少しばかりリスクが大きいと感じます。
皆さんも検討してはいかがでしょうか?
10、ビーチベット
以前自分は、就寝用のコッドとタープの下で寝転がるための折り畳み式のビーチベットを積んで、あちこちのキャンプ場に通っていたわけですが、ドライブ中に疲れてくれば適当なパーキングの端にJeepを止めてビーチベットを引っ張り出して仮眠したり、気候が穏やかな時はテントに入らず、タープ下のビーチベットで眠ったりもしていました。
そのうちコッドを二つも積んで移動することにバカバカしさを感じた自分は、ビーチベット1つに纏めることにしました。
ビーチベットってどこが違うのよ?
当然そのように考えますよね。
自分の使っているベットはいつ頃買い求めたのか思い出せない程昔の物です。
確か千円か2千円程度の安物だったのですが、余りの便利さに驚いた記憶があります。
現在主流のコットは組立式が殆どで小型軽量さがメインのものです。
但し組み立てにはこれといった統一性がなく、結構メンドウだったりもします。
また組み立てにかなりの力が必要な物もあるようで、女性では組み立てできないようなコッドもあるようです。
ところが、ビーチベットというのは折り畳みベットと言われるもので、小学生でも簡単にセットできます。
畳んでいる両足を左右に広げ、3分割の本体の頭側と足側をこれも左右に展開するだけで完成です。
実に10秒もかかりません。
さらには両端側の角度も自由に動かせるので非常に快適です。
もっとも、少しばかり狭いとか、足が2ヶ所しか無いので多少安定性に欠けるとかの問題もありますが、最近は寝心地の良い物も出ているので、選ぶとなれば、自分的には今後も折り畳みベッド1択ですね。
11、ツールナイフ
スイス製、ビクトリノックスとウェンガーのナイフが業界の2代巨頭ですね。
自分が初めて手に入れたのは20代の頃で、24得ナイフと呼ばれる物でした。
真っ赤なボディにスイスの国旗、小さいながらも精密に作られたその多機能なツールナイフは男のロマンそのものです。
正にポケットの中の工具箱で現場で、必要な工具は殆ど付いていると言う優れものでした。
今でこそ競合他社から様々なツールナイフが出てはいますが、自分はやはりビクトリノックス製のモデルをお奨めします。
物凄い種類のモデルが製品化されているので、必ず自分の目的に合ったモデルが見つかるはずです。
また信頼性においても、他の廉価版のナイフとは比べ物になりません。
12、ファーストエイドキット
実は前回のキャンプの時に火起こしの焚き付けにと、松の枝祓いをしている時、左手人差し指と中指をざっくりとやってしまいました。
こんなに手酷く切ったのは久しぶりで、特に人差し指は幅深さ共に1センチ程もカットしてしまいました。さらには縦ではなく関節方向に横向きにスライスしてしまい、一気に大量の出血に見舞われました。
すぐさま消毒しガーゼを当てて止血したのですが、指を動かすたびに出血するのでどうにもならず、液体絆創膏を使って止血するまでに1時間程も要しました。
原因は言うまでもなく馴れと気の弛みです。
通常枝を祓う時は枝の根本側を持ってその下方向に向かって切り落としていきます。
それを何を考えていたのか枝の真ん中辺りを持って上から祓っていったのです。
当然グローブ何て物も履いていません。
ちょうど手の上の枝を祓おうと力をいれた瞬間あっけなく枝が落ち、勢い余った刃先が指を掠め・・・
分厚いブレードを持つ、頑強なアタックナイフだったので、あと何センチか深ければ人差し指が落ちていたたかも知れません。
この程度で済んだのは正に僥倖でした。
ソロキャンプでとにかく気を付けたいのはこのような怪我です。
状況によっては辺りに誰もおらず、スマホの電波も届かない時もあるわけですから、己の行動に十分な配慮が必要です。
と言う訳で、最低限のファーストエイドキットは常に持ち歩いてください。
自然の物は全て雑菌に汚染されているので、最低限消毒と傷口の保護をしないと、何らかの感染症にかかるリスクが非常に高くなります。
当たり前ですが、手から血を吹き出したままでは、設営も撤収もできません。
さて、ここからは道具の使い方のコツと言ったモノをお話していきます。
何にせよ道具と言うものはただ持っているだけではその役割を充分に果たせません。
使い方に習熟が必要です。
1、ハンマーの使い方、ペグの立てかた
ペグ打ち用のハンマーは必須です。
たまに、その辺りに落ちている石で打てば良い。なんて記事を見かけたりしますが、自分の経験から言うと、キャンプ場にそんな石が都合良く落ちている事などありません。
またあったにしろ、そんな不適当な代物でペグを叩いたりしたら、テントを壊したり指を潰す羽目にもなりかねません。
良くキャンプ場で見かけるのは、小刻みにペグにハンマーを打ち込んでいる姿です。
この打ち方だとペグが入って行かず、はっきり言って疲れます。
まず、左手に持ったペグの打ち込み角度を決め、そのまま手で押し込んで見てください。
ある程度刺さったら軽く打ち込み、手を離します。
ここからがコツです。
何時もより少しばかり大きく振り上げ、落とすときには力まずハンマーの重さをそのままペグの頭に打ち下ろすような感じでやってみてください。
要領に馴れてくれば、少しばかり固い地面にも容易に打ち込むことができます。
とにかく、ハンマーを振るときは力まない事です。
2、ファイヤースターターの使い方
自分はオモチャ感覚で当たり前に使っていますが、他のキャンパーさんが使っているのはまだ、見たことがありません。
もし興味があるなら買い求めてみてはいかがでしょう。
購入するのであれば大きいモノの方が使いやすいです。
100均で売っているようなシロモノでは、達人的なスキルが必要です。
着火の要領はこうです。
まず適当な火口(ほくち、最初に火を起こす着火材)を準備します。
自分的には良く乾燥したティッシュペーパーが簡単で良いです。
これを細かく千切り、軽く固めてテーブルの端に置きます。
この上にファイヤースターターを乗せ、ストライカーで10回ばかり軽く削ります。
白いティッシュの上に黒い粉が見えてくるでしょう。
そうしたら先端ではなく、ストライカーを持っている指の辺りでスターターを削り落とします。
良い具合に火花が散れば下の粉に着火して大きな火花が飛び、簡単に火が着きます。
勘違いしないでほしいのは、飛ばした火花で火をつけるのではなく、削った粉に火をつけるのです。
粉が燃焼する過程で1000度以上の熱を発し、着火物に火をつけると言う理屈です。
これを間違うと、火がつくまで大汗をかくことになります。
またちょっと風があったり、火口が湿っていたりすると着火に手こずる事になります。
たかが火起こしですが、現代人にとっては意外と難しいモノです。
楽しんでください。
3、刃物の使い方
21世紀の現代の日本人にとって、包丁以外の刃物など、もっとも縁遠いモノの1つではないでしょうか?
さらにはスーパーコンビニなどで、加工済みの食材が当たり前のように手に入る時代となってきました。
こうなると、いずれ包丁まな板も台所から姿を消していくのかも知れません・・・?
IHクッキングヒーターの普及で、徐々にガスコンロが駆逐されつつあります。
つまりは火ですね。
何かうすら寒いものを感じます。
このまま行けば、いずれスイッチを押す以外には何も出来ない人類というものが、誕生するのではないでしょうか。
話を戻しましょう。
まずは自分が扱いきれる必要最小限の物を手にいれましょう。
そしてそれを何のために必要とするかで、選択枝が大きく変わります。
バトニング、調理器具の1つ、野外の雑務に使うため・・・・
しっかりした目的意識を持ってから購入すべきでしょう。
自分も何だかんだで10本以上持っています。
まあ半分は趣味のようなものなのですが、1つで全ての作業ををこなせるような万能のナイフというモノが未だ存在しない事も原因の1つです。
上のナイフはフルタングと呼ばれる一本の鋼の板から削り出されたナイフで頑丈な作りになっています。
下のナイフはスイッチナイフと呼ばれるモノでブレードが折りたためることが大きな特徴です。
どちらも野外の雑務用に手にいれたもので、上のナイフはもう10年以上もアウトドアのお供です。
試しに枝から火口を削っている画像です。
固いものを削るような時、又はリンゴの皮を剥く時は、先端ではなくグリップに近い部分で削ると力が入りやすく、細かい作業が楽にできます。
ナイフは包丁と逆で引きながらモノを切る刃物です。
したがって何かを切るとき、例えば撃ち倒した獲物を解体するときは刃先から差し込ようにして手前に切っていきます。
つまり刃先の鈍いナイフは、例え他の部分が鋭くとも、切れないナイフと感じてしまう訳です。
ポイントと呼ばれる先端部分はナイフの命であり、乱暴に扱って刃先を欠いてしまえば、そのナイフは使い物にならなくなります。
興味のある方は調べてみてはいかがでしょう。
非常に奥深く難しくもある世界です。
4、洗い物の基本
この話であれば奥様方の独壇場ですが、それは設備の整った一般家庭の台所であればと言う条件付きです。
アウトドアでの調理、洗浄は少しばかり勝手が違う事になります。
まず調理であればせせこましい道具であってもそれなりの経験則があれば何とかなります。
特にバーベキューなんかは切る程度の調理しかしないので、味の良し悪し以外はさして問題とはなりません。
そしてその後です。
バーベキューの後、こびりついた食材とギトギトの油にまみれた食器類と鉄板、焼き網をどのように処理するかです。
オイルに漬け込んだような鉄板をいきなり炊事場に持ち込んで、力任せにタワシでガシガシ・・・・と言うのは最悪です。
皆さんもどこかのキャンプ場で見かけたことがありませんか?
ドロドロの油と食材のカスで排水溝が詰まり、そこに汚水が溜まって下水のようになった炊事場を。
ハッキリ言ってキャンプ場の公害の1つです。
こんなことをされては、この後のキャンプができなくなります。
こんなことにならないように、ちゃんと段取りがあります。
まずは、大量の油をキッチンペーパーで拭き取る事から始めましょう。
他の食器類も同じです。
これをやるだけで作業の手間が1/3も無くなります。
続いてスクレーパー等を使って鉄板にこびりついた食材をこ削ぎ落とします。
要は残渣で排水口が詰まるのを防ぐ目的です。
これでまた1/3作業が楽になります。
ここまで下準備をしてから、初めて洗い物を炊事場に持って行くのです。
その時事前に沸かしておいたお湯も持って行きましょう。
そして洗い物にお湯をかけて軽く流します。
これだけで驚くほど油が落ちるはずです。
後は洗い流していくだけですが、必ず汚れの少ない物から洗っていくことです。
鉄板などの大物から手を付けたい気持ちは分かりますが、そんなことをしてしまうとキツい油がスポンジに染み付いてしまうので他の洗い物がベトベトになってしまいます。
そんな時でもお湯を上手く使えばキレイに落ちるので、熱いお湯を多めに用意しておけば洗浄は楽に進められます。
後は30分も日に当てておけば問題なく梱包できるはずです。
試してみてください。
5、ペグを無くさないようにするには。
キャンプでの遺失物のトップは今も昔もペグがトップなのではないでしょうか?
自分もたまにサイトで見つけます。
殆んどが付属品に付いてくるような細いピンペグです。
おそらくはまだ経験浅い方達が撤収の際に忘れて行った物だと思います。
キャンプの時に一番疲れを感じているのは最後の撤収の時でしょう。
楽しかった一時が終わり、嫌でも現実の世界に戻って行かなくてはなりません。
その現実世界への第一歩がサイトの撤収です。
それも連泊の疲れが重く残っていたり、サイトの引き渡し時間が迫っていたり、雨風の吹く悪天候時の撤収などサイトの設営よりも撤収時の方が大変だったりします。
そんな時につい忘れ物をしてしまうのは良くあることです。
そしてそんな時に最も忘れてしまうのがペグと言う事になるのでしょう。
では無くさないようにするコツをお話しましょう。
設営の時に一本、撤収の時にもう一本です。
どちらも付属品のペグのようです。
まずは使っているペグの本数を数えておくのが基本です。
テントに何本タープに何本と使用数を覚えておけば撤収時にペグを洗いながらカウントすれば良い訳です。
まあこの程度の事はどなたでも理解している話です。
それでもキャンプ場に寄付していく方々が絶えないのは次の理由があるからでしょう。
一番多いのは地面に刺したまま忘れていく事です。
これはテントやタープのガイロープに使っていたペグでしょう。
これを防ぐ方法は1つです。
ペグを抜き取るまで絶対にガイロープは外さないことです。
ペグを抜いてからロープを外し、まとめて結わえる癖をつけましょう。
そうすればロープとペグの本数が合わない時はすぐに気がつくかと思います。
次は、いかにも置き忘れて行きました。と言う感じでサイトに落ちているペグです。
これは抜いたペグを一ヶ所にまとめて置かない事が原因でしょう。
抜いたペグをその場に置いてタープ等を畳んだりしていくと、このような置き忘れに繋がると思います。
ペグを抜くときは抜く作業だけに専念し、他の作業を挟まない事です。
そして、ペグは必ず一ヶ所に纏めて置きましょう。
なぜかペグという無くしやすい道具は、目立たないよう、黒に塗装されているので、少し目を離しただけで見失ってしまいます。
また抜きながら数えていけばまず無くすことはないでしょう。
自分が目安にしているのは、抜いた数が偶数になることを目算しながら作業することです。
自分が今まで作ったキャンプサイトで、ペグの使用本数が奇数になったことはありません。
少しばかり長くなってしまいました。
ベテランの方々には基本的なお話ばかりでしたが、キャンプを初めてまだ日の浅い方々に、何かのお役にたてれば幸いです。
しっかし、今年は雨の年です。
いまブログを書いている某野営場も午前中は霧、午後は予報通り雨になりました。
今日は終日雨のようです。
9月最後の3連休に有給をくっつけて5連休という暴挙にでています。
生憎の滑り出しですが・・・
では、また。
2022年09月14日
雨の中のソロキャンプ
みなさんこんにちわ、MASADA556です。
雨雨雨・・・・うっとしい天気ですね。
というか、一部地域では災害と化していますね。
待ちにまった七月の三連休などは、有給をくっつけて5連休なんて考えていましたが、雨予報で断念、何とか一泊くらいは出掛けたいと馴染みのキャンプ場の天気予報を何度も確認していましたが、コロコロと予報が変わるので諦めてしまいました。
夏っ!特に初夏!!は大好きな季節なのですが、どうもこの梅雨だけはうっとうしくてイライラします。
そして盆休みもキャンプどころではない天気でした。
特にここ数年休日と雨が重なる週が多いので、尚更うんざりしますね。
まあ、そんなわけで今回は雨キャンプのお話をしたいと思います。
キャンプという趣味はとにかく天気やキャンプ場のコンデションに大きく影響されることは皆さんも身に染みて感じているかと思います。
特に天候だけは人間の力ではどうにもできない事なので、ひたすら週間天気図とにらめっこしながら、行きたいキャンプ場、行けそうなキャンプ場を週始めから検討し始めることになります。
自分は馴染みのキャンプ場を青森岩手秋田の三県にまたがって10ヶ所ほどを年間で回って歩くので、少しばかりの悪天候なら回避できるのですが、7月の梅雨だけはどうにもならないのです。
更には年々降水量が激化しているので、キャンプに行って遭難してしまうような危険性もあるわけで、梅雨に限らず夏のゲリラ豪雨にも細心の注意が必要となってきました。
昨年は二回ゲリラ豪雨に直撃されました。
まるで滝のような豪雨と雷に大慌てで東屋やら待避所に逃げ込んでしまいました。
雨はまだ何とかなるのですが、それに雷がくっついてこられるとさすがに避難しないわけにも行かず、大慌てでジープに飛び乗る羽目になります。
あっ、ちなみに車に落雷しても窓を閉めきってさえいれば車体表面からタイヤを伝って地面に抜けるらしいので、車の中は有効な待避所となります。
但し、ジープの上半分は帆布で出来た幌なので、落雷を受ければシートの上で黒焦げになる可能性が大です・・・・
幌車に乗っている方々は要注意ですね。
では本題に入りましょう。
先ずはキャンプ場に移動している状態から既に問題が始まっている事が良くあります。
目的地に向かってハンドルを握っている時、目的地方向にモクモクと真っ黒で巨大な入道雲が立ち上がってきたとします。
こんな不吉な代物が目に入ったら、徒歩、自転車、オートバイで移動しているのであれば、即座にコンビニのような雨風をしのげる建物に避難するべきでしょう。

雨雲から逃げている最中です。
すかさず天気予報を調べ、どのような状況なのかを認識し、対策を考えてください。
雨雲が遠ざかっているのなら、取り合えず、心配することもありませんが、こちらに向かっている場合は、深刻な状況を考えなくてはなりません。
道路が冠水したり、河川の増水、崖崩れ、倒れた木々による道路の寸断などが考えられるからです。

物凄い豪雨の跡に倒木で通れなくなった時の1枚です。
木にワイヤーをかけて引きずり出そうと考えたのですが、倒木が電線の上にのしかかっているので断念しました。
ネット情報をフルに活用し、単なる夏のにわか雨なのか、局所的なゲリラ豪雨なのかを素早く見極めることが重要です。
もし道路の冠水や停電などの豪雨災害が発生しているのであれば速攻で引き返すべきでしょう。

濃い霧と小雨で全く前が見えなくなった時の1枚です。
狭い山道で対向車が来ても分かりません。
せっかくのキャンプなのに・・・
その気持ちは自分もわかります。
しかしモタモタと悩んでいるうちに豪雨に追い付かれてしまえば、交通インフラの寸断で引き返す事も出来なくなります。
道路が完全に水没してしまえば、非常に危険な状態となります。
道路と路肩の区別がつかなくなり、どこを走っているのか判断がつかなくなります。
限界を越えて流れ込む雨水で側溝やマンホールの蓋が外れてしまい、移動に危険を伴う状況の中に孤立してしまいかねません。
無理に走りでしても路肩に脱輪、最悪転落しかねない事態となります。
また道路を冠水している水は単なる雨水ではなく、トイレや下水から溢れ出した危険な汚水であり、傷口に触れることがあれば、何らかの感染症に罹患する可能性が非常に高くなります。
夏のゲリラ豪雨はいつどこで発生しても不思議ではありません。
常に注意を怠らないことです。
とまあ、ちょっと脅かしてしまいました。
ここまで極端ではなくとも、夏の雨キャンプは誰もがいずれ体験することです。
その時になって慌てないように、事前に何らかの対策は必要かと思います。
ネット動画などを見ると大したことがないように見受けられるかもしらません。
むしろ、ちょっとしたアドベンチャー気分にひたれるかも!?
なんて考えるかもしれませんね。
急変した天候により雨に祟られた。
これはよくある事で、設営撤収時に降られなければ特に問題はありません。
ただ、初心者が面白そうだから、程度の感覚で大雨の最中にキャンプを強行つもりなら、
止めなさい。
はっきり自分はそのように言います。
高名な動画発信者などが悪天候キャンプを発信したりしていますが、動画の内容が全てだとは考えないでください。
自分はできるだけ悪天候を避けるようなキャンプ日程を組むようにしていますが、それでも何年かに一度位は完全に天気予報に裏切られ、酷い目にあったりします。
実はこの原稿を書いている今、天気予報にまたしても騙され、豪雨の真っ只中にいます。
予報が更新される度にコロコロと変更され、どんどんと悪い方向に更新されていきました。
そして深夜、とうとうポツポツとテントに雨粒が当たりだし、30分もしないうちに豪雨に・・・・

設営当日は穏やかな良い天気だったのです。


この晩までは最高でした。
事前にペグとガイロープは確認してあったので、キャンプサイト自体には心配が無かったのですが、予報では朝8時に一度止むことになっていますが、それ以降は一日中雨になっています。
今回は二人用のコットンテントなので四人用に比べ半分の手間で撤収が可能ですが、それでもギア類の乾燥と撤収を1時間で済ませるのは不可能です。
夜が明け、少しばかり早い朝飯を取り、珈琲を飲みながら空の具合を確認してみますが、強くなったり弱くなったりを繰り返すだけで止むような感じはしません。
周囲は池と川になっていてサイトもほぼ水没状態です。

すでに周囲が水没し始めています
今回は一泊の予定でタープを張っていませんが、天幕代わりのキャノピーを用意してあったので、その下で外回りのギアを片付け、いつでも車に運び込めるようにしておきます。
足元は2cmほども水没し、テントも水溜まりの上に立っているようです。
靴下を脱ぎ、足をキレイに拭き取って今度はテント内の片付けです。
必要ない物は車に運んでいたので、30分で完了です。
後は、なるようになれだ!

半分開き直って、テントの中で寝転がっていると、いつの間にか小降りに変わりました。
良し、ここだ!
テントから飛び出すと深い霧に包まれてはいますが、雨は止んでいます。

手早くギアの収納ケースをどんどん車に運び込み、いよいよテントに手を掛けようとしたところでタイムアウト・・・
いっきに大降りとなりました。
慌てて側の炊事場に緊急待避です。
事前に準備しておいた折り畳みのビーチベッドに腰掛け、珈琲を沸かしながら天候の神様に○指を突き上げます。
こうなったら持久戦です。

叩きつけるように降ってきました。
幸いこの野営場は貸しきり状態。
炊事場の施設は独占できるので、ここである程度の作業が可能です。
襲来するアブとブヨの群れを蚊取り線香と電撃ラケットで迎撃しながらベッドに転がって静かに読書の時間です。
内心ジリジリしながら待つこと約1時間・・・滝の真下に立っているような豪雨が線を引いたようにピタっと止みました。
テントに向かってダッシュです。
西の空に灰色の雲がかかっているので、この晴れ間は一時的なものでしょう。
慌てず落ち着いてテントを解体、ペグの数を数え、ガイロープを纏めて縛り二つ折りにしたテントをビーチベッドに乗せたところで再びタイムアウト!
一気に降りだした豪雨の中、素早くポンチョを被り、残っていたグラウンドシートとポール他小物を回収し、やっと一息です。
テント、キャノピー、グランドシートの泥や張り付いた草木を洗い流し、拭き取ったら軽く乾かします。
湿度が90%を越えている状態なので、乾燥させることは出来ません。
あくまで水気を切る程度です。
40分ほどかけて拭き取りと梱包をすませ、積み込みのためジープを炊事場に横付けさせます。
少しばかり雨足の弱まった中、ドロドロの姿のままシートに飛び乗り、エンジンを始動、回転をあげないようにエンスト寸前でクラッチを慎重に繋ぎますが、リヤタイヤは空転するだけで30センチも前に進みません。
柔らかな傾斜地、泥と雑草、流れ落ちてくる雨水の組み合わせはオフロードに特化したブロックタイヤにも手強い相手です。
短気を起こしていたずらにアクセルを踏みつければ、ゴツいマッドタイヤは、まるでチェーンソーのようにいとも簡単に地面に食い込んでいきます。
すかさずジープを飛び降り、フロントホイール真ん中に飛び出ている、フリーホイールハブと呼ばれている動力伝達のための装置を、4×2から4×4に切り替えます。
これでフロントのデフとフロントタイヤが直結状態となり、最悪の路面状態の中で、悪路を自在に走り回るために作られた、ジープ本来の本当のパフォーマンスを発揮できるのです。
トランスファーを4HIに切り替えると、フロントタイヤに動力が伝わり、当たり前のように斜面を登り、真っ直ぐ走ることさえ難しい泥道を普通に走りだします。
無事炊事場に横付けできました。
この間ジープが走った距離はたかだか数十メートルですが、もしオフロードに適していない車両ならば、克服できない非常に困難な数十メートルにもなりかねないのです。
帰りはいつものように中腹にある温泉でドロまみれの身体をキレイさっぱりと洗い、泡風呂に身を沈めるとあまりの気持ち良さに疲れが抜けて行きます。
キャンプ帰りの温泉と言うのも中々に良いもので、キャンプ場とひなびた温泉地と言うものはセットになっています。
マッサージ機に座り、15分ほど仮眠し、ゆったりと降りしきる雨を眺めているとほんの1時間前の苦労が夢のようです。
いつものマ○いラーメンを食べ、のんびりと帰路につきます。
と、この当たりでYOUtubeの動画は終わりになるのでしょうが、実際はこの後も苦難が続くのです。
夕方八戸に到着。
雨が小降りだったののでキャンプ道具を降ろし、泥だらけの車内に洗車ホースを突っ込んで、泥と草木、無賃乗車の虫共を吹き飛ばします。
疲れていたので今日はここまで・・・
翌日、会社を1時間早く飛び出し、グチャグチャのテント類の乾燥作業に取りかかります。
ところが天候自体が思わしくなく、今にも降りだしそうなのです。
本当は一旦組み立ててその状態で乾かすのが最善なのですが、その判断ができません。
さらには他にもキャノピーとグランドシートも乾かさなければならないので、モタモタしているわけにはいかないのです。
結局キャノピーとグランドは庭の物干しで乾かし、テントは2階ベランダで乾かすこととしました。
ボタボタと滴るテントとシートを袋から取りだし、信じられない重さになったテントを苦労して運び上げ、ベランダ物干しになんとかぶら下げることに成功しました。

水を吸って重くなっているキャンバステントを二階まで運び、物干し竿にかけるのは、大の男でも一苦労です。
シート類は庭で2時間ほども乾かして問題ない程度に乾燥させることができました。
後はテントだけなのですが、なんと翌日から東北を災害級の豪雨が襲い、東北一帯がとんでもないことに・・・
昔から自分は天気の神様と仲が悪い訳ですが、ここまで極端なのも珍しいです。
結局テントの乾燥に3日を要しました。
もしベランダがなければ、到底乾かすことはできなかったでしょう。
今回は何とか対応が上手くいきましたが、少しばかり条件が悪ければ更に対応が困難な状況に陥ったかもしれません。
もし、一日中豪雨だったら?
もし、キャンプ場自体が災害避難区域に指定されていて、避難指示が出てしまったら?
もし、炊事場や東屋が無かったら?
もし、車がスタックして動けなくなったら?
もし、足元が滑って転倒し、怪我で動けなくなったら?
もし、帰りの山道が崖崩れで移動不能になったら?
もし、・・・・
いくらでも出てきますよね。
それこそ、もし、どうしても悪天候のソロキャンに挑戦したいと言う考えであれば、思い付く全ての「もし」を全て対応可能な装備で固め、泥水に浸かった装備を乾かして整備出来る環境と時間があると言い切れるのであればチャレンジしてみるのも一興でしょう。
但し、絶対に他人には迷惑をかけない。
これが絶対条件となるのは言うまでもありませんね。
本当ならこの原稿は何処かのキャンプ場で書いている予定でした。
ところがお盆休み中は殆どが・・・雨・・豪雨・・雷雨・・・・で。最終の2日間にキャンプを強行したわけですが、現場で確認したところ、曇りのはずが降水確率90%という予報に変わっていたわけです。
キャンプシーズン前半が終わると言うのにトホホです。
では、また。
雨雨雨・・・・うっとしい天気ですね。
というか、一部地域では災害と化していますね。
待ちにまった七月の三連休などは、有給をくっつけて5連休なんて考えていましたが、雨予報で断念、何とか一泊くらいは出掛けたいと馴染みのキャンプ場の天気予報を何度も確認していましたが、コロコロと予報が変わるので諦めてしまいました。
夏っ!特に初夏!!は大好きな季節なのですが、どうもこの梅雨だけはうっとうしくてイライラします。
そして盆休みもキャンプどころではない天気でした。
特にここ数年休日と雨が重なる週が多いので、尚更うんざりしますね。
まあ、そんなわけで今回は雨キャンプのお話をしたいと思います。
キャンプという趣味はとにかく天気やキャンプ場のコンデションに大きく影響されることは皆さんも身に染みて感じているかと思います。
特に天候だけは人間の力ではどうにもできない事なので、ひたすら週間天気図とにらめっこしながら、行きたいキャンプ場、行けそうなキャンプ場を週始めから検討し始めることになります。
自分は馴染みのキャンプ場を青森岩手秋田の三県にまたがって10ヶ所ほどを年間で回って歩くので、少しばかりの悪天候なら回避できるのですが、7月の梅雨だけはどうにもならないのです。
更には年々降水量が激化しているので、キャンプに行って遭難してしまうような危険性もあるわけで、梅雨に限らず夏のゲリラ豪雨にも細心の注意が必要となってきました。
昨年は二回ゲリラ豪雨に直撃されました。
まるで滝のような豪雨と雷に大慌てで東屋やら待避所に逃げ込んでしまいました。
雨はまだ何とかなるのですが、それに雷がくっついてこられるとさすがに避難しないわけにも行かず、大慌てでジープに飛び乗る羽目になります。
あっ、ちなみに車に落雷しても窓を閉めきってさえいれば車体表面からタイヤを伝って地面に抜けるらしいので、車の中は有効な待避所となります。
但し、ジープの上半分は帆布で出来た幌なので、落雷を受ければシートの上で黒焦げになる可能性が大です・・・・
幌車に乗っている方々は要注意ですね。
では本題に入りましょう。
先ずはキャンプ場に移動している状態から既に問題が始まっている事が良くあります。
目的地に向かってハンドルを握っている時、目的地方向にモクモクと真っ黒で巨大な入道雲が立ち上がってきたとします。
こんな不吉な代物が目に入ったら、徒歩、自転車、オートバイで移動しているのであれば、即座にコンビニのような雨風をしのげる建物に避難するべきでしょう。
雨雲から逃げている最中です。
すかさず天気予報を調べ、どのような状況なのかを認識し、対策を考えてください。
雨雲が遠ざかっているのなら、取り合えず、心配することもありませんが、こちらに向かっている場合は、深刻な状況を考えなくてはなりません。
道路が冠水したり、河川の増水、崖崩れ、倒れた木々による道路の寸断などが考えられるからです。
物凄い豪雨の跡に倒木で通れなくなった時の1枚です。
木にワイヤーをかけて引きずり出そうと考えたのですが、倒木が電線の上にのしかかっているので断念しました。
ネット情報をフルに活用し、単なる夏のにわか雨なのか、局所的なゲリラ豪雨なのかを素早く見極めることが重要です。
もし道路の冠水や停電などの豪雨災害が発生しているのであれば速攻で引き返すべきでしょう。
濃い霧と小雨で全く前が見えなくなった時の1枚です。
狭い山道で対向車が来ても分かりません。
せっかくのキャンプなのに・・・
その気持ちは自分もわかります。
しかしモタモタと悩んでいるうちに豪雨に追い付かれてしまえば、交通インフラの寸断で引き返す事も出来なくなります。
道路が完全に水没してしまえば、非常に危険な状態となります。
道路と路肩の区別がつかなくなり、どこを走っているのか判断がつかなくなります。
限界を越えて流れ込む雨水で側溝やマンホールの蓋が外れてしまい、移動に危険を伴う状況の中に孤立してしまいかねません。
無理に走りでしても路肩に脱輪、最悪転落しかねない事態となります。
また道路を冠水している水は単なる雨水ではなく、トイレや下水から溢れ出した危険な汚水であり、傷口に触れることがあれば、何らかの感染症に罹患する可能性が非常に高くなります。
夏のゲリラ豪雨はいつどこで発生しても不思議ではありません。
常に注意を怠らないことです。
とまあ、ちょっと脅かしてしまいました。
ここまで極端ではなくとも、夏の雨キャンプは誰もがいずれ体験することです。
その時になって慌てないように、事前に何らかの対策は必要かと思います。
ネット動画などを見ると大したことがないように見受けられるかもしらません。
むしろ、ちょっとしたアドベンチャー気分にひたれるかも!?
なんて考えるかもしれませんね。
急変した天候により雨に祟られた。
これはよくある事で、設営撤収時に降られなければ特に問題はありません。
ただ、初心者が面白そうだから、程度の感覚で大雨の最中にキャンプを強行つもりなら、
止めなさい。
はっきり自分はそのように言います。
高名な動画発信者などが悪天候キャンプを発信したりしていますが、動画の内容が全てだとは考えないでください。
自分はできるだけ悪天候を避けるようなキャンプ日程を組むようにしていますが、それでも何年かに一度位は完全に天気予報に裏切られ、酷い目にあったりします。
実はこの原稿を書いている今、天気予報にまたしても騙され、豪雨の真っ只中にいます。
予報が更新される度にコロコロと変更され、どんどんと悪い方向に更新されていきました。
そして深夜、とうとうポツポツとテントに雨粒が当たりだし、30分もしないうちに豪雨に・・・・
設営当日は穏やかな良い天気だったのです。
この晩までは最高でした。
事前にペグとガイロープは確認してあったので、キャンプサイト自体には心配が無かったのですが、予報では朝8時に一度止むことになっていますが、それ以降は一日中雨になっています。
今回は二人用のコットンテントなので四人用に比べ半分の手間で撤収が可能ですが、それでもギア類の乾燥と撤収を1時間で済ませるのは不可能です。
夜が明け、少しばかり早い朝飯を取り、珈琲を飲みながら空の具合を確認してみますが、強くなったり弱くなったりを繰り返すだけで止むような感じはしません。
周囲は池と川になっていてサイトもほぼ水没状態です。
すでに周囲が水没し始めています
今回は一泊の予定でタープを張っていませんが、天幕代わりのキャノピーを用意してあったので、その下で外回りのギアを片付け、いつでも車に運び込めるようにしておきます。
足元は2cmほども水没し、テントも水溜まりの上に立っているようです。
靴下を脱ぎ、足をキレイに拭き取って今度はテント内の片付けです。
必要ない物は車に運んでいたので、30分で完了です。
後は、なるようになれだ!
半分開き直って、テントの中で寝転がっていると、いつの間にか小降りに変わりました。
良し、ここだ!
テントから飛び出すと深い霧に包まれてはいますが、雨は止んでいます。
手早くギアの収納ケースをどんどん車に運び込み、いよいよテントに手を掛けようとしたところでタイムアウト・・・
いっきに大降りとなりました。
慌てて側の炊事場に緊急待避です。
事前に準備しておいた折り畳みのビーチベッドに腰掛け、珈琲を沸かしながら天候の神様に○指を突き上げます。
こうなったら持久戦です。
叩きつけるように降ってきました。
幸いこの野営場は貸しきり状態。
炊事場の施設は独占できるので、ここである程度の作業が可能です。
襲来するアブとブヨの群れを蚊取り線香と電撃ラケットで迎撃しながらベッドに転がって静かに読書の時間です。
内心ジリジリしながら待つこと約1時間・・・滝の真下に立っているような豪雨が線を引いたようにピタっと止みました。
テントに向かってダッシュです。
西の空に灰色の雲がかかっているので、この晴れ間は一時的なものでしょう。
慌てず落ち着いてテントを解体、ペグの数を数え、ガイロープを纏めて縛り二つ折りにしたテントをビーチベッドに乗せたところで再びタイムアウト!
一気に降りだした豪雨の中、素早くポンチョを被り、残っていたグラウンドシートとポール他小物を回収し、やっと一息です。
テント、キャノピー、グランドシートの泥や張り付いた草木を洗い流し、拭き取ったら軽く乾かします。
湿度が90%を越えている状態なので、乾燥させることは出来ません。
あくまで水気を切る程度です。
40分ほどかけて拭き取りと梱包をすませ、積み込みのためジープを炊事場に横付けさせます。
少しばかり雨足の弱まった中、ドロドロの姿のままシートに飛び乗り、エンジンを始動、回転をあげないようにエンスト寸前でクラッチを慎重に繋ぎますが、リヤタイヤは空転するだけで30センチも前に進みません。
柔らかな傾斜地、泥と雑草、流れ落ちてくる雨水の組み合わせはオフロードに特化したブロックタイヤにも手強い相手です。
短気を起こしていたずらにアクセルを踏みつければ、ゴツいマッドタイヤは、まるでチェーンソーのようにいとも簡単に地面に食い込んでいきます。
すかさずジープを飛び降り、フロントホイール真ん中に飛び出ている、フリーホイールハブと呼ばれている動力伝達のための装置を、4×2から4×4に切り替えます。
これでフロントのデフとフロントタイヤが直結状態となり、最悪の路面状態の中で、悪路を自在に走り回るために作られた、ジープ本来の本当のパフォーマンスを発揮できるのです。
トランスファーを4HIに切り替えると、フロントタイヤに動力が伝わり、当たり前のように斜面を登り、真っ直ぐ走ることさえ難しい泥道を普通に走りだします。
無事炊事場に横付けできました。
この間ジープが走った距離はたかだか数十メートルですが、もしオフロードに適していない車両ならば、克服できない非常に困難な数十メートルにもなりかねないのです。
帰りはいつものように中腹にある温泉でドロまみれの身体をキレイさっぱりと洗い、泡風呂に身を沈めるとあまりの気持ち良さに疲れが抜けて行きます。
キャンプ帰りの温泉と言うのも中々に良いもので、キャンプ場とひなびた温泉地と言うものはセットになっています。
マッサージ機に座り、15分ほど仮眠し、ゆったりと降りしきる雨を眺めているとほんの1時間前の苦労が夢のようです。
いつものマ○いラーメンを食べ、のんびりと帰路につきます。
と、この当たりでYOUtubeの動画は終わりになるのでしょうが、実際はこの後も苦難が続くのです。
夕方八戸に到着。
雨が小降りだったののでキャンプ道具を降ろし、泥だらけの車内に洗車ホースを突っ込んで、泥と草木、無賃乗車の虫共を吹き飛ばします。
疲れていたので今日はここまで・・・
翌日、会社を1時間早く飛び出し、グチャグチャのテント類の乾燥作業に取りかかります。
ところが天候自体が思わしくなく、今にも降りだしそうなのです。
本当は一旦組み立ててその状態で乾かすのが最善なのですが、その判断ができません。
さらには他にもキャノピーとグランドシートも乾かさなければならないので、モタモタしているわけにはいかないのです。
結局キャノピーとグランドは庭の物干しで乾かし、テントは2階ベランダで乾かすこととしました。
ボタボタと滴るテントとシートを袋から取りだし、信じられない重さになったテントを苦労して運び上げ、ベランダ物干しになんとかぶら下げることに成功しました。
水を吸って重くなっているキャンバステントを二階まで運び、物干し竿にかけるのは、大の男でも一苦労です。
シート類は庭で2時間ほども乾かして問題ない程度に乾燥させることができました。
後はテントだけなのですが、なんと翌日から東北を災害級の豪雨が襲い、東北一帯がとんでもないことに・・・
昔から自分は天気の神様と仲が悪い訳ですが、ここまで極端なのも珍しいです。
結局テントの乾燥に3日を要しました。
もしベランダがなければ、到底乾かすことはできなかったでしょう。
今回は何とか対応が上手くいきましたが、少しばかり条件が悪ければ更に対応が困難な状況に陥ったかもしれません。
もし、一日中豪雨だったら?
もし、キャンプ場自体が災害避難区域に指定されていて、避難指示が出てしまったら?
もし、炊事場や東屋が無かったら?
もし、車がスタックして動けなくなったら?
もし、足元が滑って転倒し、怪我で動けなくなったら?
もし、帰りの山道が崖崩れで移動不能になったら?
もし、・・・・
いくらでも出てきますよね。
それこそ、もし、どうしても悪天候のソロキャンに挑戦したいと言う考えであれば、思い付く全ての「もし」を全て対応可能な装備で固め、泥水に浸かった装備を乾かして整備出来る環境と時間があると言い切れるのであればチャレンジしてみるのも一興でしょう。
但し、絶対に他人には迷惑をかけない。
これが絶対条件となるのは言うまでもありませんね。
本当ならこの原稿は何処かのキャンプ場で書いている予定でした。
ところがお盆休み中は殆どが・・・雨・・豪雨・・雷雨・・・・で。最終の2日間にキャンプを強行したわけですが、現場で確認したところ、曇りのはずが降水確率90%という予報に変わっていたわけです。
キャンプシーズン前半が終わると言うのにトホホです。
では、また。
2022年07月18日
コットンテントの魅力
こんにちわMASADA556です。
しばらく投稿をサボっていたので2本投稿いたします。
お時間のある方はゆっくりとお付き合いくださいませ。
今回の冒頭は岩手県のとあるキャンプ場から書き始めています。(6月下旬)
ここは年に2~3回は必ず訪れるキャンプ場で、山の中腹から遠くに見える八戸市やその向こうの太平洋が一望できます。
その素晴らしい景観に惹かれ、疲れた神経を癒しにこの静かなキャンプ場を訪れるのです。
日が暮れれば全く人の気配は無くなり、遠くの街の灯りを眺めながら森のざわめきに耳を傾け、山の静謐な空気に包まれるのは最高のひとときです。

街の喧騒といった人工的な音が一切入ってこない空間なので、仕事中は過度の負担をかけている神経がアイドリング状態に落ち着きます。
他人の声も聞こえないので、何も考える必要がなくなり、自然と頭の中が空になります。
この何も「考える必要のない時間」
という物を作り出すのは大変難しく、自分ではソロキャンプの時だけしか経験できない貴重な時間です。
仕事や梅雨の天候不順の合間を縫ってようやくここに戻って来ました。
いつもの場所にタープを張りテントを立て、準備万端整えて汗をぬぐいながら椅子に座り冷たいドリンクを口にしたとき、
「戻ってきたな・・・」
自然とそんな考えが浮かびます。
出掛けてきたのではない、本来居るべき場所に戻ってきただけなのだ。
この何とも言えない解放感を求めるキャンパーは、自分だけではないはずです。

ほとんど人気が無く、最高の眺め、静かな山の空気、そしてすぐ横には山の神様を祀った社があり、自分を見守ってくれます。
正に良いことずくめの野営場なのですが、唯一怖いのは時折突風が吹き付けることです。
まあ、海に面した山の斜面なので仕方のない事なのですが、風の強い時に当たるとちょっと怖いです。
冗談事ではなくタープやテントが飛ばされそうになるほどです。
以前天候の問題で時間的な余裕がなく、一泊だけキャンプしようと考え、この夜営場に来たときにやられそうになりました。
夕方晩飯の準備をしている時に何の前触れもなく突然の突風!
2人用の小型テントが押し潰されそうなほど歪み、テーブルの上の道具類が全て吹き飛びました。
幸いな事にガスコンロで簡単な調理をするつもりだったので、炭や焚き火といった火の類いは使っておらず、大事には至りませんでした。
ただその晩は何度も突風に見舞われ、眠れぬ一夜を過ごしました。
翌日、今にも降りだしそうな空模様のなか、撤収を急いでいると、テントを支えているアルミポールのジョイント部分二ヶ所に4センチほどの亀裂が見つかり、テントが倒壊寸前だった事が分かりました。
オートバイでのツーリング用に手に入れた軽量テントだったので、むしろ良くもってくれたと感心したくらいです。
古いものですが、国産の有名メーカーの製品だったことが壊れなかった理由のひとつだと考えます。
以来その夜営場には他のポリエステルのテントではなく、アメリカ製のコットンテントを持って行くことにしています。
一度だけ強風が一日中吹き付ける日がありましたが全く問題とせず、ゆったりとテントの中にお籠りして本を読む時間を過ごす事ができました。
そして今日の現在地の天候は無風となっていますが、実際にはちょっと強めの風がふき、時折突風が吹き抜けていきます。
山の天気予報とは当てにならないものです。
と、言う訳で今回は、コットンテントの魅力。についてお話してみようと思います。
今のところ自分はコットンテントを2つ持っています。
とは言っても同じメーカーのテントの感想なので、なんか違うんじゃない?
などと思われた方がおられましたら、どうか御容赦を。
皆さんはキャンプ地で愛用されているテントのどこに魅力を感じどんな機能を重視していますか。
小型軽量で持ち運びに困らない。前室が広くタープ要らずだ。とても広くファミリーがゆったりと過ごせる・・・
皆さんそれぞれの思い入れがあり、これからのキャンプで様々な思い出作りに一役かってくれる事でしょう。
またキャンプ地での主役として安全な一夜の宿となってくれることでしょう。
但し、全てが順風満帆なキャンプだった。とは行かないはずです。
当たり前ですが自然環境と調和していかなければ成立しない趣味なので、季節、時期そして天候といった事柄に常に配慮していかなければならないと言った難しい側面も持ち合わせています。
春、夏、秋、冬
日本ほど四季の恵まれた国も珍しく、季節ごとに自然が見せる表情も様々です。
また同じ季節でも訪れる場所や時期で、環境は全く変わっていきます。
元々キャンプ場と言うのは高原であったり山中であったり森林であったりと街とは大分違った環境に作られていることがほとんどなので、その辺りを十分考慮にいれて持っていくテント、タープ、道具類を判断しないと、もしかしたら大変な目にあうかもしれません。
そこで、○○キャンプ場に週末に行こう。と考えた時、装備で真っ先に考えるのはやっぱりテントです。
気温、風、天候、距離、宿泊日数、環境、キャンプ場の混み具合、キャンプサイトの大小・・・
そんなところをプラスマイナスしながら考えます。
そのような条件を加味した結果、やはり行き着くのはいつものコットンテントなのです。
勿論人が作り出した道具ですから100%目的に合致している訳はありません。
その辺りの条件は少しばかりの工夫と他の道具類で補えば良い事なので、ベテランの腕の見せ所。と言った所でしょうか?
まず、このテントの特徴として最初に上げるのは、物凄く丈夫と言うか頑強に作られていることです。
それは海外のキャンプ動画などでも多数アップされています。
雪深い真冬の山間部や、すさまじい雪嵐が吹き付ける大雪原などでも問題なく耐えきってしまう頑強さに、ベテランハンターから極地の自然を愛し、何週間でも僻地で生きていけるようなヘビーユーザーなどに信頼と人気があるテントメーカーです。
その代償として、とても重く、梱包状態も大きくてかさ張ります。
穏やかな季節だけを楽しむライトなユーザーには明らかなオーバースペックとなります。
また、それなりに高価なテントですので、購入を考えるならば、少しばかり慎重な判断が必要かもしれません。
当然ですが、徒歩、オートバイ、自転車などでのキャンプでは運搬がほぼ不可能なので、あくまで車両を利用したキャンパーを対象としています。
まあ、前置きはここまでとしましょう。
今のところ、一泊~二泊程度のキャンプでは小型の2人用を、それ以上の時は4人用の物と、大体そんな感じで使い分けています。
今回は4人用のモデルで利点や欠点を話していきます。

幾つもの特徴を持ったテントですが、先ず設営の簡単さが上げられるでしょう。
但し国産モデルでは類を見ない独特な設営方法ですので最初は戸惑う事でしょう。
またテント自体の重量を持ち上げるような組み方なので、それなりの腕力と少しばかりのコツが必要です。
キャノピー以外はガイロープを一切必要としない反面、4人以上のテントとなると、かなりの数のペグを打ち込んで固定する形でテント自体を安定させています。
ドーム型テントのような手軽さはありません。
では中に入ってみましょう。
最初に目につくのは、分厚いビニール素材でできたフロアでしょうか。
触ってみればわかりますが、穴でも開けない限り浸水することはありません。
ただ独特の薬品のような匂いがするので、ちょっと気になるかもしれませんね。
自分にとっては我が家の香りのようなものです。
そして一番に感じるのは、ロッジ型テントの特徴でもある中の広さでしょう。
ほぼ垂直にウォールが立っているので、四角形に近い構造がもたらす広さは、他の構造のテントとは比較になりません。
身長170センチの自分が当たり前に立って歩けるだけの高さもあり、圧迫感と言うものを感じることはありません。
まるで小さな部屋の中にいるような感覚を覚えます。
ウォールの繊維がコットンであるために、光や風などの遮断性が高く、ペラペラのポリエステルとは違い、壁のような安心感があります。
夜はゆったりと熟睡できますよ。

そして一番気になるところ、雨に対してはどうなの?
今まで2回ほど集中豪雨に見舞われましたが、全く問題としませんでした。
雨が降るとコットン生地が水を吸い込み、繊維が膨張して浸水を防ぐという面白い発想を元に作られているのです。

天井部分に水たまりができていますが、内側に染み通ってくるくることはありません。
またウォールの外側は撥水性も抜群で、浸水の不安を感じることはありません。
もう1つ、テント最大の問題である結露に対してですが、これもまた問題ありません。
当然結露はするのですが、ポリエステルのように内壁一面に張り付き
雨のように滴り落ちてくる。といった心配とは皆無です。
発生した水分はコットン生地に吸い取られ、ほとんど水滴が発生しません。
ウォールを触ってみると、柔らかな繊維が水分を吸い込んで、微かに湿っているのが分かります。
これには驚きました、シングルウォールタイプのテントの厄介な問題はこの結露で、特に外気とテント内の温度差が大きいときは、テント内側がびしょ濡れになります。
これが寝具を濡らし、寒い時期の連泊キャンプでは意外な障害となります。
羽毛入りの寝袋などは結露を吸収しやすく、ひどく濡らしてしまえば冬季の連泊ならば諦めなくてはならなくなるほどです。
コットンテントならば、その心配も余りしなくて良いようです。
このメーカーのテントに限った事ですが、入り口が大きく取られ、正面と裏側にも同じように出入りができるので物の搬入や出入りにストレスを感じる事がありません。
その他にも大きな小物入れやウォール両側についているランタンフック、結露を防ぐためのベンチレーター、入り口両面の大きな網戸は真夏でも十分な外気を取り入れてくれます。入り口を覆うキャノピー、ここに椅子と小さなテーブルを置いておけば、小雨程度なら問題なく過ごすことができます。
キャンプそしてテントと言うものを、十分理解している人間が設計したテントであると思います。
アメリカ人らしい機能的で合理的なテントです。
色々と誉め契りましたが、1つだけ困ったことがあります。
設営の簡単さは最初に説明しましたが、逆に撤収の時がいささか大変なのです。
キャンプの数日間が好天であればさしたる問題は無いのです。
陽射しと風で十分に乾かし、よいしょと畳んでしまえばいいのですが、途中で雨に見舞われると撤収の手間が倍位に跳ね上がります。
このテントの耐水性の1つであるフロアのバスタブ構造が少しばかり問題なのです。
ご存じの通り、テントのフロアがウォールまで立ち上がっている構造をバスタブ構造と言いますが、このテントは更にウォール部分が地面から持ち上がる構造になっているので、降った雨がフロアシートとその下に敷いているグラウンドシートの間に入り込み、いつまでも乾かないのです。
そんな時の撤収手順はこうです。
先ずはテント本体を徹底的に乾かします。
どんなテントであれ、これを怠るとカビの原因になります。
次からが問題です。
まず乾いたタオルを7~8枚準備し、ポールを解体したテントを両端から真ん中に向けて畳んでいきます。

するとフロアシートの下にデッカイ水溜まりが出来ている訳です。

テントを濡らさないように慎重に畳みながらシートの水をタオルで拭き取っていきます。
拭き終わったらそのまま風に当て5~7分程も乾かし、また折り畳んでは拭き取りを繰り返すのです。
両辺を真ん中まで畳んだら、別に広げたシートまで持っていき、そこで残った水気を拭き取り、畳んで袋に押し込みます。
そしてプールのようになっているグランドシートも、また拭き取って乾かし畳みます。
この作業に、ざっと1時間はかかります。
乾きが悪ければ当然もっとかかります。
五月のキャンプの時は、畳んでいる最中に2度も通り雨に降られ、最悪でした。
なんと撤収に3時間を要しました。
せっかく乾かしたテント、タープを始め、ずぶ濡れになったギアを拭き取り、乾かすといった作業を3回も行った訳ですから・・・
自分はギアに何か問題が起きない限りキャンプ場で全ての事を完結させます。
自宅に戻ってからギアを広げて何かをするといった事は絶対しません。
しかしこの時だけは流石の自分も心がくじけそうになりました。
適当にジープに突っ込んで家で乾かすか・・・?
しかし、キッチリ梱包しないと車の中に積みきれない事は事前に分かりきっていることです。
なにせ運転席以外に空いているスペースはないのですから。
管理人さんに預けて、後で取りに来ようか・・・?
しかし、仕事の都合で来れるとしても、一週間後です。
ずぶ濡れのギアを一週間放りっぱなしにしては、錆びとカビで全滅することは目に見えています。
濡れた椅子に座り込み、また強くなってきた陽射しにため息をつきながら温くなったコーラで一息ついて、3回目の撤収作業に取りかかりました。
実はこのテントの購入を考えた時最大の難関はこの撤収時の天候でした。
フロアシートの事は別としても、重量や梱包時の大きさから考えて、雨天時の撤収は無理に近いと考えていたからです。
結局手に入れて以降、このテントでのキャンプ後半には撤収のタイミングを考えて、天気予報とにらめっこといった状態です。
これだけはポリエステル製のテントには敵いませんね。
薄く非常に軽い材質なので、5分も日に当ててやれば乾いてしまいます。
かかる手間も1/3程度でしょう。
そんなことは分かりきっているのに、なぜか大きくて重いコットンテントをジープの荷台に積み込んでいる自分なのです。
そして最後に、大した問題ではない・・・いや嫌いな人には大問題でしょう。
実はこのテントメチャクチャ虫にたかられます。
2年前の秋にはテントに地蜘蛛が取りついて離れず大変でした。
自分は刺してくる虫以外はあまり気にしない質なのですが、
いくら払い落としてもテントに取りつこうと全速で駆け戻ってくるのでキリがありません。
仕方なく蜘蛛を踏み潰しながらの撤収という何ともゾッとしない作業となりました。
虫たちにとってもコットンの肌触りというのは魅力的に感じるようです。
何とも迷惑な話なのですが・・・
書き終わったら撤収に入ります。
キャンプ場で原稿を書き上げたのは久しぶりです。
天気予報がまた急遽変更されて、明け方から3時間ばかり強い雨が降りました。
現在11時16分です。
タープの下で外気温32°、厳しい陽射しが照りつけ、風も時おり突風が吹き付けてきます。
さあ、大仕事の始まりです。
では、また。
PS
実はキャンプの帰りに少しばかり寄り道したのですが、ちょっと奇妙なモノを見つけました。
自分は帰りに時間があれば必ずどこかに寄り道してしまう癖があります。
一番多いのは新たにキャンプ場を見つけて歩いたり絶景ポイントを探してジープを向かわせます。
今回も心当たりのある山の中向かってハンドルを切りました。
全く対向車とすれ違うことのない山道を20分ばかり走らせ、目的の場所を見つけました。
綺麗に整えられた場内を走り、駐車場に車を止めると、目の前には連なる山々とその向こうの太平洋が日差しに照らされて素晴らしい展望を見せてくれます。
スゲーっ最高じゃん!!
思わずそんな声が出ました。
早速車から飛び降り景色を満喫すると、施設を見学させてもらうことにしました。
管理棟に向かうと無人のようで、問い合わせ先などが壁に貼りけてあります。
一通り目を通して、場内を散策します。
芝生も手入れされゴミ一つ落ちてません。
炊事場も手入れされ、水も出ます。
中々魅力的な所なのですが・・・・何の音もしません。
つまり誰一人人がいないのです。
林間サイトなる所に向かってみましたが、斜面がやたらと急なうえに舗装されていないのでキャンプ道具を抱えてここまで上がってくるのはまず無理です。
更にその道を上っていくと頂上付近に子供用の遊園地が現れたのには驚きました。
木々に埋め尽くされそうになりながらも、滑り台、階段、スロープ、ロープ通路などが組み合わされた結構大きくて色鮮やかな遊戯施設が森に包まれながら、ポツンと存在しているのです。
余りの違和感に背すじにゾクリとした寒気を感じます。
綺麗に整備されついさっきまで子供たちが遊んでいたような錯覚を覚えるほどです。
施設を横にそれて上を見上げると、草木に覆われた東屋が見えたので、よいしょと登っていくと、
ジャリ、ギシっ・・・・
何かが東屋の中で歩いているような音がします。
首筋が泡立つような嫌な感覚に思わず足を止めそうになりました。

結局人などいる訳もなく、朽ちかけた東屋があるだけでした。
誰も来ない山奥の遊園地。
何とも奇妙で生理的な怖さを感じます。
夕日の中、足早に森を抜けジープに乗り込み、ディーゼルエンジンの心強い音に軽くため息をついて、施設を後にしたのでした。
しばらく投稿をサボっていたので2本投稿いたします。
お時間のある方はゆっくりとお付き合いくださいませ。
今回の冒頭は岩手県のとあるキャンプ場から書き始めています。(6月下旬)
ここは年に2~3回は必ず訪れるキャンプ場で、山の中腹から遠くに見える八戸市やその向こうの太平洋が一望できます。
その素晴らしい景観に惹かれ、疲れた神経を癒しにこの静かなキャンプ場を訪れるのです。
日が暮れれば全く人の気配は無くなり、遠くの街の灯りを眺めながら森のざわめきに耳を傾け、山の静謐な空気に包まれるのは最高のひとときです。
街の喧騒といった人工的な音が一切入ってこない空間なので、仕事中は過度の負担をかけている神経がアイドリング状態に落ち着きます。
他人の声も聞こえないので、何も考える必要がなくなり、自然と頭の中が空になります。
この何も「考える必要のない時間」
という物を作り出すのは大変難しく、自分ではソロキャンプの時だけしか経験できない貴重な時間です。
仕事や梅雨の天候不順の合間を縫ってようやくここに戻って来ました。
いつもの場所にタープを張りテントを立て、準備万端整えて汗をぬぐいながら椅子に座り冷たいドリンクを口にしたとき、
「戻ってきたな・・・」
自然とそんな考えが浮かびます。
出掛けてきたのではない、本来居るべき場所に戻ってきただけなのだ。
この何とも言えない解放感を求めるキャンパーは、自分だけではないはずです。
ほとんど人気が無く、最高の眺め、静かな山の空気、そしてすぐ横には山の神様を祀った社があり、自分を見守ってくれます。
正に良いことずくめの野営場なのですが、唯一怖いのは時折突風が吹き付けることです。
まあ、海に面した山の斜面なので仕方のない事なのですが、風の強い時に当たるとちょっと怖いです。
冗談事ではなくタープやテントが飛ばされそうになるほどです。
以前天候の問題で時間的な余裕がなく、一泊だけキャンプしようと考え、この夜営場に来たときにやられそうになりました。
夕方晩飯の準備をしている時に何の前触れもなく突然の突風!
2人用の小型テントが押し潰されそうなほど歪み、テーブルの上の道具類が全て吹き飛びました。
幸いな事にガスコンロで簡単な調理をするつもりだったので、炭や焚き火といった火の類いは使っておらず、大事には至りませんでした。
ただその晩は何度も突風に見舞われ、眠れぬ一夜を過ごしました。
翌日、今にも降りだしそうな空模様のなか、撤収を急いでいると、テントを支えているアルミポールのジョイント部分二ヶ所に4センチほどの亀裂が見つかり、テントが倒壊寸前だった事が分かりました。
オートバイでのツーリング用に手に入れた軽量テントだったので、むしろ良くもってくれたと感心したくらいです。
古いものですが、国産の有名メーカーの製品だったことが壊れなかった理由のひとつだと考えます。
以来その夜営場には他のポリエステルのテントではなく、アメリカ製のコットンテントを持って行くことにしています。
一度だけ強風が一日中吹き付ける日がありましたが全く問題とせず、ゆったりとテントの中にお籠りして本を読む時間を過ごす事ができました。
そして今日の現在地の天候は無風となっていますが、実際にはちょっと強めの風がふき、時折突風が吹き抜けていきます。
山の天気予報とは当てにならないものです。
と、言う訳で今回は、コットンテントの魅力。についてお話してみようと思います。
今のところ自分はコットンテントを2つ持っています。
とは言っても同じメーカーのテントの感想なので、なんか違うんじゃない?
などと思われた方がおられましたら、どうか御容赦を。
皆さんはキャンプ地で愛用されているテントのどこに魅力を感じどんな機能を重視していますか。
小型軽量で持ち運びに困らない。前室が広くタープ要らずだ。とても広くファミリーがゆったりと過ごせる・・・
皆さんそれぞれの思い入れがあり、これからのキャンプで様々な思い出作りに一役かってくれる事でしょう。
またキャンプ地での主役として安全な一夜の宿となってくれることでしょう。
但し、全てが順風満帆なキャンプだった。とは行かないはずです。
当たり前ですが自然環境と調和していかなければ成立しない趣味なので、季節、時期そして天候といった事柄に常に配慮していかなければならないと言った難しい側面も持ち合わせています。
春、夏、秋、冬
日本ほど四季の恵まれた国も珍しく、季節ごとに自然が見せる表情も様々です。
また同じ季節でも訪れる場所や時期で、環境は全く変わっていきます。
元々キャンプ場と言うのは高原であったり山中であったり森林であったりと街とは大分違った環境に作られていることがほとんどなので、その辺りを十分考慮にいれて持っていくテント、タープ、道具類を判断しないと、もしかしたら大変な目にあうかもしれません。
そこで、○○キャンプ場に週末に行こう。と考えた時、装備で真っ先に考えるのはやっぱりテントです。
気温、風、天候、距離、宿泊日数、環境、キャンプ場の混み具合、キャンプサイトの大小・・・
そんなところをプラスマイナスしながら考えます。
そのような条件を加味した結果、やはり行き着くのはいつものコットンテントなのです。
勿論人が作り出した道具ですから100%目的に合致している訳はありません。
その辺りの条件は少しばかりの工夫と他の道具類で補えば良い事なので、ベテランの腕の見せ所。と言った所でしょうか?
まず、このテントの特徴として最初に上げるのは、物凄く丈夫と言うか頑強に作られていることです。
それは海外のキャンプ動画などでも多数アップされています。
雪深い真冬の山間部や、すさまじい雪嵐が吹き付ける大雪原などでも問題なく耐えきってしまう頑強さに、ベテランハンターから極地の自然を愛し、何週間でも僻地で生きていけるようなヘビーユーザーなどに信頼と人気があるテントメーカーです。
その代償として、とても重く、梱包状態も大きくてかさ張ります。
穏やかな季節だけを楽しむライトなユーザーには明らかなオーバースペックとなります。
また、それなりに高価なテントですので、購入を考えるならば、少しばかり慎重な判断が必要かもしれません。
当然ですが、徒歩、オートバイ、自転車などでのキャンプでは運搬がほぼ不可能なので、あくまで車両を利用したキャンパーを対象としています。
まあ、前置きはここまでとしましょう。
今のところ、一泊~二泊程度のキャンプでは小型の2人用を、それ以上の時は4人用の物と、大体そんな感じで使い分けています。
今回は4人用のモデルで利点や欠点を話していきます。
幾つもの特徴を持ったテントですが、先ず設営の簡単さが上げられるでしょう。
但し国産モデルでは類を見ない独特な設営方法ですので最初は戸惑う事でしょう。
またテント自体の重量を持ち上げるような組み方なので、それなりの腕力と少しばかりのコツが必要です。
キャノピー以外はガイロープを一切必要としない反面、4人以上のテントとなると、かなりの数のペグを打ち込んで固定する形でテント自体を安定させています。
ドーム型テントのような手軽さはありません。
では中に入ってみましょう。
最初に目につくのは、分厚いビニール素材でできたフロアでしょうか。
触ってみればわかりますが、穴でも開けない限り浸水することはありません。
ただ独特の薬品のような匂いがするので、ちょっと気になるかもしれませんね。
自分にとっては我が家の香りのようなものです。
そして一番に感じるのは、ロッジ型テントの特徴でもある中の広さでしょう。
ほぼ垂直にウォールが立っているので、四角形に近い構造がもたらす広さは、他の構造のテントとは比較になりません。
身長170センチの自分が当たり前に立って歩けるだけの高さもあり、圧迫感と言うものを感じることはありません。
まるで小さな部屋の中にいるような感覚を覚えます。
ウォールの繊維がコットンであるために、光や風などの遮断性が高く、ペラペラのポリエステルとは違い、壁のような安心感があります。
夜はゆったりと熟睡できますよ。
そして一番気になるところ、雨に対してはどうなの?
今まで2回ほど集中豪雨に見舞われましたが、全く問題としませんでした。
雨が降るとコットン生地が水を吸い込み、繊維が膨張して浸水を防ぐという面白い発想を元に作られているのです。
天井部分に水たまりができていますが、内側に染み通ってくるくることはありません。
またウォールの外側は撥水性も抜群で、浸水の不安を感じることはありません。
もう1つ、テント最大の問題である結露に対してですが、これもまた問題ありません。
当然結露はするのですが、ポリエステルのように内壁一面に張り付き
雨のように滴り落ちてくる。といった心配とは皆無です。
発生した水分はコットン生地に吸い取られ、ほとんど水滴が発生しません。
ウォールを触ってみると、柔らかな繊維が水分を吸い込んで、微かに湿っているのが分かります。
これには驚きました、シングルウォールタイプのテントの厄介な問題はこの結露で、特に外気とテント内の温度差が大きいときは、テント内側がびしょ濡れになります。
これが寝具を濡らし、寒い時期の連泊キャンプでは意外な障害となります。
羽毛入りの寝袋などは結露を吸収しやすく、ひどく濡らしてしまえば冬季の連泊ならば諦めなくてはならなくなるほどです。
コットンテントならば、その心配も余りしなくて良いようです。
このメーカーのテントに限った事ですが、入り口が大きく取られ、正面と裏側にも同じように出入りができるので物の搬入や出入りにストレスを感じる事がありません。
その他にも大きな小物入れやウォール両側についているランタンフック、結露を防ぐためのベンチレーター、入り口両面の大きな網戸は真夏でも十分な外気を取り入れてくれます。入り口を覆うキャノピー、ここに椅子と小さなテーブルを置いておけば、小雨程度なら問題なく過ごすことができます。
キャンプそしてテントと言うものを、十分理解している人間が設計したテントであると思います。
アメリカ人らしい機能的で合理的なテントです。
色々と誉め契りましたが、1つだけ困ったことがあります。
設営の簡単さは最初に説明しましたが、逆に撤収の時がいささか大変なのです。
キャンプの数日間が好天であればさしたる問題は無いのです。
陽射しと風で十分に乾かし、よいしょと畳んでしまえばいいのですが、途中で雨に見舞われると撤収の手間が倍位に跳ね上がります。
このテントの耐水性の1つであるフロアのバスタブ構造が少しばかり問題なのです。
ご存じの通り、テントのフロアがウォールまで立ち上がっている構造をバスタブ構造と言いますが、このテントは更にウォール部分が地面から持ち上がる構造になっているので、降った雨がフロアシートとその下に敷いているグラウンドシートの間に入り込み、いつまでも乾かないのです。
そんな時の撤収手順はこうです。
先ずはテント本体を徹底的に乾かします。
どんなテントであれ、これを怠るとカビの原因になります。
次からが問題です。
まず乾いたタオルを7~8枚準備し、ポールを解体したテントを両端から真ん中に向けて畳んでいきます。
するとフロアシートの下にデッカイ水溜まりが出来ている訳です。
テントを濡らさないように慎重に畳みながらシートの水をタオルで拭き取っていきます。
拭き終わったらそのまま風に当て5~7分程も乾かし、また折り畳んでは拭き取りを繰り返すのです。
両辺を真ん中まで畳んだら、別に広げたシートまで持っていき、そこで残った水気を拭き取り、畳んで袋に押し込みます。
そしてプールのようになっているグランドシートも、また拭き取って乾かし畳みます。
この作業に、ざっと1時間はかかります。
乾きが悪ければ当然もっとかかります。
五月のキャンプの時は、畳んでいる最中に2度も通り雨に降られ、最悪でした。
なんと撤収に3時間を要しました。
せっかく乾かしたテント、タープを始め、ずぶ濡れになったギアを拭き取り、乾かすといった作業を3回も行った訳ですから・・・
自分はギアに何か問題が起きない限りキャンプ場で全ての事を完結させます。
自宅に戻ってからギアを広げて何かをするといった事は絶対しません。
しかしこの時だけは流石の自分も心がくじけそうになりました。
適当にジープに突っ込んで家で乾かすか・・・?
しかし、キッチリ梱包しないと車の中に積みきれない事は事前に分かりきっていることです。
なにせ運転席以外に空いているスペースはないのですから。
管理人さんに預けて、後で取りに来ようか・・・?
しかし、仕事の都合で来れるとしても、一週間後です。
ずぶ濡れのギアを一週間放りっぱなしにしては、錆びとカビで全滅することは目に見えています。
濡れた椅子に座り込み、また強くなってきた陽射しにため息をつきながら温くなったコーラで一息ついて、3回目の撤収作業に取りかかりました。
実はこのテントの購入を考えた時最大の難関はこの撤収時の天候でした。
フロアシートの事は別としても、重量や梱包時の大きさから考えて、雨天時の撤収は無理に近いと考えていたからです。
結局手に入れて以降、このテントでのキャンプ後半には撤収のタイミングを考えて、天気予報とにらめっこといった状態です。
これだけはポリエステル製のテントには敵いませんね。
薄く非常に軽い材質なので、5分も日に当ててやれば乾いてしまいます。
かかる手間も1/3程度でしょう。
そんなことは分かりきっているのに、なぜか大きくて重いコットンテントをジープの荷台に積み込んでいる自分なのです。
そして最後に、大した問題ではない・・・いや嫌いな人には大問題でしょう。
実はこのテントメチャクチャ虫にたかられます。
2年前の秋にはテントに地蜘蛛が取りついて離れず大変でした。
自分は刺してくる虫以外はあまり気にしない質なのですが、
いくら払い落としてもテントに取りつこうと全速で駆け戻ってくるのでキリがありません。
仕方なく蜘蛛を踏み潰しながらの撤収という何ともゾッとしない作業となりました。
虫たちにとってもコットンの肌触りというのは魅力的に感じるようです。
何とも迷惑な話なのですが・・・
書き終わったら撤収に入ります。
キャンプ場で原稿を書き上げたのは久しぶりです。
天気予報がまた急遽変更されて、明け方から3時間ばかり強い雨が降りました。
現在11時16分です。
タープの下で外気温32°、厳しい陽射しが照りつけ、風も時おり突風が吹き付けてきます。
さあ、大仕事の始まりです。
では、また。
PS
実はキャンプの帰りに少しばかり寄り道したのですが、ちょっと奇妙なモノを見つけました。
自分は帰りに時間があれば必ずどこかに寄り道してしまう癖があります。
一番多いのは新たにキャンプ場を見つけて歩いたり絶景ポイントを探してジープを向かわせます。
今回も心当たりのある山の中向かってハンドルを切りました。
全く対向車とすれ違うことのない山道を20分ばかり走らせ、目的の場所を見つけました。
綺麗に整えられた場内を走り、駐車場に車を止めると、目の前には連なる山々とその向こうの太平洋が日差しに照らされて素晴らしい展望を見せてくれます。
スゲーっ最高じゃん!!
思わずそんな声が出ました。
早速車から飛び降り景色を満喫すると、施設を見学させてもらうことにしました。
管理棟に向かうと無人のようで、問い合わせ先などが壁に貼りけてあります。
一通り目を通して、場内を散策します。
芝生も手入れされゴミ一つ落ちてません。
炊事場も手入れされ、水も出ます。
中々魅力的な所なのですが・・・・何の音もしません。
つまり誰一人人がいないのです。
林間サイトなる所に向かってみましたが、斜面がやたらと急なうえに舗装されていないのでキャンプ道具を抱えてここまで上がってくるのはまず無理です。
更にその道を上っていくと頂上付近に子供用の遊園地が現れたのには驚きました。
木々に埋め尽くされそうになりながらも、滑り台、階段、スロープ、ロープ通路などが組み合わされた結構大きくて色鮮やかな遊戯施設が森に包まれながら、ポツンと存在しているのです。
余りの違和感に背すじにゾクリとした寒気を感じます。
綺麗に整備されついさっきまで子供たちが遊んでいたような錯覚を覚えるほどです。
施設を横にそれて上を見上げると、草木に覆われた東屋が見えたので、よいしょと登っていくと、
ジャリ、ギシっ・・・・
何かが東屋の中で歩いているような音がします。
首筋が泡立つような嫌な感覚に思わず足を止めそうになりました。
結局人などいる訳もなく、朽ちかけた東屋があるだけでした。
誰も来ない山奥の遊園地。
何とも奇妙で生理的な怖さを感じます。
夕日の中、足早に森を抜けジープに乗り込み、ディーゼルエンジンの心強い音に軽くため息をついて、施設を後にしたのでした。
2022年07月18日
フィールドキッチン
皆さんこんにちは、マサダ556です。
キャンプ、楽しんでいますか?
まだ寒い時期でしたが、毎年キャンプ初めはGWにとある湖畔の野営場に足を運んでいます。
春キャンプは人も少なく厄介な虫もいないので、過ごしやすいので すが、天候が不安定なのがネックですね。
ここには足掛け4日お世話になりましたが、今年は連日の雨と低温に悩まされるキャンプとなりました。
外気温が日中でも8度ほどで日が暮れると4度以下にまで低下します。
そしてあまり激しくは無いものの、シトシトと降り続く冷たい雨・・・
幸い風は弱かったのですが、それでも手足の先がギリギリと冷えてきます。
炭火に当たりながら晩飯の仕度をするのですが、こうも冷えると億劫になりがちです。
とは言うものの、コンビニ弁当ではせっかくの雰囲気がぶち壊しです。
そこで今回のお話は 「フィールドキッチン」 です。
皆さんには余り聞き覚えの無い言葉だと思います。
フィールドキッチンとは、軍隊で言う移動型の野外炊飯車あるいはそれに相当するモノをそのように呼称しています。
歴史は相当古く1800年頃にはヨーロッパでその原型が現れ、アメリカでは西武開拓時代には既にカウボーイや開拓者たちが使っていたようです。
(また寒くなってきました。ついさっきまで、9:30頃は22度だったものが今は12度です。山の天気とは本当に気紛れです。五月二日)
飯の盛りが悪い軍隊が、勝てた試しはない。
軍関係者では昔から言われている言葉です。
いかに精強な部隊でも、補給線を絶たれ軍事的インフラが確保できない事態に陥ると、ただちに撤退を視野に入れた行動を取ります。
人員、武器弾薬、医療品、水食料のどれが欠けても戦闘の継続は不可能となるからです。
また補給線を奪取されるということは、敵が後ろに回り込み退路を絶たれた。と言う事を意味します。
物資の補給もなく、いつ後ろに回り込んだ敵に背中を刺されるか分からない状況で、目の前に展開している敵との戦闘など、誰も考えたくはないでしょう。
さらに言えば、後ろを遮断した敵を何とかしない限り増援の部隊すら望めないのです。
このような状況では兵達の士気など絶望的となります。
乏しい食料弾薬、焼けつくような喉の渇き、医療品の不足で放って置かれるだけの傷病兵・・・
いずれ脱走者までもが出始め、呆気なく戦線は崩壊します。
云わばいかに強大な敵でも補給線さえ絶ってしまえば、圧倒的に有利な立場で戦闘の主導権を握ることができるのです。
したがって現代の先進国の軍隊は、いずれも先進的なフィールドキッチンを保有して有事に備えているわけです。
全5軍、世界最大規模の軍事力を世界中に展開することが可能なアメリカ軍では、最前線の部隊でさえ3食のうち必ず1食は温かい食事が取れるように配給部隊を配置しているそうです。
いかに軍事行動と食事が密着したものなのか、お分かりかいただけたかと思います。
さて、のっけからキャンプとは関係無いような話をしてしまいましたが、キャンプそのものも、食事の良し悪しはダイレクトに跳ね返ってくる話です。
言うまでの話ではなく、誰でも「不味い飯は嫌だ」
これに尽きる訳です。
キャンプ飯の美味い不味いは、これからのキャンプと言う趣味を根本的に見直す結果にもなりかねないのです。
自分的には不味い飯など御免被るので、調味料と調理器具には気を遣っています。
特に調理器具はなるだけ妥協しません。
美味い飯にありつくためには必須な道具であり、調理後の洗い物まで考えて自分なりに納得したものを揃えています。
したがって今流行りの小型の調理器具や色々と重ねて収納するスタッキングとは縁のないモノばかりです。
少しばかり説明していきます。
自分が、調理食事に使う器具はここ何年か全く変わっていません。
基本的には、調理台に使っているスチールテーブル、これだけは最近新調しました。
その上に乗るコンロ、調理器具である飯盒、フライパン、1リッター鍋、ケトル、樹脂製の蓋付きカップ。
後は湯沸かしや簡単な調理に使っているガスコンロと五徳、何枚かの樹脂食器。
これらをメインとして使っています。
つまり自分のフィールドキッチンと言うわけです。
これだけで、何不自由なく様々なキャンプ飯を満喫しています。
ではどのような使い方をしているのか自己流ではありますがお話したいと思います。
先ずは炊飯に使っているのは昔ながらの飯盒です。
一時期流行りのメスティンを飯1合用の小さいサイズとその倍ほどの大きさのモノを二つ買いそろえて使ってみましたが、なんとも使いづらいですね。
ご飯の味は悪くはないのですが、焦げ付かないか確認のために何度か蓋を開けてかき回してみたり、火加減の調整にも気を使います。
構造的に浅い作りなので、炊飯中にボタボタと糊のようなお湯が滴り落ち、ガスコンロが汚れ焦げ付いてしまい、使えません。
食べ終わった後はメスティンの底にご飯がこびりついてしまうので、今度は洗い落とすのに一苦労です。
更に言えば、炊飯する以外にほとんど使用用途がありません。
小型のモノを半年ばかりキャンプや台所で使ってみましたが、満足行く結果が得られず結局お蔵入りです。
大きい方は一度も使わないまま小屋の中です。
やはり飯盒に戻ってしまいました。
特にドイツ式の飯盒を手に入れてからは、余りにも便利すぎて野外の炊飯はこれ一辺倒になりました。
日本式の飯盒に比べ中子が深く作られているので、ここで炊飯しながら
レトルトパックや缶詰も同時に加熱できます。
蓋も深い作りになっているので、炊飯が終わった後に蒸らしながら、スープを作ったり、フライパンの変わりに簡単な炒め物を作ったりもできるのです。
自分的には理想的な調理器具のひとつです。
早速もう1つ買い求めて自宅でも使っているくらいです。
自分の求めるモノは、小さいとか、中に収納できるとかではなく、
「いかに多用途な使い方が可能か」
これに尽きます。
自宅の台所とは違い、キャンプ場に持ち込める道具や食材など、たかが知れています。
そんな状況で美味い飯を作ろうと考えるなら、先ず料理の知識です。
手持ちの食材と調味料で何が出来るのか?
この知識が豊富な人ほど有利と言えます。
そしてそれを可能にする調理器具の存在が不可欠と自分は考えます。
つまりどれだけ多用途に応用が出来るか。が、道具選びの基本になっているわけです。
ちょと例を挙げてみましょう。
キャンプに欠かせない食材と言えば、真っ先に肉を挙げる人がほとんどではないでしょうか?
しかし毎食焼き肉ではさすがに直ぐ飽きてしまいますよね。
では、肉料理と言ったらどれだけ思い付くでしょうか?
簡単に焼くと言っても、ステーキなのか焼き肉なのかで大きく変わって来ます。
また網焼きか鉄板焼きか、煮て食べるにしても肉鍋にするかしゃぶしゃぶにするか、はたまた、すき焼きにするのか?
どれをとっても食材や調味料は大きく変わり、同時にそれに対応できる器具でないと料理はできません。
せっかくパックの焼き鳥を買ってきても、焼き網か焼き鳥スタンドに類するものが無ければ、焼き鳥は難しいと言うことになってしまいます。
こんな時、多用途に使える調理器具の便利さが、身に染みて理解できると思います。

いつも使っている食事用のギアたちです。
フライパンと言う調理器具を知らない人はこの国にはいないでしょう。
台所でもキャンプでも大活躍です。
今流行りの主流は、取っ手が外れるものや、鉄板の分厚いもの、またステーキに特化したような、小さな鉄板などですね。
自分も何か面白い調理器具がないかAmazon等で良く検索したりします。
しかし何年か前に某スーパーで見つけたフライパンを越えるものは今だ現れていません。
それは、25センチの丸形、両端に取っ手がついた至って平凡な形をしたフライパン、特にテフロン加工が施されている訳でもないただの鉄板です。
しかしそのパンには厚い鉄製の蓋が別売りで付属しているのでした。
こいつは使えるっ。
直感的にそう感じた自分は早速買い込んでキャンプに持ち込んでみました。
思った通り、中々便利です。
まず、当然の事ながら蓋があれば、埃が入りません。
風の強いときには落ち葉まで入り込む事があるので今までは目を離せませんでした。
次に、何と言っても虫の侵入が大きく減りました。
特に春先の寒いときなどプールに飛び込むかのように羽虫達が鍋やパンのなかに飛び込んでくるのでウンザリします。
一度など余りにもハエがいっぱい入っているので一鍋丸ごと麻婆豆腐を捨ててしまったことがあるくらいです。
そして最大の便利さはこの蓋が厚い事です。
一度グラタンやピザをつくってみましたが、成功です。
ホワイトソースの上に粉チーズをたっぷりと振りかけて蓋をし、その上に真っ赤な炭を乗せて15分ほど加熱します。
この時蓋が熱に弱いと変形してしまうので隙間が開いて上手く行きません。
しかしこの蓋はそんなこともなく、無事役割を果たしてくれました。
つまり簡易的ながらダッチオーブンでの調理も可能となったわけです。
当然保温にも優れ、何かを煮込むときにも活躍しています。

ケトル
コーヒー好きの自分には切っても切れない器具です。
当然有って当たり前の器具なのですが、適当な大きさのケトルと言うものが中々見つかりませんでした。
またケトル1つに4~5千円も出すつもりもなかったので、ずっと鍋で湯沸かしをしていたのですがこのキャンプブームで低価格のキャンプ用品が手に入るようになりました。
鍋、パン、ケトル、樹脂食器のセットに早速飛び付きました。
4千円程度の商品だったかと思いますが、実用上何の問題もなく今も当たり前に使っています。

スチールテーブル
以前は小型のアルミテーブルを使っていましたが、大きめの荷物が1品増えることを覚悟して購入しました。
結果としては大変便利なので良い買い物でした。
この上にコンロから食器に至るまで全てを乗せて調理が可能で、正にフィールドキッチンそのものです。
このテーブルも幾つかの競合する候補の中から耐荷重が高く、足がロックできてぐらつかない物を前提に選びました。
特に足がロックできないテーブルは野外で使うには危険が伴います。
傾斜地では倒れる危険性が高く、誤って蹴ったりしても同様です。
更に物が乗ったまま移動させるにもリスクが伴います。
自分的にはロック機構の付いたテーブルを強く推奨します。
デザイン、重量等よりも、安全性と耐久性を優先させることが、アウトドアギアの鉄則です。
マグカップ
色々と手にいれて、7~8個位は持っているでしょうか?
数年前に100円ショップで手に入れた樹脂製マグカップが今のところベストです。
何の変哲のないプラのマグカップですが、スチールの物に比べ、軽く断熱性に優れ、コーヒーもぬるくなりませんね。
しかも蓋付きなので、保温性と同時に虫やゴミの侵入も防いでくれる優れものです。
夏の夜、ランタンの灯りの下でも安心してバーボンを楽しむ事ができるようになりました。
五徳 スタンド
絶対に無くてはならない。と言うギアではありません。
ですがこれがあればガスコンロの使い方の幅が大きく広がります。
自分が使っているものは25センチ前後の大きさで、両の足に風防がついていて高さの調整も可能なモデルです。
小さなカセットガスコンロでもこれがあれば、同時に3つまでなら加熱が可能なので、非常に効率良く調理ができます。
また多少テーブルが傾いていたとしても、鍋やケトルが滑り落ちたことが無いので、安心して調理ができます。
風避けがついていれば熱効率も上がるので、燃料の節約にも繋がります。
この6種類を組み合わせる事で自分のフィールドキッチンが出来上がります。
今回のキャンプで作った食事は、焼き鳥、お茶漬け、麻婆豆腐、ピザ、青椒肉絲、ハンバーグ&ベーコン、ホタテバター焼き等・・・・
自宅よりも美味いご飯を食べているような気がします。

焼き肉!

酎ハイと焼き鳥です

魅惑のマグロ丼!!
ここ八戸の港にまた珍しい船が入港しています。
八戸は港がそれなりに大きいので、結構いろんな船が人知れず入っていたりもします。
海底探査船から始まり、様々な護衛艦、大型貨物船、そして豪華客船
に至るまで珍しい船が入ってきます。
しかし今回のお客様はデカイです。
サルベージ船のようですが、その大きさには驚きました。
これならゴジラでも吊り上げてしまいそうです。

6月を過ぎたあたりにいつの間にか消えてしまいました。
もしかしたら北海道の海難事故のために待機していたのかもしれませんね。
ではまた、
キャンプ、楽しんでいますか?
まだ寒い時期でしたが、毎年キャンプ初めはGWにとある湖畔の野営場に足を運んでいます。
春キャンプは人も少なく厄介な虫もいないので、過ごしやすいので すが、天候が不安定なのがネックですね。
ここには足掛け4日お世話になりましたが、今年は連日の雨と低温に悩まされるキャンプとなりました。
外気温が日中でも8度ほどで日が暮れると4度以下にまで低下します。
そしてあまり激しくは無いものの、シトシトと降り続く冷たい雨・・・
幸い風は弱かったのですが、それでも手足の先がギリギリと冷えてきます。
炭火に当たりながら晩飯の仕度をするのですが、こうも冷えると億劫になりがちです。
とは言うものの、コンビニ弁当ではせっかくの雰囲気がぶち壊しです。
そこで今回のお話は 「フィールドキッチン」 です。
皆さんには余り聞き覚えの無い言葉だと思います。
フィールドキッチンとは、軍隊で言う移動型の野外炊飯車あるいはそれに相当するモノをそのように呼称しています。
歴史は相当古く1800年頃にはヨーロッパでその原型が現れ、アメリカでは西武開拓時代には既にカウボーイや開拓者たちが使っていたようです。
(また寒くなってきました。ついさっきまで、9:30頃は22度だったものが今は12度です。山の天気とは本当に気紛れです。五月二日)
飯の盛りが悪い軍隊が、勝てた試しはない。
軍関係者では昔から言われている言葉です。
いかに精強な部隊でも、補給線を絶たれ軍事的インフラが確保できない事態に陥ると、ただちに撤退を視野に入れた行動を取ります。
人員、武器弾薬、医療品、水食料のどれが欠けても戦闘の継続は不可能となるからです。
また補給線を奪取されるということは、敵が後ろに回り込み退路を絶たれた。と言う事を意味します。
物資の補給もなく、いつ後ろに回り込んだ敵に背中を刺されるか分からない状況で、目の前に展開している敵との戦闘など、誰も考えたくはないでしょう。
さらに言えば、後ろを遮断した敵を何とかしない限り増援の部隊すら望めないのです。
このような状況では兵達の士気など絶望的となります。
乏しい食料弾薬、焼けつくような喉の渇き、医療品の不足で放って置かれるだけの傷病兵・・・
いずれ脱走者までもが出始め、呆気なく戦線は崩壊します。
云わばいかに強大な敵でも補給線さえ絶ってしまえば、圧倒的に有利な立場で戦闘の主導権を握ることができるのです。
したがって現代の先進国の軍隊は、いずれも先進的なフィールドキッチンを保有して有事に備えているわけです。
全5軍、世界最大規模の軍事力を世界中に展開することが可能なアメリカ軍では、最前線の部隊でさえ3食のうち必ず1食は温かい食事が取れるように配給部隊を配置しているそうです。
いかに軍事行動と食事が密着したものなのか、お分かりかいただけたかと思います。
さて、のっけからキャンプとは関係無いような話をしてしまいましたが、キャンプそのものも、食事の良し悪しはダイレクトに跳ね返ってくる話です。
言うまでの話ではなく、誰でも「不味い飯は嫌だ」
これに尽きる訳です。
キャンプ飯の美味い不味いは、これからのキャンプと言う趣味を根本的に見直す結果にもなりかねないのです。
自分的には不味い飯など御免被るので、調味料と調理器具には気を遣っています。
特に調理器具はなるだけ妥協しません。
美味い飯にありつくためには必須な道具であり、調理後の洗い物まで考えて自分なりに納得したものを揃えています。
したがって今流行りの小型の調理器具や色々と重ねて収納するスタッキングとは縁のないモノばかりです。
少しばかり説明していきます。
自分が、調理食事に使う器具はここ何年か全く変わっていません。
基本的には、調理台に使っているスチールテーブル、これだけは最近新調しました。
その上に乗るコンロ、調理器具である飯盒、フライパン、1リッター鍋、ケトル、樹脂製の蓋付きカップ。
後は湯沸かしや簡単な調理に使っているガスコンロと五徳、何枚かの樹脂食器。
これらをメインとして使っています。
つまり自分のフィールドキッチンと言うわけです。
これだけで、何不自由なく様々なキャンプ飯を満喫しています。
ではどのような使い方をしているのか自己流ではありますがお話したいと思います。
先ずは炊飯に使っているのは昔ながらの飯盒です。
一時期流行りのメスティンを飯1合用の小さいサイズとその倍ほどの大きさのモノを二つ買いそろえて使ってみましたが、なんとも使いづらいですね。
ご飯の味は悪くはないのですが、焦げ付かないか確認のために何度か蓋を開けてかき回してみたり、火加減の調整にも気を使います。
構造的に浅い作りなので、炊飯中にボタボタと糊のようなお湯が滴り落ち、ガスコンロが汚れ焦げ付いてしまい、使えません。
食べ終わった後はメスティンの底にご飯がこびりついてしまうので、今度は洗い落とすのに一苦労です。
更に言えば、炊飯する以外にほとんど使用用途がありません。
小型のモノを半年ばかりキャンプや台所で使ってみましたが、満足行く結果が得られず結局お蔵入りです。
大きい方は一度も使わないまま小屋の中です。
やはり飯盒に戻ってしまいました。
特にドイツ式の飯盒を手に入れてからは、余りにも便利すぎて野外の炊飯はこれ一辺倒になりました。
日本式の飯盒に比べ中子が深く作られているので、ここで炊飯しながら
レトルトパックや缶詰も同時に加熱できます。
蓋も深い作りになっているので、炊飯が終わった後に蒸らしながら、スープを作ったり、フライパンの変わりに簡単な炒め物を作ったりもできるのです。
自分的には理想的な調理器具のひとつです。
早速もう1つ買い求めて自宅でも使っているくらいです。
自分の求めるモノは、小さいとか、中に収納できるとかではなく、
「いかに多用途な使い方が可能か」
これに尽きます。
自宅の台所とは違い、キャンプ場に持ち込める道具や食材など、たかが知れています。
そんな状況で美味い飯を作ろうと考えるなら、先ず料理の知識です。
手持ちの食材と調味料で何が出来るのか?
この知識が豊富な人ほど有利と言えます。
そしてそれを可能にする調理器具の存在が不可欠と自分は考えます。
つまりどれだけ多用途に応用が出来るか。が、道具選びの基本になっているわけです。
ちょと例を挙げてみましょう。
キャンプに欠かせない食材と言えば、真っ先に肉を挙げる人がほとんどではないでしょうか?
しかし毎食焼き肉ではさすがに直ぐ飽きてしまいますよね。
では、肉料理と言ったらどれだけ思い付くでしょうか?
簡単に焼くと言っても、ステーキなのか焼き肉なのかで大きく変わって来ます。
また網焼きか鉄板焼きか、煮て食べるにしても肉鍋にするかしゃぶしゃぶにするか、はたまた、すき焼きにするのか?
どれをとっても食材や調味料は大きく変わり、同時にそれに対応できる器具でないと料理はできません。
せっかくパックの焼き鳥を買ってきても、焼き網か焼き鳥スタンドに類するものが無ければ、焼き鳥は難しいと言うことになってしまいます。
こんな時、多用途に使える調理器具の便利さが、身に染みて理解できると思います。
いつも使っている食事用のギアたちです。
フライパンと言う調理器具を知らない人はこの国にはいないでしょう。
台所でもキャンプでも大活躍です。
今流行りの主流は、取っ手が外れるものや、鉄板の分厚いもの、またステーキに特化したような、小さな鉄板などですね。
自分も何か面白い調理器具がないかAmazon等で良く検索したりします。
しかし何年か前に某スーパーで見つけたフライパンを越えるものは今だ現れていません。
それは、25センチの丸形、両端に取っ手がついた至って平凡な形をしたフライパン、特にテフロン加工が施されている訳でもないただの鉄板です。
しかしそのパンには厚い鉄製の蓋が別売りで付属しているのでした。
こいつは使えるっ。
直感的にそう感じた自分は早速買い込んでキャンプに持ち込んでみました。
思った通り、中々便利です。
まず、当然の事ながら蓋があれば、埃が入りません。
風の強いときには落ち葉まで入り込む事があるので今までは目を離せませんでした。
次に、何と言っても虫の侵入が大きく減りました。
特に春先の寒いときなどプールに飛び込むかのように羽虫達が鍋やパンのなかに飛び込んでくるのでウンザリします。
一度など余りにもハエがいっぱい入っているので一鍋丸ごと麻婆豆腐を捨ててしまったことがあるくらいです。
そして最大の便利さはこの蓋が厚い事です。
一度グラタンやピザをつくってみましたが、成功です。
ホワイトソースの上に粉チーズをたっぷりと振りかけて蓋をし、その上に真っ赤な炭を乗せて15分ほど加熱します。
この時蓋が熱に弱いと変形してしまうので隙間が開いて上手く行きません。
しかしこの蓋はそんなこともなく、無事役割を果たしてくれました。
つまり簡易的ながらダッチオーブンでの調理も可能となったわけです。
当然保温にも優れ、何かを煮込むときにも活躍しています。
ケトル
コーヒー好きの自分には切っても切れない器具です。
当然有って当たり前の器具なのですが、適当な大きさのケトルと言うものが中々見つかりませんでした。
またケトル1つに4~5千円も出すつもりもなかったので、ずっと鍋で湯沸かしをしていたのですがこのキャンプブームで低価格のキャンプ用品が手に入るようになりました。
鍋、パン、ケトル、樹脂食器のセットに早速飛び付きました。
4千円程度の商品だったかと思いますが、実用上何の問題もなく今も当たり前に使っています。
スチールテーブル
以前は小型のアルミテーブルを使っていましたが、大きめの荷物が1品増えることを覚悟して購入しました。
結果としては大変便利なので良い買い物でした。
この上にコンロから食器に至るまで全てを乗せて調理が可能で、正にフィールドキッチンそのものです。
このテーブルも幾つかの競合する候補の中から耐荷重が高く、足がロックできてぐらつかない物を前提に選びました。
特に足がロックできないテーブルは野外で使うには危険が伴います。
傾斜地では倒れる危険性が高く、誤って蹴ったりしても同様です。
更に物が乗ったまま移動させるにもリスクが伴います。
自分的にはロック機構の付いたテーブルを強く推奨します。
デザイン、重量等よりも、安全性と耐久性を優先させることが、アウトドアギアの鉄則です。
マグカップ
色々と手にいれて、7~8個位は持っているでしょうか?
数年前に100円ショップで手に入れた樹脂製マグカップが今のところベストです。
何の変哲のないプラのマグカップですが、スチールの物に比べ、軽く断熱性に優れ、コーヒーもぬるくなりませんね。
しかも蓋付きなので、保温性と同時に虫やゴミの侵入も防いでくれる優れものです。
夏の夜、ランタンの灯りの下でも安心してバーボンを楽しむ事ができるようになりました。
五徳 スタンド
絶対に無くてはならない。と言うギアではありません。
ですがこれがあればガスコンロの使い方の幅が大きく広がります。
自分が使っているものは25センチ前後の大きさで、両の足に風防がついていて高さの調整も可能なモデルです。
小さなカセットガスコンロでもこれがあれば、同時に3つまでなら加熱が可能なので、非常に効率良く調理ができます。
また多少テーブルが傾いていたとしても、鍋やケトルが滑り落ちたことが無いので、安心して調理ができます。
風避けがついていれば熱効率も上がるので、燃料の節約にも繋がります。
この6種類を組み合わせる事で自分のフィールドキッチンが出来上がります。
今回のキャンプで作った食事は、焼き鳥、お茶漬け、麻婆豆腐、ピザ、青椒肉絲、ハンバーグ&ベーコン、ホタテバター焼き等・・・・
自宅よりも美味いご飯を食べているような気がします。
焼き肉!
酎ハイと焼き鳥です
魅惑のマグロ丼!!
ここ八戸の港にまた珍しい船が入港しています。
八戸は港がそれなりに大きいので、結構いろんな船が人知れず入っていたりもします。
海底探査船から始まり、様々な護衛艦、大型貨物船、そして豪華客船
に至るまで珍しい船が入ってきます。
しかし今回のお客様はデカイです。
サルベージ船のようですが、その大きさには驚きました。
これならゴジラでも吊り上げてしまいそうです。
6月を過ぎたあたりにいつの間にか消えてしまいました。
もしかしたら北海道の海難事故のために待機していたのかもしれませんね。
ではまた、
2021年12月28日
キャンプ場の灯り
こんにちは、MASADA556です。
紅葉の時期も終わり、足早に秋から冬に季節が移り変わってしまいました。
11月いっぱいでほとんどのキャンプ場、野営場は閉鎖され、冬支度に入ります。
場所によっては5メートル以上も雪が降り積もる東北では、峠道や山道の多くは通行止めとなり、ごく一部のキャンプ場を除いて5月頃までお休みです。

かねてから噂に聞いていた野営場の場所をようやく探し出し下見に来たところです。
素晴らしい景観の野営場ですが、炊事場に熊の気配が色濃く残されています。


ここでのキャンプはそれなりの覚悟が必要なようです。
逆に冬季のみ営業というキャンプ場もあります。
メートル単位で降り積もる風雪の中、全てが凍り付くマイナス環境をモノともせず楽しめる、装備と経験を持ち合わせた方々だけが入って行ける世界です。
自分のような軟弱者には到底無理な世界なのです。
その代わり、今度は車中泊をメインとしたアウトドア生活が始まります。
自分的には冬の方が車中泊がやり易くて楽に感じます。
まあ、今時エアコンも無いような車に乗っているので、夏の熱地獄よりは冬の寒さの方が対応しやすいという理由です。
但し、真冬の夜は車内温度はマイナスになるので、しっかりした防寒対策が必要で、不十分な装備では凍死の危険を感じるほどです。
車両にも対策が必要です。
スタッドレスタイヤの装着は当たり前として、スタック対策の装備類も準備するべきでしょう。
最近は法的に装備が義務化されつつあるタイヤチェーン等も準備しておけば、深雪に見舞われた時や、雪道に不馴れなドライバーたちは心強い事でしょう。
ただ、タイヤチェーンはあれば良いと言う訳ではなく、取り付け方に少しばかりコツが必要なので、事前に十分な練習が必要です。
特に関東圏にお住まいの方は、準備を怠らないことです。
例えばタイヤチェーンを準備した。
取り付けかたも練習した。
これでOK、大丈夫。
ではないのです。
良くその時の状況を考えて見ることが必要です。
悪天候による降雪が原因でのチェーン規制となる訳ですから、まずどのタイミングでチェーンを装着するかです。
○○峠積雪によるチェーン規制という表示看板が出ていたとします。
そうなるとどの程度の積雪でチェーンを装着するのか、ちょっと悩むかと思います。
路面が乾いているのに早々と着けてしまいますと、外れてしまったり、最悪チェーンが切れてしまいます。
かといってギリギリのタイミングまで粘ったりするとパーキングスペースに車が満杯状態となり、順番待ちの長い列に並ぶ羽目にもなりかねません。
その間にも雪はどんどん積もっていくので停止状態から登りに向けてのスタートが困難になり、最悪遭難状態に陥ります。
無理に路肩で作業を始めたりすると、今度は渋滞の原因になったり、下手をすると大型車両に車を持っていかれることになります。
無事にパーキングに入ってチェーンを取り付けるとしても、しっかりした防寒着と雨具に長靴、防寒防水の手袋が必須です。
これらが無くては、とても荒天時に野外作業などできません。
例えば、手を剥き出しのまま濡れたチェーンなどいじっていれば、5分もしないうちに冷えきって動かなくなります。
これは冗談話ではありませんよ。

いつ、何処で撮ったか忘れてしまいましたが、強烈な横殴りな風雪にウンザリして道の駅に逃げ込んで、そのまま一泊した時の一枚です。
もうひとつ注意が必要なことがあります。
最近のスタッドレスタイヤは性能がいいので、そこそこの積雪でも登って行けるかも知れません。
面倒だしなんとか走っているから大丈夫だ。
そんな考えで峠道を走っているとやがて目の前に余り考えたくない光景が広がります。
そうです、道というのは登ったらいずれ降ることになっているのです。
降りの雪道は登りの何倍も運転が難しいと言うことを、己の身をもって知る良い機会となるでしょう。
ちょっと大袈裟に思えるかも知れませんが、東北の真冬を甘く見ないことです。
ここ青森県で、過去に立ち往生した車の中で死亡した例が幾つもあるのです。
以上は東北の冬を余り体験したことの無い方向けの話です。
さて、ここからは私個人の意見です。
自分は東北生まれの東北育ちで、青森、岩手、秋田の3県はしょっちゅう走り回っているドライブコースのようなものです。
キャンプや車中泊、名所巡りで夏冬関係なく走っているわけですが、真冬のドライブでタイヤチェーンなどという物を装着して走っている車を見たことがありません。
大型車やタクシー、救急車などの緊急車両がつけているのをたまに見かけるくらいで、どれだけ雪が降ろうが路面が凍結しようが、一般車がチェーンをつけて走るなどということはまずあり得ません。
自分もつけて雪道を走った経験はありません。
と言うか、そもそも持っていません。
大昔に友人の車に取り付けを手伝った程度ですので、取り付けかたも覚えていないのです。
それでも雪道を当たり前に走ってきました。
そもそも殆んどの東北人が、チェーンなど持ってません。
ワンシーズン東北の冬道を体験してもらえれば容易に理解してもらえるのですが、一口に冬道と言っても路面の状況は様々です。
完全に乾燥したドライな路面から、降り始めの新雪、踏み硬められた圧雪状態、圧雪の上面が凍り付く半凍結状態、溶けた雪が際凍結したアイスバーン、固く凍結した圧雪にタイヤが溝を掘ってしまった轍道、一晩で数メートルも積もる深雪、その雪が溶けかかったり、みぞれが大量にふると路面はシャーベット状態になります。
最悪なのは一見ウェット路面に見える凍結路面でミラーバーンと言われる現象です。
一見水なのか凍っているのかまったく分からないため、通勤時に事故が多発します。
東北の冬道というのはこれらの路面状況が数十メートル、数百メートル、数キロメートル毎に次々と現れ、又は混ざり合って現れるのです。
そのような状況下で一々チェーンを着けたり外したりなど、誰も考えない訳です。
またスタックするよりも走行中に車のコントロールを失う方が遥かに危険です。
チェーンを装着することで全く変わってしまう運転特性に、山道の下りなどで対応できなくなるほうが、自分的には怖く感じます。
最近の車関係の冬記事を読んでいると、チェーンは冬のドライブに必須だ。みたいに書かれている記事を見かける事が多くなりました。
自分の経験から鑑みるに、余り雪国事情をご存じないライターが書いた啓発記事程度の認識で斜め読みしています。
法律的に携帯装着が義務化されている地域では携行しなければならないのでしょうが、ここ東北三県ではそのような法もありません。
自分の経験から少しばかり言わせて戴ければ、東北の冬道にもっとも有効なのは、車高が高めの4輪駆動車です。
今で言うSUVがそれにあたるのでしょうか。
一般道を走っている時4輪駆動が一番能力を発揮するのは、静止状態からのスタート時です。
路面が凍結している時など、2駆の車ではタイヤが空転してしまい、ほんの数センチの段差すら越えられないなんてことも当たり前にあります。
4輪にトラクションがかかる車なら、そのような心配も殆んどありません。
一旦走り出してしまえば、4駆も2駆もそんな変わりはありません。
急ハンドル、急ブレーキなどの急のつく操作をせず、余裕のある車間距離を取って運転すれば問題ありません。
凍結路で一番むずかしいのは減速する時と止まるときです。
スリップ事故の殆んどがこの減速時に発生します。
減速時にも4輪駆動車は威力を発揮します。
まずアクセルからゆっくり足を放してください。
この状態で、4輪全体にエンジンブレーキがかかりますので、車両の姿勢を崩すことなく減速が可能です。
後はロックしないようにジワリとブレーキを踏み、速度を落としていきます。
また東北の冬で注意するべきは路面状況だけではありません。
気象の変化による道路状況も考えなくてはならないことも良くあります。
例えば「地吹雪」と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは雪国特有の現象で、横殴りの風雪が酷い時に良く見られます。
濃い霧の中を走っているようなもので、濃密な雪のカーテンに視界を阻まれ、前走車のテールランプすら見えなくなります。
多重の追突事故や、道路からの逸脱などが多発する、非常に危険な道路状況になります。
逆に晴れているからといって安心できるわけではありません。
積雪の多い道路を晴れた日に走っていると、雪で反射した強い紫外線を受けて目が焼けます。
「雪目」と言われる症状で、目に強い光線を浴び続けると網膜が焼け、その晩に疼くような痛みと、大量の涙に悩まされる事になります。
路面状況にも注意が必要です。
日が陰っている路面は固く締まっているのですが、日当たりのいい路面は溶けてツルツルのスケートリンク状態になっているので、殆んどブレーキが効きません。
このような神経を使う路面状況が交互に現れる事になります。
また、たまに見かける道路の上に落ちているの雪の固まりですが、絶対に避けてください。
あれは雪ではなく、大型の下回りに張り付いていた固い氷の固まりです。
安易に踏みつけると車体下回りや足回りを壊してしまうことになりかねません。
要注意の落下物です。
他にも色々な注意点はあるのですが、挙げ続けるとキリがありませんのでこの辺りで本題に入ります。
今回はキャンプ場の灯りです。
自分はこのキャンプ場で使う照明器具についてはうるさい方です。
色々と試してみたり、他のキャンパーさんの道具を見たり意見を聞いてみたりと、そこそこ試行錯誤も試してみました。
また最近になって進歩が著しいLEDライトなども10個以上買い込んでキャンプ場で試してみたりもしてます。
少し前のLEDライトなど暗くてとてもメインに使える物ではなく、自分のサイトの位置を知らせる常夜灯程度の性能しかありませんでした。
しかし、ここ数年で一気に進化したのには驚きです。
自分も4千円くらいのモノを手にいれてみましたが、圧倒的に明るく、しかも光度の調整や灯りの種類も選べるうえに、温度計と時計までついていて、他のモバイル器機に充電までが可能なのです。
少しばかり重いのが難点ですが、バッテリー寿命も相当長く、三日間程度のキャンプでは1/3も電気を消費しませんでした。
もう一つ手にいれれば他の照明器具は恐らく必要なくなるでしょう。
あとは、ソーラー発電パネルを手にいれれば、天候が良好な時はほぼ無限に夜の灯りを手にいれることができます。

最近手に入れたLEDランタンです。
非常に使い勝手が良いので、夜間の作業時に活躍しています。
ここまでは良いことずくめです。
しかし、考えてみてください。
自分は自然の中に文明の便利さを持ち込むためにキャンプしている訳ではありません。
大好きな自然環境の中での落ち着いたひとときをすごしたいがためのキャンプです。
必要な時以外はできるだけ人工的な光は入れたくないのです。
今まで何度かガソリンランタンやガスランタンを手に入れようか考えた事はありました。
ガソリンランタンの点火前の儀式的な作法やガスランタンの手軽さはどちらも魅力的で、量販店のアウトドアコーナーで、何度か手にとって考え込んだものです。
そんなことが10年程も続き、結局手に入れぬまま今に至っています。
理由は当時のランタンでは、まずホワイトガソリンが高価で専門店でなければ手に入らないこと、ガスも同じような理由です。
しかし時代と共にランタンも進化し、赤ガスばかりか様々な燃料を使用できる、マルチヒューエルのランタンやコンロが出回り出し、ガスタイプも安価なカセットガス使用の物が大半を占めています。
手に入れない理由は無くなりました。
しかし令和のこの時代、メインに使っているのは、やはり古ぼけた灯油ランタンなのです。
現在所有している灯油ランタンは、大、中、小、の3つです。
最初に手に入れた大タイプのランタンは20年以上もキャンプのお供をしてくれました。
どこもモノともわからぬまま量販店で見かけたときに買い求めたものですが、特にどこかが壊れるということもなく、最近まで使っていました。
ただ作りがあまり良くなかったようで、芯をどのようにカットしても煤が出て、一晩でホヤが真っ黒になります。
最初は灯油ランタンなんてこんなものだろうぬと気にせずにいたのですが、後に手に入れた物は比較的綺麗に燃えてくれるので、テントの中に持ち込んでも煤に悩まされる事はなくなりました。

外気の余りの冷たさにテントに逃げ込んできた時の一枚です。
ヒーターばかりかランタンまで総動員して暖を取っています。
まあ、外で使う事がメインなので、余り気にしてはいなかったのですが、最近メンテナンス中に芯を押し上げるパーツについているパッキングが劣化して割れてしまいました。
今さら交換パーツが手に入るわけもなく、なんとか使えないこともなかったのですが、風の強い時や万が一落としてしまった時の危険性を考えて、引退してもらう事にしました。
今は小屋の奥で静かに余生を送っております。
特に灯油ランタンに何かこだわりがある訳ではないのですが、あの優しい感じがする独特な光に包まれて過ごす夜は、自分にとって欠かせないモノとなっているようです。
以前、物は試しとLEDライトだけで夜を過ごそうとしたときがありました。
最初は室内にいるのとさして変わらない明るさに驚き、技術力の進歩に感謝し、いつものように晩飯を食べてからタープ下のビーチベットに横になって一杯やりながら本を読んでいたのですが、何かこう違和感のようなものを感じ始めました。
・・・・?
何かわからぬまま、夜は更け、トイレに行き、戻るときに原因がわかりました。
余りにもハッキリとサイトの様子が見えすぎるのです。
サイトに近づくにつれ、LEDライトのギラつく光が全てを照らしていて車のヘッドライトでも当てられているように映し出されています。
まるで自宅にいるようではないか・・・
違和感の原因はこれでした。
自分は自然の中に包まれたくてここに来ているのです。
そこにワザワザ便利さを求めてどうするのだ・・・
便利さを追求し、様々な機器を集めて作られたのが家であり、街であり都市であれば、その真逆を求めたのが本来のキャンプの姿です。
都市生活という、自分には不自然に感じる環境につかれた心身をリセットしたくて、人気の無い野営場などを選んでキャンプしているのに、何で逆を求める・・・?
サイトに戻り、いつもの灯油ランタンを2つ車から下ろし、ホヤを磨き、芯をハサミでカットします。
だいたいこんなもんだろ。
目分量で灯油を補充し、灯りをともします。
タープを支えている2本のポールにランタンを吊り下げ、LEDライトを全て取り払いました。

先程とは段違いの暗さです。
しばらくすると目が暗さに馴れて、タープ下での作業に支障が無くなります。
コンロに炭を足し、ケトルに水を入れ、コーヒーの準備に取りかかります。
炭火の火加減を確認、網の上にケトルを乗せ、立ち上がったついでにタープの外で身体を伸ばし、顔を上に向けるとさっきまでは見えなかった、満天の星空に気がつきます。
手を伸ばせば届きそう。とは正にこの事で、天の川の輝きまでが手に取るように確認できます。
10メートル程歩き、眼前に広がる湖面に目をやれば、半分に欠けた月が鏡のように澄んだ湖面に映し出され、その向こうには山々の稜線が湖をグルリと囲んでいます。
時おり心地よい風が吹き抜け、木々を揺らします。
胸一杯に深呼吸すれば、人工的な何かの匂いが排除された、本当の空気の匂いというものを感じます。
後ろに視界を戻せば、オレンジ色のどこか懐かしい灯りの中で、ケトルが湯気をたてています。

人工的な光の中では人工的な物しか見えなくなります。
そして自然の灯りの中では、自然のモノたちが見えるようになります。
これは経験してみなければ分からない事です。

太古の昔、初期の人類たちが手にして以来、火が作り出すオレンジ色の灯りは、以降電球が発明されるまで何千年もの間人類に夜の闇を照らす灯りを提供してくれました。
この火を操る術を最初の人類が学ぶ事がなければ、現在の地球文明は成り立たなかったでしょう。
暗闇の恐怖を退け、暖を取り、肉を調理するこを覚え、水を沸騰させ肉や木の実、草の類いを合わせて煮込む事で料理が始まりました。
やがては鉄を土や砂から取り出す事を覚え、このとてつもなく固い物質を加工する技術すら産み出していくのです。
恐らく、現代人にもこの記憶が遺伝子レベルで刷り込まれているはずです。
この記憶が色濃く残っている者は自然の中にあるべき何かを求め、古代の記憶を失ってしまった者たちは、逆に現代科学が作り出す文明に適応し、大都市を構成する素子として、更に文明を進化させていくでしょう。
もしかしたら、灯油ランタンの灯りをどのように感じるか?
が、ソロキャンパーとしての資質を見分ける、1つの目安なのかもしれません。
早いもので2021年もあと数日で終わりを告げます。
今年のキャンプはちょっと不完全燃焼気味で終わってしまいました。
前半は連休と悪天候が重なり、中盤は体調不良に悩まされ、後半は仕事とのバッティングに悩まされました。
特に連休に必ず天候が崩れ、しまいには台風まで連続でぶつかって来たときには、台風なんぞ気化爆弾で吹き飛ばすべきだ!!
天に向かって○指を突き立てたものです。
来年こそは悪天候と連休が重なると言う、何かの呪いじみた現象は終わりにして欲しいものです。
外には静かに雪が降り積もっています。
めったに雪が積もったりしない、ここ八戸では珍しい天候です。
各地でも積雪による混乱が生じているようです。
これからの年末年始、車や電車の移動には十分注意してください。
皆様、良いお年をお迎えください。
では、また。
紅葉の時期も終わり、足早に秋から冬に季節が移り変わってしまいました。
11月いっぱいでほとんどのキャンプ場、野営場は閉鎖され、冬支度に入ります。
場所によっては5メートル以上も雪が降り積もる東北では、峠道や山道の多くは通行止めとなり、ごく一部のキャンプ場を除いて5月頃までお休みです。
かねてから噂に聞いていた野営場の場所をようやく探し出し下見に来たところです。
素晴らしい景観の野営場ですが、炊事場に熊の気配が色濃く残されています。
ここでのキャンプはそれなりの覚悟が必要なようです。
逆に冬季のみ営業というキャンプ場もあります。
メートル単位で降り積もる風雪の中、全てが凍り付くマイナス環境をモノともせず楽しめる、装備と経験を持ち合わせた方々だけが入って行ける世界です。
自分のような軟弱者には到底無理な世界なのです。
その代わり、今度は車中泊をメインとしたアウトドア生活が始まります。
自分的には冬の方が車中泊がやり易くて楽に感じます。
まあ、今時エアコンも無いような車に乗っているので、夏の熱地獄よりは冬の寒さの方が対応しやすいという理由です。
但し、真冬の夜は車内温度はマイナスになるので、しっかりした防寒対策が必要で、不十分な装備では凍死の危険を感じるほどです。
車両にも対策が必要です。
スタッドレスタイヤの装着は当たり前として、スタック対策の装備類も準備するべきでしょう。
最近は法的に装備が義務化されつつあるタイヤチェーン等も準備しておけば、深雪に見舞われた時や、雪道に不馴れなドライバーたちは心強い事でしょう。
ただ、タイヤチェーンはあれば良いと言う訳ではなく、取り付け方に少しばかりコツが必要なので、事前に十分な練習が必要です。
特に関東圏にお住まいの方は、準備を怠らないことです。
例えばタイヤチェーンを準備した。
取り付けかたも練習した。
これでOK、大丈夫。
ではないのです。
良くその時の状況を考えて見ることが必要です。
悪天候による降雪が原因でのチェーン規制となる訳ですから、まずどのタイミングでチェーンを装着するかです。
○○峠積雪によるチェーン規制という表示看板が出ていたとします。
そうなるとどの程度の積雪でチェーンを装着するのか、ちょっと悩むかと思います。
路面が乾いているのに早々と着けてしまいますと、外れてしまったり、最悪チェーンが切れてしまいます。
かといってギリギリのタイミングまで粘ったりするとパーキングスペースに車が満杯状態となり、順番待ちの長い列に並ぶ羽目にもなりかねません。
その間にも雪はどんどん積もっていくので停止状態から登りに向けてのスタートが困難になり、最悪遭難状態に陥ります。
無理に路肩で作業を始めたりすると、今度は渋滞の原因になったり、下手をすると大型車両に車を持っていかれることになります。
無事にパーキングに入ってチェーンを取り付けるとしても、しっかりした防寒着と雨具に長靴、防寒防水の手袋が必須です。
これらが無くては、とても荒天時に野外作業などできません。
例えば、手を剥き出しのまま濡れたチェーンなどいじっていれば、5分もしないうちに冷えきって動かなくなります。
これは冗談話ではありませんよ。
いつ、何処で撮ったか忘れてしまいましたが、強烈な横殴りな風雪にウンザリして道の駅に逃げ込んで、そのまま一泊した時の一枚です。
もうひとつ注意が必要なことがあります。
最近のスタッドレスタイヤは性能がいいので、そこそこの積雪でも登って行けるかも知れません。
面倒だしなんとか走っているから大丈夫だ。
そんな考えで峠道を走っているとやがて目の前に余り考えたくない光景が広がります。
そうです、道というのは登ったらいずれ降ることになっているのです。
降りの雪道は登りの何倍も運転が難しいと言うことを、己の身をもって知る良い機会となるでしょう。
ちょっと大袈裟に思えるかも知れませんが、東北の真冬を甘く見ないことです。
ここ青森県で、過去に立ち往生した車の中で死亡した例が幾つもあるのです。
以上は東北の冬を余り体験したことの無い方向けの話です。
さて、ここからは私個人の意見です。
自分は東北生まれの東北育ちで、青森、岩手、秋田の3県はしょっちゅう走り回っているドライブコースのようなものです。
キャンプや車中泊、名所巡りで夏冬関係なく走っているわけですが、真冬のドライブでタイヤチェーンなどという物を装着して走っている車を見たことがありません。
大型車やタクシー、救急車などの緊急車両がつけているのをたまに見かけるくらいで、どれだけ雪が降ろうが路面が凍結しようが、一般車がチェーンをつけて走るなどということはまずあり得ません。
自分もつけて雪道を走った経験はありません。
と言うか、そもそも持っていません。
大昔に友人の車に取り付けを手伝った程度ですので、取り付けかたも覚えていないのです。
それでも雪道を当たり前に走ってきました。
そもそも殆んどの東北人が、チェーンなど持ってません。
ワンシーズン東北の冬道を体験してもらえれば容易に理解してもらえるのですが、一口に冬道と言っても路面の状況は様々です。
完全に乾燥したドライな路面から、降り始めの新雪、踏み硬められた圧雪状態、圧雪の上面が凍り付く半凍結状態、溶けた雪が際凍結したアイスバーン、固く凍結した圧雪にタイヤが溝を掘ってしまった轍道、一晩で数メートルも積もる深雪、その雪が溶けかかったり、みぞれが大量にふると路面はシャーベット状態になります。
最悪なのは一見ウェット路面に見える凍結路面でミラーバーンと言われる現象です。
一見水なのか凍っているのかまったく分からないため、通勤時に事故が多発します。
東北の冬道というのはこれらの路面状況が数十メートル、数百メートル、数キロメートル毎に次々と現れ、又は混ざり合って現れるのです。
そのような状況下で一々チェーンを着けたり外したりなど、誰も考えない訳です。
またスタックするよりも走行中に車のコントロールを失う方が遥かに危険です。
チェーンを装着することで全く変わってしまう運転特性に、山道の下りなどで対応できなくなるほうが、自分的には怖く感じます。
最近の車関係の冬記事を読んでいると、チェーンは冬のドライブに必須だ。みたいに書かれている記事を見かける事が多くなりました。
自分の経験から鑑みるに、余り雪国事情をご存じないライターが書いた啓発記事程度の認識で斜め読みしています。
法律的に携帯装着が義務化されている地域では携行しなければならないのでしょうが、ここ東北三県ではそのような法もありません。
自分の経験から少しばかり言わせて戴ければ、東北の冬道にもっとも有効なのは、車高が高めの4輪駆動車です。
今で言うSUVがそれにあたるのでしょうか。
一般道を走っている時4輪駆動が一番能力を発揮するのは、静止状態からのスタート時です。
路面が凍結している時など、2駆の車ではタイヤが空転してしまい、ほんの数センチの段差すら越えられないなんてことも当たり前にあります。
4輪にトラクションがかかる車なら、そのような心配も殆んどありません。
一旦走り出してしまえば、4駆も2駆もそんな変わりはありません。
急ハンドル、急ブレーキなどの急のつく操作をせず、余裕のある車間距離を取って運転すれば問題ありません。
凍結路で一番むずかしいのは減速する時と止まるときです。
スリップ事故の殆んどがこの減速時に発生します。
減速時にも4輪駆動車は威力を発揮します。
まずアクセルからゆっくり足を放してください。
この状態で、4輪全体にエンジンブレーキがかかりますので、車両の姿勢を崩すことなく減速が可能です。
後はロックしないようにジワリとブレーキを踏み、速度を落としていきます。
また東北の冬で注意するべきは路面状況だけではありません。
気象の変化による道路状況も考えなくてはならないことも良くあります。
例えば「地吹雪」と言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは雪国特有の現象で、横殴りの風雪が酷い時に良く見られます。
濃い霧の中を走っているようなもので、濃密な雪のカーテンに視界を阻まれ、前走車のテールランプすら見えなくなります。
多重の追突事故や、道路からの逸脱などが多発する、非常に危険な道路状況になります。
逆に晴れているからといって安心できるわけではありません。
積雪の多い道路を晴れた日に走っていると、雪で反射した強い紫外線を受けて目が焼けます。
「雪目」と言われる症状で、目に強い光線を浴び続けると網膜が焼け、その晩に疼くような痛みと、大量の涙に悩まされる事になります。
路面状況にも注意が必要です。
日が陰っている路面は固く締まっているのですが、日当たりのいい路面は溶けてツルツルのスケートリンク状態になっているので、殆んどブレーキが効きません。
このような神経を使う路面状況が交互に現れる事になります。
また、たまに見かける道路の上に落ちているの雪の固まりですが、絶対に避けてください。
あれは雪ではなく、大型の下回りに張り付いていた固い氷の固まりです。
安易に踏みつけると車体下回りや足回りを壊してしまうことになりかねません。
要注意の落下物です。
他にも色々な注意点はあるのですが、挙げ続けるとキリがありませんのでこの辺りで本題に入ります。
今回はキャンプ場の灯りです。
自分はこのキャンプ場で使う照明器具についてはうるさい方です。
色々と試してみたり、他のキャンパーさんの道具を見たり意見を聞いてみたりと、そこそこ試行錯誤も試してみました。
また最近になって進歩が著しいLEDライトなども10個以上買い込んでキャンプ場で試してみたりもしてます。
少し前のLEDライトなど暗くてとてもメインに使える物ではなく、自分のサイトの位置を知らせる常夜灯程度の性能しかありませんでした。
しかし、ここ数年で一気に進化したのには驚きです。
自分も4千円くらいのモノを手にいれてみましたが、圧倒的に明るく、しかも光度の調整や灯りの種類も選べるうえに、温度計と時計までついていて、他のモバイル器機に充電までが可能なのです。
少しばかり重いのが難点ですが、バッテリー寿命も相当長く、三日間程度のキャンプでは1/3も電気を消費しませんでした。
もう一つ手にいれれば他の照明器具は恐らく必要なくなるでしょう。
あとは、ソーラー発電パネルを手にいれれば、天候が良好な時はほぼ無限に夜の灯りを手にいれることができます。
最近手に入れたLEDランタンです。
非常に使い勝手が良いので、夜間の作業時に活躍しています。
ここまでは良いことずくめです。
しかし、考えてみてください。
自分は自然の中に文明の便利さを持ち込むためにキャンプしている訳ではありません。
大好きな自然環境の中での落ち着いたひとときをすごしたいがためのキャンプです。
必要な時以外はできるだけ人工的な光は入れたくないのです。
今まで何度かガソリンランタンやガスランタンを手に入れようか考えた事はありました。
ガソリンランタンの点火前の儀式的な作法やガスランタンの手軽さはどちらも魅力的で、量販店のアウトドアコーナーで、何度か手にとって考え込んだものです。
そんなことが10年程も続き、結局手に入れぬまま今に至っています。
理由は当時のランタンでは、まずホワイトガソリンが高価で専門店でなければ手に入らないこと、ガスも同じような理由です。
しかし時代と共にランタンも進化し、赤ガスばかりか様々な燃料を使用できる、マルチヒューエルのランタンやコンロが出回り出し、ガスタイプも安価なカセットガス使用の物が大半を占めています。
手に入れない理由は無くなりました。
しかし令和のこの時代、メインに使っているのは、やはり古ぼけた灯油ランタンなのです。
現在所有している灯油ランタンは、大、中、小、の3つです。
最初に手に入れた大タイプのランタンは20年以上もキャンプのお供をしてくれました。
どこもモノともわからぬまま量販店で見かけたときに買い求めたものですが、特にどこかが壊れるということもなく、最近まで使っていました。
ただ作りがあまり良くなかったようで、芯をどのようにカットしても煤が出て、一晩でホヤが真っ黒になります。
最初は灯油ランタンなんてこんなものだろうぬと気にせずにいたのですが、後に手に入れた物は比較的綺麗に燃えてくれるので、テントの中に持ち込んでも煤に悩まされる事はなくなりました。
外気の余りの冷たさにテントに逃げ込んできた時の一枚です。
ヒーターばかりかランタンまで総動員して暖を取っています。
まあ、外で使う事がメインなので、余り気にしてはいなかったのですが、最近メンテナンス中に芯を押し上げるパーツについているパッキングが劣化して割れてしまいました。
今さら交換パーツが手に入るわけもなく、なんとか使えないこともなかったのですが、風の強い時や万が一落としてしまった時の危険性を考えて、引退してもらう事にしました。
今は小屋の奥で静かに余生を送っております。
特に灯油ランタンに何かこだわりがある訳ではないのですが、あの優しい感じがする独特な光に包まれて過ごす夜は、自分にとって欠かせないモノとなっているようです。
以前、物は試しとLEDライトだけで夜を過ごそうとしたときがありました。
最初は室内にいるのとさして変わらない明るさに驚き、技術力の進歩に感謝し、いつものように晩飯を食べてからタープ下のビーチベットに横になって一杯やりながら本を読んでいたのですが、何かこう違和感のようなものを感じ始めました。
・・・・?
何かわからぬまま、夜は更け、トイレに行き、戻るときに原因がわかりました。
余りにもハッキリとサイトの様子が見えすぎるのです。
サイトに近づくにつれ、LEDライトのギラつく光が全てを照らしていて車のヘッドライトでも当てられているように映し出されています。
まるで自宅にいるようではないか・・・
違和感の原因はこれでした。
自分は自然の中に包まれたくてここに来ているのです。
そこにワザワザ便利さを求めてどうするのだ・・・
便利さを追求し、様々な機器を集めて作られたのが家であり、街であり都市であれば、その真逆を求めたのが本来のキャンプの姿です。
都市生活という、自分には不自然に感じる環境につかれた心身をリセットしたくて、人気の無い野営場などを選んでキャンプしているのに、何で逆を求める・・・?
サイトに戻り、いつもの灯油ランタンを2つ車から下ろし、ホヤを磨き、芯をハサミでカットします。
だいたいこんなもんだろ。
目分量で灯油を補充し、灯りをともします。
タープを支えている2本のポールにランタンを吊り下げ、LEDライトを全て取り払いました。

先程とは段違いの暗さです。
しばらくすると目が暗さに馴れて、タープ下での作業に支障が無くなります。
コンロに炭を足し、ケトルに水を入れ、コーヒーの準備に取りかかります。
炭火の火加減を確認、網の上にケトルを乗せ、立ち上がったついでにタープの外で身体を伸ばし、顔を上に向けるとさっきまでは見えなかった、満天の星空に気がつきます。
手を伸ばせば届きそう。とは正にこの事で、天の川の輝きまでが手に取るように確認できます。
10メートル程歩き、眼前に広がる湖面に目をやれば、半分に欠けた月が鏡のように澄んだ湖面に映し出され、その向こうには山々の稜線が湖をグルリと囲んでいます。
時おり心地よい風が吹き抜け、木々を揺らします。
胸一杯に深呼吸すれば、人工的な何かの匂いが排除された、本当の空気の匂いというものを感じます。
後ろに視界を戻せば、オレンジ色のどこか懐かしい灯りの中で、ケトルが湯気をたてています。
人工的な光の中では人工的な物しか見えなくなります。
そして自然の灯りの中では、自然のモノたちが見えるようになります。
これは経験してみなければ分からない事です。
太古の昔、初期の人類たちが手にして以来、火が作り出すオレンジ色の灯りは、以降電球が発明されるまで何千年もの間人類に夜の闇を照らす灯りを提供してくれました。
この火を操る術を最初の人類が学ぶ事がなければ、現在の地球文明は成り立たなかったでしょう。
暗闇の恐怖を退け、暖を取り、肉を調理するこを覚え、水を沸騰させ肉や木の実、草の類いを合わせて煮込む事で料理が始まりました。
やがては鉄を土や砂から取り出す事を覚え、このとてつもなく固い物質を加工する技術すら産み出していくのです。
恐らく、現代人にもこの記憶が遺伝子レベルで刷り込まれているはずです。
この記憶が色濃く残っている者は自然の中にあるべき何かを求め、古代の記憶を失ってしまった者たちは、逆に現代科学が作り出す文明に適応し、大都市を構成する素子として、更に文明を進化させていくでしょう。
もしかしたら、灯油ランタンの灯りをどのように感じるか?
が、ソロキャンパーとしての資質を見分ける、1つの目安なのかもしれません。
早いもので2021年もあと数日で終わりを告げます。
今年のキャンプはちょっと不完全燃焼気味で終わってしまいました。
前半は連休と悪天候が重なり、中盤は体調不良に悩まされ、後半は仕事とのバッティングに悩まされました。
特に連休に必ず天候が崩れ、しまいには台風まで連続でぶつかって来たときには、台風なんぞ気化爆弾で吹き飛ばすべきだ!!
天に向かって○指を突き立てたものです。
来年こそは悪天候と連休が重なると言う、何かの呪いじみた現象は終わりにして欲しいものです。
外には静かに雪が降り積もっています。
めったに雪が積もったりしない、ここ八戸では珍しい天候です。
各地でも積雪による混乱が生じているようです。
これからの年末年始、車や電車の移動には十分注意してください。
皆様、良いお年をお迎えください。
では、また。
2021年10月17日
単泊と連泊
皆さんこんにちわ、MASADA556です。
暑さがぶり返したり、急に気温が下がったりとおかしな天候でありますが、日を追うごとに秋が深まっていきますね。
東北の地では11月の中頃までにはほとんどのキャンプ場、野営場は閉鎖されて雪の中に埋まってしまいます。
今年のシーズン終了はもうすぐです。
今回はキャンプの楽しみの最大のひとつである長期の連泊や装備の違いについて考えてみましょう。
キャンプの楽しみ方は人それぞれで、キャンプに付随する様々な趣味と合わせて考えれば非常に奥行きが深く間口の広い趣味であると言えます。
皆さんも今度キャンプ場を見回してみてください。
自転車やオートバイ、徒歩旅行などの途中で一時の宿を求めてキャンプ場に入ってくるツーリングライダー。
奥さまや子供達と野外での楽しみを求めて来るファミリー。
登山の中継地点としてキャンプ場を利用する登山者。
一言でキャンプと言ってもその利用目的は様々です。
その中ではっきり分かれるものはキャンプ場の滞在日数です。
デイキャンプから始まり、一泊だけの単発キャンプ。
長期滞在を目的とする連泊キャンプ。
大体がこの三つに分かれるかと思います。
デイキャンプとはBBQに代表されるような、半日あるいは夕方位まで滞在するキャンプのことで手軽にできるキャンプの代表格です。
次に一泊の滞在を目的とした単発キャンプです。
ここから本格的なキャンプとなっていくわけです。
キャンプの形態としては最も一般的なもので、準備する装備も少なめ。
焚き火の炎を楽しみながら、キャンプ場の夜を満喫し、翌朝10時ころにはキャンプ場を出て帰宅の徒につく。
と言った感じでしょうか。
対して2泊以上の滞在を目的とした連泊キャンプは滞在日数に比例して持ち込む装備も大がかりなものになっていきます。
特にキャンプ場をベースとして、自転車やボート等他の趣味の同時進行も考えているようなら、かなりの大型車かトレーラーを牽引してくるような重装備でキャンプに望むことになります。
では、単発と連泊キャンプの考え方、装備の違いについて説明していきたいと思います。
一泊分の装備に燃料や食料を日数分増やせば良いだけでは?
その様な質問を逆に返されそうですが、そう簡単には行かないのがこの趣味の面白さと難しいところです。
続けます。
最近良く目にする単発キャンプスタイルですと、流行りのパップテントのお座敷スタイルでしょうか。
地面にマットを敷き、ドッカリと胡座をかきながら焚き火の灯りのなか、美味しそうなつまみをつつきながら一杯やっている姿を見かけるようになりました。
テント自体の設営撤収も早く、汗を流して撤収作業をしている自分を横目にあっという間にかたづけてスマートに帰っていく姿を見ていると、羨ましくなることがあります。
まさに単発スタイルそのもので、少ないギアを効率的に使うことで設営撤収の手間を省きキャンプ時間を有効に使うことができます。
テント自体も非常に開放的でキャノピーの下にマットと寝袋を準備するだけで、その前に座り込んで火の準備をし、食事をしたり好きな酒を一杯やるわけです。
眠くなれば靴を脱いで後ろのマットに横たわり、寝袋に潜り込むだけ。朝が来れば、インスタントラーメンやパックご飯で簡単な朝食を取ってさっさと帰り支度に入ります。
早い人だと7時ころには撤収を終え、次の目的地に向けて走り出していきます。
自分もバイクで連泊ツーリングをしていた時はこんな感じのキャンプをしていました。
オートバイのシートというのはとかく狭いもので、テントと寝袋マットに簡単な調理器具を積むだけでもうう何のスペースもありません。
それ以外にも雨具と少しばかりの着替え、ロードマップ等を積むともういっぱいでとても今のような余裕のあるキャンプなどできる状況ではありませんでした。
それに当時はキャンプそのものよりもバイクでの移動がメインのキャンプだったので、ギヤを充実させるよりも有り合わせの物を工夫して何とかしようという考えだったので、ガムテープと針金、瞬間接着剤があれば大体のことは解決できたのです。
二十歳代から四十歳前半のバイクでのキャンプ、そして現在の野営そのものを楽しむキャンプ。
どちらも同じキャンプではありますが、似てはいるものの、全く違う世界を楽しんでいることに気がつくことがあります。
ごく最近まで、自分はソロでの単発のキャンプというものを殆んどしたことがありません。
昔も今もメインは連泊オンリーです。
バイクでのツーリングキャンプは別として、ジープにギアを積み込んで山奥に出掛けるようになっても、やはりキャンプは連泊なのです。
ここから自分がなぜ連泊キャンプにこだわるのか?
そして装備、ギアの違いなども織り混ぜてお話していきたいと思います。
先ず前もってお話しておきますが、
自分は物凄い面倒くさがりやです。
例えば食事をすることすら面倒だと感じる時があるくらいです。
そんな日は茹で玉子とコーヒーで1日を生きていたりもします。
おまけに極端な合理主義者と言う、かなりメンドクサイ性格です。
その性格は当然趣味にも反映されています。
つまりはキャンプをするにも極力面倒は避けたいわけです。
先ず面倒な事のトップは、同じ道を一泊程度で行き帰りすることです。
おんなじ景色を眺めながら走っても、たいして面白味の無いことは説明するまでもありませんね。
逆に面白そうな林道が沢山あるような山道などをみつければ、いくら走っても興味は尽きない訳です。
そして一番嫌だと感じるのは、せっかく設営したサイトをたった一晩で撤収する事に酷く抵抗を感じるからです。
地形や風向き等に気を遣い、キャンプ場に合わせて立ち上げたサイトをたった20時間程度で解体してしまうのは、何とも非合理に感じてしまいます。
それともうひとつの大きな理由がありまして、それが連泊キャンプの最大の理由となるのです。
皆さんはキャンプ場を選ぶ時は何を基準としていますか?
有名だから、自宅に近いから、高機能だから、ペットと同伴できるから・・・
どなたにもお気に入りのキャンプ場があり、その理由も様々でしょう。
自分がキャンプ場に求める一番大きな魅力は、そのロケーションにあります。
以前とあるキャンパーの方に、なんで同じキャンプ場に何泊も泊まるのですか?
そんな質問をされたことがあります。
自分の答えはいつも決まっています。
別荘とおんなじですよ。
一番気に入った景色を目の前にして、好きなことを、ノンビリとやっていくのです。
季節が変われば、また新たな景色を求めて場所を変えることもできますよ。
最高の別荘ではないですか?

毎日登ってくる朝日ですが、通勤中の車内から見る時とキャンプ場で見る時ではまるで違って見えるのはなぜでしょうか?
この答えを聞くと大概の方は、
なるほど、分かりますよ!?
と、納得していただけます。
その風景を楽しむためならば、何時間運転しようが、けして苦にならないものです。
冒頭を書いている今も、八戸市の自宅から4時間程も走った山奥の野営場で、キーボードを叩いています。
最も最近は自宅で書き物をするよりも、こうして野外でキーボードに向かい合う方が筆が進むようになってしまいました。

秋田のキャンプ場に向かう時の一枚です。
当日秋田県鹿角に抜ける山ルートは雨で、鹿角市に降りたら急に晴れてきました。
さて、連泊するのはいいとして、そのためにはいかな面倒くさがりの自分でも、それなりに考えなくてはならない事が出てきます。
以前にも書きましたが、先ずは最適なサイト選びから始まります。
自分が気に入った景色が見渡せる場所。
そしてそこがサイトに適しているのか?
トイレや炊事場との距離は?
どの程度のキャンパーが集まりそうか?
強風や豪雨に対処できそうか、等々それらを足したり引いたり、時には割ってみたりしながら、現状での最適なサイトを見つける事になります。
自分は必ず下見をしてからキャンプ場を利用することにしているので、サイトも大体の当たりを付けておきます。
さあ、設営です。
自分の考える野営の条件では、残念ですが、パップテント等のお座敷スタイルは有り得ません。
理由として、極端に悪天候に弱く、テントサイトとして助長性に乏しい事が大きな欠点となるからです。
元々パップテントの原型は各国陸軍兵士の個人装備に遡ります。
野営地や前線での使用を目的としているだけに非常用、あるいは極短時間の使用だけを目的として設計された物です。
したがって辛うじて雨風を凌げる程度の物で、快適性など全く考えていないと言うのがパップテント又はそれに類するテントということになります。
ベトナム戦争当時のアメリカ兵が使っていたテントを友人が持っています。
ポリコットンのような素材のポンチョを2枚張り合わせ、両端に1、5メーター程の枝をポール替わりに立てて、中には2名が潜り込めると言った具合です。
中は真っ暗で狭く、ただ寝ることができるだけです。
ネボスケの友人を朝起こしに行ったら身体の上を蜘蛛が這い廻っていました。
また、お座敷スタイルで強い雨や風雨に曝されるとちょっと大変です。
殆んどのギアが雨ざらしとなり、フロアの無いこのテントでは中が川になったり池になったりします。
こうなると、食事とか睡眠とかの話では無くなり、全てが水没し、泥まみれになります。
開放的とはつまりこのような事も許容しなければならないということです。
二日以上、長ければ5日程度も山にこもるのですから、少しばかりの雨風で狼狽えてはいられない事になります。
そのように考えていけば、どうしても重装備になりがちです。
今回のキャンプ装備で説明します。
先ずテントですが、停滞している台風14号の影響で今一つ天候が読めない上に、このキャンプ場はスマホが一切使えないと言う理由から軽量で乾かしやすいポリエステルの物を準備。
アメリカ製のコットンテントに比べると、どうしても小さめですが、4人用のテントなので、中に籠ってもさほどストレスは感じません。
タープは2種類を準備。
日光を遮る夏向けの物と、耐水性が高く風にも強い、悪天候向けの2枚を用意しました。
到着日は結構日差しが強かったため、夏用のタープを設営。
海面高度631メーターの山の上ですが、日中は暑く、強い日射しで気温が31°に達したので、これで正解のようです。
寝袋はコールマンのスリーシーズン用と、一応、快適温度マイナス15℃まで対応可能な2枚を持っていますが、今回は秋口の高所と言うことで冬用を準備。
何てカッコいい事を書いていますが実は忘れてきました。
しかし常時車に積んでいる防寒装備の毛布類のおかげで、寒い思いをせずにすんでいます。
昨夜22時頃の気温が7℃だったのでこれらの装備が無ければ到底眠ることはできなかったでしょう。
まさに備えあれば患いなしです。
全く自慢にはなりませんが・・・
テーブルは大昔から使っている木製の丸型テーブルを準備しました。
大きく分厚い木製のテーブルは10キロ程も重量があるので移動する時にはかさ張るものの、設置してしまえばその安定感は現在の主流である軽量の折り畳みテーブルとは比較になりません。
今回は初日以外は時おり突風が吹くような風の強いフィールドだったので、これも大正解でした。


素晴らしいサイトですが、ちょっと風が強く時折突風も吹くので、タープのポールを低く下げ、テントやタープのガイロープは手を抜かず全て厳重に固定しています。
また、一切携帯の電波が入らないので、悪天候に変わっても慌てないような準備が必要なキャンプ場です。
睡眠の要となるテント、居住には必須のタープ、食事や作業に大きく影響してくるテーブル類がしっかりしたものでないと、長期間の滞在には不安がつきまとう事になります。
またテント生活のギアは全てが椅子に座る事を前提としているので、地面に直接接しているものはありません。
つまり急な豪雨に直撃されても慌てる事は何もないということです。
但し、気を付けなくてはならないのは、ペグとガイロープだけはしっかりとしたもので設営することです。
これだけはいかに面倒くさがりの自分でも手を抜かない事にしています。
テントのペグは付属品の細いペグなどは使わず、20センチ以上の鍛造ペグを全ヶ所に打ち込み、タープのペグは30センチの物を使用。
張りかたも、強風を考えるとどうしてもA型と呼ばれる形状になってしまいます。
夜中の悪天候に見舞われた時、ずぶ濡れになりながらペグの打ち直しやタープの撤収、最悪は車への避難などまっぴらごめんなので、この辺りの設営道具は重量やかさばり具合などは全く無視して、丈夫、頑丈という、機能のみに重点をおいて買い揃えた物ばかりです。
おかげさまで御隣様が車に逃げ込むことがあっても、自分はペグ、ガイロープの張り具合をチェックする程度ですんでいます。

平日ですので、広々としたサイトは自分の貸し切りです。
このあとサイト内の道路を30分ほどジョギングして久しぶりに汗を流し、近所の温泉に直行です。
次に重要と考えるのは寝具です。
これに関してはそれ以外の物を重要視するような意見も出てくるかも知れませんが、自分的には連泊の良し悪しを左右する大切なギアなのです。
テントは平地に設営すること。
これは言うまでもなくキャンプの常識ですが、そんなまっ平らな地面が見つかる訳もありません。
どうしても、うねりや傾斜があるわけで、マット類でうまく吸収できればいいのですが、中々難しかったりします。
タオルなどを使って調整しても、微妙なうねりが気になって寝付けなかったり、最悪はひどい腰痛に悩まされて予定を繰り上げて八戸に戻り、その足で整骨院に駆け込んだ事まであります。
重い鈍痛に苦しみながらサイトを撤収し、脂汗をかきながら車を運転するような目には二度と合いたくないので、必ずコットを準備することにしています。
コットであれば、少しばかりの地面の凹凸など幾らでも調整可能なうえ、その上に何種類かのマットや長座布団を敷くことによって、好きな様に寝心地をセッティングできるのです。
普段は非常に寝付きの悪い自分でも朝までグッスリと眠れる訳ですから、長期のキャンプにはかかせない物の一つです。
実は、注文していたマットが届いたばかりなので、今夜早速使ってみようとエアーを入れているところです。
以前使っていた5センチ厚のマットがエアーの漏れが出始めたので、今度は同じメーカーの9センチ厚のモデルを購入してみました。
この、マットだけは好みの個人差が大きいギアなので、どれがおすすめとは言えないのですが、自分的に使いやすいと感じているのはインフレーターマットです。
エアーマットの中に弾性素材を封入した構造のマットで、エアーをいれなくてそこそこ弾力性があり、どの程度エアーをいれるかでマットの固さをある調整できるという便利なマットです。
長く使っているとパンクしてしまう、梱包しても大きくて多少重いと言う欠点があるものの、寝心地はとても気にいっています。
使い慣れたコットと適正な固さのマットの組み合わせは、野外での一晩に心地よい睡眠を提供してくれるのです。
質の良い睡眠を適正に取ると言うのはアウトドアでの基本です。
寝不足で疲れを溜め込んでしまったのでは、リフレッシュのためのキャンプと言う意味が無くなってしまいます。
普段は夜型の私生活が、キャンプの生活スタイルでリセットされ、正常な時間帯に体内時計が調整されていくにつれ、体調は改善されて早寝早起きの習慣が戻ってきます。
食欲も改善され、仕事をしている時のように「時間が来たので食べる。」
そんなエネルギー補充的な食事とは違い、「お腹が空いた、美味い飯を食べたい。」
自然と身体の欲求にしたがった食欲に変わっていきます。
キャンプでのご飯はついつい食べすぎてしまうのは、真に身体が求めているためだからでしょう。
そしてYouTubeなどの動画などでもあまり触れられませんが、テント内の環境も非常に大切です。
なんと言っても宿泊地の家となるわけですから、機能的で快適に過ごせなければ、だんだんウンザリしたものになってしまうでしょう。
そのため大さはどうしても四人以上の物が必要で、その中にコットから始まり、細々とした道具類を置かなくてはなりません。
そう考えるとテントの主要キャパは4人以上、中にコットを置いても手足を伸ばせるスペースが欲しくなります。
天候が悪い時は、殆ど一日中で過ごす事になるので、一人~二人用のテントでは、中で全く身動きが取れなくなってしまいます。

アメリカ製のロッジテントの中です。
ごちゃごちゃと散らかっているのはいつものことで、見苦しくてすみません。
大体このようなレイアウトでキャンプしているのですが、他のテントと比べると6人用くらいのキャパがあるので、広々とした幕内は非常に快適です。
また大きくてもフロアの無い形状のテントですと、強風時には終始下から吹き込んでくる隙間風に悩まされることになります。
サイト面が土のときは土埃が舞い上がり、寝袋からクッカーの中までホコリまみれと言うことになってしまいます。
スカート付きの便利な物もありますが、大雨に祟られるとスカート部分が泥だらけになり、後日テントのクリーニングが大変です。
ですがこの辺りの問題は、サイトを注意深く選んでいけば何とかなる話です。
何と言ってもサイトで一番厄介なのは、地面が土、そして次が砂利や採石を敷いたサイトです。
悪天候となればダイレクトに厄災が跳ね返ってくることになるので、自分的には絶対避けたいサイトです。
自分が知る限りそのようなキャンプ場はここ東北の地には無いようですが、過去一度だけ、採石の上の土を被せて芝生にしたようなサイトにあたったことがあります。
ペグを打ち込んだ時に気がついたのですが、10センチも打ち込んだらペグが硬いものに突き当たり、止まってしまいました。
当時はテント付属の細いピンペグを使っていたので、これは不味いな。
そう感じたことを覚えています。
ペグの感触を探りながら、少しずつずらしてようやく全ヶ所を打ち込みましたが、ペグの保持力が弱く、引っ張ると簡単に抜けてきます。
当然キャンプ場の利用手続きを済ませてあったので、どうしようもなく、不安な一夜を過ごしました。
幸い穏やかな一夜でしたが、当時は天候を調べる方法はラジオ程度の物しかなく、ずっとラジオ放送に耳を傾けつつ、暖めたオニギリにかじりついていました。
今ではそんな事も無くなりましたが、キャンプ初心者の方々には注意して欲しい問題です。
見誤ると強風に当たってしまった時、テントごと吹き飛ばされかねないことになります。

確か秋田県阿仁付近の山道での一枚だったと思います。
朝早くから走り回っていたので食後に山道脇のパーキングに車を止めて一休みです。
30分程度の仮眠のつもりが二時間近く眠ってしまい、自宅に着いたのは21時ころになってしまいました。
もう一つ注意したいにが、テントの色です。
女性のソロキャンパーも当たり前に見かける現在、カラフルな色合いのテントも多数ネット通販のサイトで見かけるようになりました。
しかし、購入ボタンをクリックする前に、本当にそのカラーで良いのかもう一度考えてみてください。
最近、何だかなあ~・・・。そう感じたのは真っ赤なテントと真っ黒なテントです。
これは個人の感覚の問題なので一概には言えない事ですが、色覚というのは人間の五感の中でも大なウエイトを占めているものなので、普段あり得ないような色合いの中で生活していくのは、感覚的にかなり不自然です。
絶対とは言いませんが、自分の部屋の壁紙の色が真っ赤です。というような人もまずいないのではないでしょうか?
何もかも赤く染まった空間の中で本を読んだり動画を見たりしたあとに表に出ていけば、あまりの違和感に立ち眩みを起こしそうになるでしょう。
恐らくテント内で食事をしたときにも、かなり違和感を感じると思いますよ。
真っ赤な焼き肉なんて、はたしてしっかり焼けているのかすら良くわからないうえに、虫が紛れ込んでいても気がつきませんね。
自分的には、敬遠したいのは、とにかくおかしな色のテントです。
同様に真っ黒なテントというのも、かなり考えものでしょう。
単純に考えても、夏に限らず日差しの強いときはとてつもなく暑くなるわけで、真夏ならもはや、熱い!!のレベルの達するでしょう。
昼間でも少し日が陰れば真っ暗となり、ランタンを準備する必要が出てくるかもしれません。
何だか洞窟にでも住んでいる気分になるのではないでしょうか?
テントとは間違いなく実用的な道具です。
可愛いとか格好いいなどのおかしなセンスで選んでしまえば、キャンプ場で苦労するのは、間違いなく自分であることは忘れないことです。
最後に、これは個人的な意見ですが、キャンプ初心者の方々にこそ連泊を経験して欲しいと思います。
もちろんいきなりというのは無理がありますが、自分が気に入ったキャンプ場を見つけた時が最初のチャンスです。
宿泊日数に合わせた燃料、食料の計画、キャンプ場周辺の地理、天候を良く調べ、最適なサイトを探し数日間の別荘を立ち上げてください。
もちろん色々な苦労が出てきます。
しかし日程に余裕があれば、何も焦る必要はありません。
逆に試してみたいことがあれば、積極的にやってみるだけの時間的な余裕があります。
ゆったりとした時間を過ごし、朝日のコーヒー、日中の穏やかなひと時、ゆっくりと落ちていく夕日を眺め、オイルランタンの明かりの中、口にする酒の美味さは、言葉では言い表せないものがあります。
そして撤収後にキャンプサイトを見回し、忘れ物やゴミの確認を済ませ、キャンプ場を後にするときの感覚は、何度体験しても寂しいものです。
また、あそこに戻るのか・・・
潔く自宅に帰る気にならず、必ずと言っていいほど近辺の観光地や新たなキャンプ場を探しにハンドルを切るわけです。
悪天候が続くようなキャンプの時は疲労が身体に残り、しばらくはいいかな・・・。そう思う時もありますが、何日か会社と自宅を往復する日々を過ごしていると、当たり前のように新たなキャンプ計画を立てている自分に気づくことがあります。
思わず苦笑いです。


とあるキャンプ場の下見に向かっているところです。
この後に更に道は険しく狭くなるのですが、管理人の居るしっかりしたキャンプ場でした。
がけ崩れで最近まで通行止めになっていたそうです。
15分ほど管理人のおじさんと話した後、雨の中八戸まで4時間強のドライブです。
面白い林道ですが、さすがに熊が多く、行きと帰りに熊を見かけました。
ツキノワグマが当たり前に道路を横切っていきます。

ホルスターに入っているのはペッパースプレーです。
自分は少しばかり武道の心得がありますが、クマと柔道をやらかす自信もないので、山に入るときは必須と考えています。
ここ、東北の地や北海道ではちょっと山に入れば当たり前に熊を見かけます、また実際に襲われて複数の人間が命を落としています。
甘えた考えは厳禁です。
この辺りでペンを置きたいと思います。
連泊キャンプの楽しさや、道具選びの違いや基準と言うものが少しでもお分かりいただければ幸いです。
では、また。
暑さがぶり返したり、急に気温が下がったりとおかしな天候でありますが、日を追うごとに秋が深まっていきますね。
東北の地では11月の中頃までにはほとんどのキャンプ場、野営場は閉鎖されて雪の中に埋まってしまいます。
今年のシーズン終了はもうすぐです。
今回はキャンプの楽しみの最大のひとつである長期の連泊や装備の違いについて考えてみましょう。
キャンプの楽しみ方は人それぞれで、キャンプに付随する様々な趣味と合わせて考えれば非常に奥行きが深く間口の広い趣味であると言えます。
皆さんも今度キャンプ場を見回してみてください。
自転車やオートバイ、徒歩旅行などの途中で一時の宿を求めてキャンプ場に入ってくるツーリングライダー。
奥さまや子供達と野外での楽しみを求めて来るファミリー。
登山の中継地点としてキャンプ場を利用する登山者。
一言でキャンプと言ってもその利用目的は様々です。
その中ではっきり分かれるものはキャンプ場の滞在日数です。
デイキャンプから始まり、一泊だけの単発キャンプ。
長期滞在を目的とする連泊キャンプ。
大体がこの三つに分かれるかと思います。
デイキャンプとはBBQに代表されるような、半日あるいは夕方位まで滞在するキャンプのことで手軽にできるキャンプの代表格です。
次に一泊の滞在を目的とした単発キャンプです。
ここから本格的なキャンプとなっていくわけです。
キャンプの形態としては最も一般的なもので、準備する装備も少なめ。
焚き火の炎を楽しみながら、キャンプ場の夜を満喫し、翌朝10時ころにはキャンプ場を出て帰宅の徒につく。
と言った感じでしょうか。
対して2泊以上の滞在を目的とした連泊キャンプは滞在日数に比例して持ち込む装備も大がかりなものになっていきます。
特にキャンプ場をベースとして、自転車やボート等他の趣味の同時進行も考えているようなら、かなりの大型車かトレーラーを牽引してくるような重装備でキャンプに望むことになります。
では、単発と連泊キャンプの考え方、装備の違いについて説明していきたいと思います。
一泊分の装備に燃料や食料を日数分増やせば良いだけでは?
その様な質問を逆に返されそうですが、そう簡単には行かないのがこの趣味の面白さと難しいところです。
続けます。
最近良く目にする単発キャンプスタイルですと、流行りのパップテントのお座敷スタイルでしょうか。
地面にマットを敷き、ドッカリと胡座をかきながら焚き火の灯りのなか、美味しそうなつまみをつつきながら一杯やっている姿を見かけるようになりました。
テント自体の設営撤収も早く、汗を流して撤収作業をしている自分を横目にあっという間にかたづけてスマートに帰っていく姿を見ていると、羨ましくなることがあります。
まさに単発スタイルそのもので、少ないギアを効率的に使うことで設営撤収の手間を省きキャンプ時間を有効に使うことができます。
テント自体も非常に開放的でキャノピーの下にマットと寝袋を準備するだけで、その前に座り込んで火の準備をし、食事をしたり好きな酒を一杯やるわけです。
眠くなれば靴を脱いで後ろのマットに横たわり、寝袋に潜り込むだけ。朝が来れば、インスタントラーメンやパックご飯で簡単な朝食を取ってさっさと帰り支度に入ります。
早い人だと7時ころには撤収を終え、次の目的地に向けて走り出していきます。
自分もバイクで連泊ツーリングをしていた時はこんな感じのキャンプをしていました。
オートバイのシートというのはとかく狭いもので、テントと寝袋マットに簡単な調理器具を積むだけでもうう何のスペースもありません。
それ以外にも雨具と少しばかりの着替え、ロードマップ等を積むともういっぱいでとても今のような余裕のあるキャンプなどできる状況ではありませんでした。
それに当時はキャンプそのものよりもバイクでの移動がメインのキャンプだったので、ギヤを充実させるよりも有り合わせの物を工夫して何とかしようという考えだったので、ガムテープと針金、瞬間接着剤があれば大体のことは解決できたのです。
二十歳代から四十歳前半のバイクでのキャンプ、そして現在の野営そのものを楽しむキャンプ。
どちらも同じキャンプではありますが、似てはいるものの、全く違う世界を楽しんでいることに気がつくことがあります。
ごく最近まで、自分はソロでの単発のキャンプというものを殆んどしたことがありません。
昔も今もメインは連泊オンリーです。
バイクでのツーリングキャンプは別として、ジープにギアを積み込んで山奥に出掛けるようになっても、やはりキャンプは連泊なのです。
ここから自分がなぜ連泊キャンプにこだわるのか?
そして装備、ギアの違いなども織り混ぜてお話していきたいと思います。
先ず前もってお話しておきますが、
自分は物凄い面倒くさがりやです。
例えば食事をすることすら面倒だと感じる時があるくらいです。
そんな日は茹で玉子とコーヒーで1日を生きていたりもします。
おまけに極端な合理主義者と言う、かなりメンドクサイ性格です。
その性格は当然趣味にも反映されています。
つまりはキャンプをするにも極力面倒は避けたいわけです。
先ず面倒な事のトップは、同じ道を一泊程度で行き帰りすることです。
おんなじ景色を眺めながら走っても、たいして面白味の無いことは説明するまでもありませんね。
逆に面白そうな林道が沢山あるような山道などをみつければ、いくら走っても興味は尽きない訳です。
そして一番嫌だと感じるのは、せっかく設営したサイトをたった一晩で撤収する事に酷く抵抗を感じるからです。
地形や風向き等に気を遣い、キャンプ場に合わせて立ち上げたサイトをたった20時間程度で解体してしまうのは、何とも非合理に感じてしまいます。
それともうひとつの大きな理由がありまして、それが連泊キャンプの最大の理由となるのです。
皆さんはキャンプ場を選ぶ時は何を基準としていますか?
有名だから、自宅に近いから、高機能だから、ペットと同伴できるから・・・
どなたにもお気に入りのキャンプ場があり、その理由も様々でしょう。
自分がキャンプ場に求める一番大きな魅力は、そのロケーションにあります。
以前とあるキャンパーの方に、なんで同じキャンプ場に何泊も泊まるのですか?
そんな質問をされたことがあります。
自分の答えはいつも決まっています。
別荘とおんなじですよ。
一番気に入った景色を目の前にして、好きなことを、ノンビリとやっていくのです。
季節が変われば、また新たな景色を求めて場所を変えることもできますよ。
最高の別荘ではないですか?
毎日登ってくる朝日ですが、通勤中の車内から見る時とキャンプ場で見る時ではまるで違って見えるのはなぜでしょうか?
この答えを聞くと大概の方は、
なるほど、分かりますよ!?
と、納得していただけます。
その風景を楽しむためならば、何時間運転しようが、けして苦にならないものです。
冒頭を書いている今も、八戸市の自宅から4時間程も走った山奥の野営場で、キーボードを叩いています。
最も最近は自宅で書き物をするよりも、こうして野外でキーボードに向かい合う方が筆が進むようになってしまいました。
秋田のキャンプ場に向かう時の一枚です。
当日秋田県鹿角に抜ける山ルートは雨で、鹿角市に降りたら急に晴れてきました。
さて、連泊するのはいいとして、そのためにはいかな面倒くさがりの自分でも、それなりに考えなくてはならない事が出てきます。
以前にも書きましたが、先ずは最適なサイト選びから始まります。
自分が気に入った景色が見渡せる場所。
そしてそこがサイトに適しているのか?
トイレや炊事場との距離は?
どの程度のキャンパーが集まりそうか?
強風や豪雨に対処できそうか、等々それらを足したり引いたり、時には割ってみたりしながら、現状での最適なサイトを見つける事になります。
自分は必ず下見をしてからキャンプ場を利用することにしているので、サイトも大体の当たりを付けておきます。
さあ、設営です。
自分の考える野営の条件では、残念ですが、パップテント等のお座敷スタイルは有り得ません。
理由として、極端に悪天候に弱く、テントサイトとして助長性に乏しい事が大きな欠点となるからです。
元々パップテントの原型は各国陸軍兵士の個人装備に遡ります。
野営地や前線での使用を目的としているだけに非常用、あるいは極短時間の使用だけを目的として設計された物です。
したがって辛うじて雨風を凌げる程度の物で、快適性など全く考えていないと言うのがパップテント又はそれに類するテントということになります。
ベトナム戦争当時のアメリカ兵が使っていたテントを友人が持っています。
ポリコットンのような素材のポンチョを2枚張り合わせ、両端に1、5メーター程の枝をポール替わりに立てて、中には2名が潜り込めると言った具合です。
中は真っ暗で狭く、ただ寝ることができるだけです。
ネボスケの友人を朝起こしに行ったら身体の上を蜘蛛が這い廻っていました。
また、お座敷スタイルで強い雨や風雨に曝されるとちょっと大変です。
殆んどのギアが雨ざらしとなり、フロアの無いこのテントでは中が川になったり池になったりします。
こうなると、食事とか睡眠とかの話では無くなり、全てが水没し、泥まみれになります。
開放的とはつまりこのような事も許容しなければならないということです。
二日以上、長ければ5日程度も山にこもるのですから、少しばかりの雨風で狼狽えてはいられない事になります。
そのように考えていけば、どうしても重装備になりがちです。
今回のキャンプ装備で説明します。
先ずテントですが、停滞している台風14号の影響で今一つ天候が読めない上に、このキャンプ場はスマホが一切使えないと言う理由から軽量で乾かしやすいポリエステルの物を準備。
アメリカ製のコットンテントに比べると、どうしても小さめですが、4人用のテントなので、中に籠ってもさほどストレスは感じません。
タープは2種類を準備。
日光を遮る夏向けの物と、耐水性が高く風にも強い、悪天候向けの2枚を用意しました。
到着日は結構日差しが強かったため、夏用のタープを設営。
海面高度631メーターの山の上ですが、日中は暑く、強い日射しで気温が31°に達したので、これで正解のようです。
寝袋はコールマンのスリーシーズン用と、一応、快適温度マイナス15℃まで対応可能な2枚を持っていますが、今回は秋口の高所と言うことで冬用を準備。
何てカッコいい事を書いていますが実は忘れてきました。
しかし常時車に積んでいる防寒装備の毛布類のおかげで、寒い思いをせずにすんでいます。
昨夜22時頃の気温が7℃だったのでこれらの装備が無ければ到底眠ることはできなかったでしょう。
まさに備えあれば患いなしです。
全く自慢にはなりませんが・・・
テーブルは大昔から使っている木製の丸型テーブルを準備しました。
大きく分厚い木製のテーブルは10キロ程も重量があるので移動する時にはかさ張るものの、設置してしまえばその安定感は現在の主流である軽量の折り畳みテーブルとは比較になりません。
今回は初日以外は時おり突風が吹くような風の強いフィールドだったので、これも大正解でした。
素晴らしいサイトですが、ちょっと風が強く時折突風も吹くので、タープのポールを低く下げ、テントやタープのガイロープは手を抜かず全て厳重に固定しています。
また、一切携帯の電波が入らないので、悪天候に変わっても慌てないような準備が必要なキャンプ場です。
睡眠の要となるテント、居住には必須のタープ、食事や作業に大きく影響してくるテーブル類がしっかりしたものでないと、長期間の滞在には不安がつきまとう事になります。
またテント生活のギアは全てが椅子に座る事を前提としているので、地面に直接接しているものはありません。
つまり急な豪雨に直撃されても慌てる事は何もないということです。
但し、気を付けなくてはならないのは、ペグとガイロープだけはしっかりとしたもので設営することです。
これだけはいかに面倒くさがりの自分でも手を抜かない事にしています。
テントのペグは付属品の細いペグなどは使わず、20センチ以上の鍛造ペグを全ヶ所に打ち込み、タープのペグは30センチの物を使用。
張りかたも、強風を考えるとどうしてもA型と呼ばれる形状になってしまいます。
夜中の悪天候に見舞われた時、ずぶ濡れになりながらペグの打ち直しやタープの撤収、最悪は車への避難などまっぴらごめんなので、この辺りの設営道具は重量やかさばり具合などは全く無視して、丈夫、頑丈という、機能のみに重点をおいて買い揃えた物ばかりです。
おかげさまで御隣様が車に逃げ込むことがあっても、自分はペグ、ガイロープの張り具合をチェックする程度ですんでいます。
平日ですので、広々としたサイトは自分の貸し切りです。
このあとサイト内の道路を30分ほどジョギングして久しぶりに汗を流し、近所の温泉に直行です。
次に重要と考えるのは寝具です。
これに関してはそれ以外の物を重要視するような意見も出てくるかも知れませんが、自分的には連泊の良し悪しを左右する大切なギアなのです。
テントは平地に設営すること。
これは言うまでもなくキャンプの常識ですが、そんなまっ平らな地面が見つかる訳もありません。
どうしても、うねりや傾斜があるわけで、マット類でうまく吸収できればいいのですが、中々難しかったりします。
タオルなどを使って調整しても、微妙なうねりが気になって寝付けなかったり、最悪はひどい腰痛に悩まされて予定を繰り上げて八戸に戻り、その足で整骨院に駆け込んだ事まであります。
重い鈍痛に苦しみながらサイトを撤収し、脂汗をかきながら車を運転するような目には二度と合いたくないので、必ずコットを準備することにしています。
コットであれば、少しばかりの地面の凹凸など幾らでも調整可能なうえ、その上に何種類かのマットや長座布団を敷くことによって、好きな様に寝心地をセッティングできるのです。
普段は非常に寝付きの悪い自分でも朝までグッスリと眠れる訳ですから、長期のキャンプにはかかせない物の一つです。
実は、注文していたマットが届いたばかりなので、今夜早速使ってみようとエアーを入れているところです。
以前使っていた5センチ厚のマットがエアーの漏れが出始めたので、今度は同じメーカーの9センチ厚のモデルを購入してみました。
この、マットだけは好みの個人差が大きいギアなので、どれがおすすめとは言えないのですが、自分的に使いやすいと感じているのはインフレーターマットです。
エアーマットの中に弾性素材を封入した構造のマットで、エアーをいれなくてそこそこ弾力性があり、どの程度エアーをいれるかでマットの固さをある調整できるという便利なマットです。
長く使っているとパンクしてしまう、梱包しても大きくて多少重いと言う欠点があるものの、寝心地はとても気にいっています。
使い慣れたコットと適正な固さのマットの組み合わせは、野外での一晩に心地よい睡眠を提供してくれるのです。
質の良い睡眠を適正に取ると言うのはアウトドアでの基本です。
寝不足で疲れを溜め込んでしまったのでは、リフレッシュのためのキャンプと言う意味が無くなってしまいます。
普段は夜型の私生活が、キャンプの生活スタイルでリセットされ、正常な時間帯に体内時計が調整されていくにつれ、体調は改善されて早寝早起きの習慣が戻ってきます。
食欲も改善され、仕事をしている時のように「時間が来たので食べる。」
そんなエネルギー補充的な食事とは違い、「お腹が空いた、美味い飯を食べたい。」
自然と身体の欲求にしたがった食欲に変わっていきます。
キャンプでのご飯はついつい食べすぎてしまうのは、真に身体が求めているためだからでしょう。
そしてYouTubeなどの動画などでもあまり触れられませんが、テント内の環境も非常に大切です。
なんと言っても宿泊地の家となるわけですから、機能的で快適に過ごせなければ、だんだんウンザリしたものになってしまうでしょう。
そのため大さはどうしても四人以上の物が必要で、その中にコットから始まり、細々とした道具類を置かなくてはなりません。
そう考えるとテントの主要キャパは4人以上、中にコットを置いても手足を伸ばせるスペースが欲しくなります。
天候が悪い時は、殆ど一日中で過ごす事になるので、一人~二人用のテントでは、中で全く身動きが取れなくなってしまいます。
アメリカ製のロッジテントの中です。
ごちゃごちゃと散らかっているのはいつものことで、見苦しくてすみません。
大体このようなレイアウトでキャンプしているのですが、他のテントと比べると6人用くらいのキャパがあるので、広々とした幕内は非常に快適です。
また大きくてもフロアの無い形状のテントですと、強風時には終始下から吹き込んでくる隙間風に悩まされることになります。
サイト面が土のときは土埃が舞い上がり、寝袋からクッカーの中までホコリまみれと言うことになってしまいます。
スカート付きの便利な物もありますが、大雨に祟られるとスカート部分が泥だらけになり、後日テントのクリーニングが大変です。
ですがこの辺りの問題は、サイトを注意深く選んでいけば何とかなる話です。
何と言ってもサイトで一番厄介なのは、地面が土、そして次が砂利や採石を敷いたサイトです。
悪天候となればダイレクトに厄災が跳ね返ってくることになるので、自分的には絶対避けたいサイトです。
自分が知る限りそのようなキャンプ場はここ東北の地には無いようですが、過去一度だけ、採石の上の土を被せて芝生にしたようなサイトにあたったことがあります。
ペグを打ち込んだ時に気がついたのですが、10センチも打ち込んだらペグが硬いものに突き当たり、止まってしまいました。
当時はテント付属の細いピンペグを使っていたので、これは不味いな。
そう感じたことを覚えています。
ペグの感触を探りながら、少しずつずらしてようやく全ヶ所を打ち込みましたが、ペグの保持力が弱く、引っ張ると簡単に抜けてきます。
当然キャンプ場の利用手続きを済ませてあったので、どうしようもなく、不安な一夜を過ごしました。
幸い穏やかな一夜でしたが、当時は天候を調べる方法はラジオ程度の物しかなく、ずっとラジオ放送に耳を傾けつつ、暖めたオニギリにかじりついていました。
今ではそんな事も無くなりましたが、キャンプ初心者の方々には注意して欲しい問題です。
見誤ると強風に当たってしまった時、テントごと吹き飛ばされかねないことになります。
確か秋田県阿仁付近の山道での一枚だったと思います。
朝早くから走り回っていたので食後に山道脇のパーキングに車を止めて一休みです。
30分程度の仮眠のつもりが二時間近く眠ってしまい、自宅に着いたのは21時ころになってしまいました。
もう一つ注意したいにが、テントの色です。
女性のソロキャンパーも当たり前に見かける現在、カラフルな色合いのテントも多数ネット通販のサイトで見かけるようになりました。
しかし、購入ボタンをクリックする前に、本当にそのカラーで良いのかもう一度考えてみてください。
最近、何だかなあ~・・・。そう感じたのは真っ赤なテントと真っ黒なテントです。
これは個人の感覚の問題なので一概には言えない事ですが、色覚というのは人間の五感の中でも大なウエイトを占めているものなので、普段あり得ないような色合いの中で生活していくのは、感覚的にかなり不自然です。
絶対とは言いませんが、自分の部屋の壁紙の色が真っ赤です。というような人もまずいないのではないでしょうか?
何もかも赤く染まった空間の中で本を読んだり動画を見たりしたあとに表に出ていけば、あまりの違和感に立ち眩みを起こしそうになるでしょう。
恐らくテント内で食事をしたときにも、かなり違和感を感じると思いますよ。
真っ赤な焼き肉なんて、はたしてしっかり焼けているのかすら良くわからないうえに、虫が紛れ込んでいても気がつきませんね。
自分的には、敬遠したいのは、とにかくおかしな色のテントです。
同様に真っ黒なテントというのも、かなり考えものでしょう。
単純に考えても、夏に限らず日差しの強いときはとてつもなく暑くなるわけで、真夏ならもはや、熱い!!のレベルの達するでしょう。
昼間でも少し日が陰れば真っ暗となり、ランタンを準備する必要が出てくるかもしれません。
何だか洞窟にでも住んでいる気分になるのではないでしょうか?
テントとは間違いなく実用的な道具です。
可愛いとか格好いいなどのおかしなセンスで選んでしまえば、キャンプ場で苦労するのは、間違いなく自分であることは忘れないことです。
最後に、これは個人的な意見ですが、キャンプ初心者の方々にこそ連泊を経験して欲しいと思います。
もちろんいきなりというのは無理がありますが、自分が気に入ったキャンプ場を見つけた時が最初のチャンスです。
宿泊日数に合わせた燃料、食料の計画、キャンプ場周辺の地理、天候を良く調べ、最適なサイトを探し数日間の別荘を立ち上げてください。
もちろん色々な苦労が出てきます。
しかし日程に余裕があれば、何も焦る必要はありません。
逆に試してみたいことがあれば、積極的にやってみるだけの時間的な余裕があります。
ゆったりとした時間を過ごし、朝日のコーヒー、日中の穏やかなひと時、ゆっくりと落ちていく夕日を眺め、オイルランタンの明かりの中、口にする酒の美味さは、言葉では言い表せないものがあります。
そして撤収後にキャンプサイトを見回し、忘れ物やゴミの確認を済ませ、キャンプ場を後にするときの感覚は、何度体験しても寂しいものです。
また、あそこに戻るのか・・・
潔く自宅に帰る気にならず、必ずと言っていいほど近辺の観光地や新たなキャンプ場を探しにハンドルを切るわけです。
悪天候が続くようなキャンプの時は疲労が身体に残り、しばらくはいいかな・・・。そう思う時もありますが、何日か会社と自宅を往復する日々を過ごしていると、当たり前のように新たなキャンプ計画を立てている自分に気づくことがあります。
思わず苦笑いです。
とあるキャンプ場の下見に向かっているところです。
この後に更に道は険しく狭くなるのですが、管理人の居るしっかりしたキャンプ場でした。
がけ崩れで最近まで通行止めになっていたそうです。
15分ほど管理人のおじさんと話した後、雨の中八戸まで4時間強のドライブです。
面白い林道ですが、さすがに熊が多く、行きと帰りに熊を見かけました。
ツキノワグマが当たり前に道路を横切っていきます。
ホルスターに入っているのはペッパースプレーです。
自分は少しばかり武道の心得がありますが、クマと柔道をやらかす自信もないので、山に入るときは必須と考えています。
ここ、東北の地や北海道ではちょっと山に入れば当たり前に熊を見かけます、また実際に襲われて複数の人間が命を落としています。
甘えた考えは厳禁です。
この辺りでペンを置きたいと思います。
連泊キャンプの楽しさや、道具選びの違いや基準と言うものが少しでもお分かりいただければ幸いです。
では、また。
2021年09月27日
車両その2
こんにちわ、MASADA556です。
今日は栗拾いにでも行こうか・・・
何て考えていたのですが、急遽変更して車の整備です。
と言うのも連休中のキャンプから帰る途中、ずっと豪雨に見舞われ、その中を四時間程も走って八戸まで戻って来ました。
そして9月の25日が一日中強い雨が降り続け、結果として車の中が池のようになってしまい、積んであるものが全てずぶ濡れになりました。
なんで、そんなバカな事になるのかと言いますと、両側のドアが無いからです。
実は現在、ドアを修理ついでに改良中でして、依頼した当初は一週間の見積もりでしたが一ヶ月ほども経った現在もまだ帰って来ていないのです。

フルクローズのドアの代わりにハーフドアをつけています。
膝上をカバーする程度のドアですが、これが無いと、風は巻き込むわ、フロントタイヤが巻き上げた雨水がシャワーのように降りかかるわで、大雨の時は溺れそうになります。
最も幌を外す事が前提の車なので、車自体は特に問題は無いのですが、それに乗っている人間は別の話で、寒くて暑く、硬いサスペンションでピョンピョン跳ね回るこの車に乗ることに、体力的な限界を感じた時がソロキャンプも卒業だと考えています。
但し、古い車なので部品探しも大変で、維持していくのも難しくなりつつあります。
今回は車の整備ついでに自分の車を少しばかり読者の皆さんに紹介していきたいと思います。
正式名称は三菱JEEP J55\FEと言います。
車両の起源はとてつもなく古く、1941年の第二次世界大戦時まで遡ります。
当初は前線偵察用4\1t 4×4トラックとして開発されました。
後にJEEPと呼ばれるようになった、戦場で絶大な信頼を得ていたトラックを、終戦後に三菱がライセンス生産した車両が三菱JEEPと言うトラックなのです。
四駆タイプの車をジープと呼ぶ人がたまに居ますが、それは間違いでライセンスを所得していた三菱以外は、JEEPの名称もその特徴的な七本スリットのフロントグリルも一切使うことはできません。
1952年から製造を開始、1998年にライセンスを返上し、生産を終了した今では三菱ですら、JEEPの名前をホームページ上で見かける事はありません。
日本でJEEPと呼ばれる車両は、三菱自動車が生産したトラックだけなのです。

その中で最後に特別仕様で300台だけ生産したファイナルエディションモデルの一台が自分のJ55です。
ちなみに今大人気のスズキジムニーですが、その名前の由来は、JEEPの弟分、ジープミニがジムニーと言う車名になったのだ。
そのように聞いたことがあります。
もし興味を持たれたのであれば、少しばかりネット検索してはいかがですか?
物凄い量の情報が出てきますよ。
では始めましょう。
最初はとにかく車内の物を全て表に出し、日と風に当てて乾かすことから始めましょう。
滴るほど雨水を吸い込んだマット、毛布、細い道具類を次々と引っ張り出していくと、先週のキャンプ場から同行してきたカメムシが幾らでも出てきます。
自分は刺してこない限り、あまり虫の類は気にしない達なので、適当に表に放り出しますが、ダメな方はこの時点で挫けるかもしれません。
ここ何年か夏の豪雨が極端になってきていますので、幌を全部外すフルオープンにはしていません。
おかげさまで、車内には砂や土埃が泥状態になってこびりついていますので、一気に洗車です。


少しでも車という物を御存じの方が見たら驚くでしょう。
しかし、心配には及びません。
計器類を始め、JEEPのパーツは防水仕様になっているので、中も外も洗車できるのです。

ナビシートの下を洗っているところです。
この下に燃料タンクが入っています。つまり助手席に座る人は燃料の上に座っているのです。
以前錆びたタンクに穴が開いて、ナビシート下のフットスペースに軽油がたっぷりと溜まっていたことがあります。
自分はタバコは吸わないので問題ないのですが、さすがにあまりいい気分はしませんでしたね。
普通の乗用車なら内装は腐食するわ、匂いが抜けないわで廃車になってしまうのでしょうが、フロアに開いている水抜きから軽油を抜いて洗車してしまえばOKです。

ちょっと見ずらいかもしれません。
真ん中に見えるのが、フットスペースに開いている水抜き穴です。
雨が降れば水が嫌でも入ってくるので普段から開けっ放しです。
ブラシと洗剤で数年分の汚れを洗い流したら乾かしましょう。
幸い今日は程よい日差しとちょい強めの風が吹いているので、すぐに乾くでしょう。


見違えるように綺麗になりました。
さっきまでの畑仕事後の耕運機みたいな車内とは思えません。
コーヒーをたてて一休みしたら、今度は乾くまでの時間を利用してタイヤローテーションもしましょう。
出来るだけ車のメンテナンスは自分でやるようにしています。
とは言っても、エンジンはディーゼルなので、殆どメンテナンスフリーです。
精々オイル交換とエアクリーナーの点検と交換、ラジエター液の補充とバッテリーのチェックくらいしかやれることはありません。
そして四千キロごとのオイル交換時に、駆動系とステアリング系周りにグリスアップが必要で、グリスガン片手に車の下に潜り込むことになります。
先週にオイル交換とグリスアップは済ませましたので、残ったローテーションをやってしまいましょう。
これをサボるとタイヤが偏摩耗して極端に寿命が短くなってしまいます。
ただし、しっかりしたジャッキなどの工具類とそれなりの経験が無いと、ジャッキを倒してしまったり知らぬうちにハブナットが緩んでいたいたりと非常に危険な事になりますので、初めての方はスタンドなどで店員さんにアドバイスを受けましょう。
とにかく自信と知識が無ければ手を出すべきではありません。
車両の整備とは、自己責任が伴う行為だという事を忘れないことです。
さて硬い話はここまでにして、サッサと済ませてしまいましょう。
ま助手席側から外します。
jeepはそちら側のハブナットが逆ねじになっているので、それを知らずにインパクトを使うとハブボルトを折ってしまうことになりますので要注意です。
Jeep乗りにはありがちな話ですが、タイヤ交換やパンク修理の時にスタンドの店員に説明しておかないとやられてしまいます。
以前スタンドでパンク修理を依頼した時に、店員に説明したのにかかわらずやられそうになったことがあります。
信じられないことに、ハブボルトに逆ねじがあることを知らなかったようです。
某大手の自動車部品の量販店で、でオイル交換のついでに、自分がグリスアップをしたい旨を伝えた時もちょっと困りました。
「お客さんを工場に入れられない。グリスアップが必要ならメカニックがやります」
そんな答えでしたが、若いスタッフしか見かけない工場の様子に不安を覚えた自分は、出来ますか?。
そう伺うと、大丈夫という答えが帰って来たので、料金を聞くと五千円という答えが返ってきました。
自分がやれば十分程度の作業に、五千円という法外な料金請求にちょっとカチンときた自分は、店員に、
「伺いますが、三菱Jeepのグリスアップポイントはどこに何ヶ所ありますか?」
すると、分からない。という想像の斜め上な返事が返ってきました。
驚いた自分は、「はっ・・・この会社は作業内容もろくに分からないのに、料金だけは出せるのですか?
どういう理屈でしょう」
すると店員氏は「・・・・・ならばグリスアップの必要な個所を指示していただければ、大丈夫です」
その返答にあきれ果てた自分は、
「それで五千円請求するつもりですか?・・・良いです、5千円は払いましょう。
その代わり整備授業料として自分は一万五千円請求しますが、それで良いですか」
店員氏は黙り込んでしまったので、
「とても安心して任せられないので、オイル交換も結構です、自分でやりますから」
そう言いおいて店を出て、代わりに〇ェームスに寄って同じことをお願いしたら、快くピットを貸してくださいました。
また幾つかのアドバイスもいただきましたので、大変助かりました。
古い車ならでのエピソードの一つです。
以前乗っていた古いジム二ーの時も似たようなアクシデントが何回かあったので、信用できる車屋さん以外は、一切他人に車をさわらせないようにしています。

昔話をしているうちにローテーション完了です。
あとは数十キロ走った後軽く増し締めすれば完了です。
次にタイヤに手をかける時はスタッドレスタイヤに交換の時になります。

ついでのついでにシート下のトランクスペースも開けました。
ここのウエザーストリップが破れると水が溜まってしまい、錆びてしまいます。
最悪底が抜けて工具類がそっくり無くなります。
大昔、友人のjeepの底が抜けてしまい、ベニヤ板で塞いでいました。

えっ、今どき!? なんて言われそうですが、自分はATの運転が大変苦手です。
はっきり言って、古いマニュアル車しか運転できないのです。
今どきの自動車は正に自動車で、様々なアシストシステムが付いていて、気が付かないうちに運転に介入してこようとします。
自分はたまらなくこれが嫌で、代車などを借りた時は出来るだけ機械的なアシストはカットしてしまいます。
特に冬道では車がどんな動きをするか分からないので、恐怖です。
次に自分が乗れるような車が、果たしてあるのでしょうか?
左からトランスミッション、次がトランスファーで左側がスーパーローの切り替えレバーです。
2.7リッターインタークーラーターボと前進八段後進二段のミッションが生み出す大トルクと走破性能は、走る荒れ地を選びません。
更にハイギヤードキットを組み込むと、前進十二段後進三段となるので、唯一苦手な高速走行もこなせるようになり、また面白い車になります。
シフトレバーの根元のふくらみはミッションケースです。
なんとjeepはミッションから直接レバー類が出ているのです。
全くリンケージを介していないいないので、まるでスイッチのようにカチカチシフトが入ります。
ただし、足元がミッションなので走行中はエンジンの音と混じりあってかなりうるさいです。
助手席の人間の会話は怒鳴りあいになるので非常に疲れます。
車内も乾きました。
サッサと装備を積み込みましょう。
次回は普通にキャンプ関係の記事を書きたいと思っていますが、また明後日に曲がってしまいました時はどうかご容赦を。

キャンプの帰りに豪雨に祟られながら拾ってきた山栗です。
小さいのですが、甘くてとても美味しいですよ。
では、また
今日は栗拾いにでも行こうか・・・
何て考えていたのですが、急遽変更して車の整備です。
と言うのも連休中のキャンプから帰る途中、ずっと豪雨に見舞われ、その中を四時間程も走って八戸まで戻って来ました。
そして9月の25日が一日中強い雨が降り続け、結果として車の中が池のようになってしまい、積んであるものが全てずぶ濡れになりました。
なんで、そんなバカな事になるのかと言いますと、両側のドアが無いからです。
実は現在、ドアを修理ついでに改良中でして、依頼した当初は一週間の見積もりでしたが一ヶ月ほども経った現在もまだ帰って来ていないのです。
フルクローズのドアの代わりにハーフドアをつけています。
膝上をカバーする程度のドアですが、これが無いと、風は巻き込むわ、フロントタイヤが巻き上げた雨水がシャワーのように降りかかるわで、大雨の時は溺れそうになります。
最も幌を外す事が前提の車なので、車自体は特に問題は無いのですが、それに乗っている人間は別の話で、寒くて暑く、硬いサスペンションでピョンピョン跳ね回るこの車に乗ることに、体力的な限界を感じた時がソロキャンプも卒業だと考えています。
但し、古い車なので部品探しも大変で、維持していくのも難しくなりつつあります。
今回は車の整備ついでに自分の車を少しばかり読者の皆さんに紹介していきたいと思います。
正式名称は三菱JEEP J55\FEと言います。
車両の起源はとてつもなく古く、1941年の第二次世界大戦時まで遡ります。
当初は前線偵察用4\1t 4×4トラックとして開発されました。
後にJEEPと呼ばれるようになった、戦場で絶大な信頼を得ていたトラックを、終戦後に三菱がライセンス生産した車両が三菱JEEPと言うトラックなのです。
四駆タイプの車をジープと呼ぶ人がたまに居ますが、それは間違いでライセンスを所得していた三菱以外は、JEEPの名称もその特徴的な七本スリットのフロントグリルも一切使うことはできません。
1952年から製造を開始、1998年にライセンスを返上し、生産を終了した今では三菱ですら、JEEPの名前をホームページ上で見かける事はありません。
日本でJEEPと呼ばれる車両は、三菱自動車が生産したトラックだけなのです。
その中で最後に特別仕様で300台だけ生産したファイナルエディションモデルの一台が自分のJ55です。
ちなみに今大人気のスズキジムニーですが、その名前の由来は、JEEPの弟分、ジープミニがジムニーと言う車名になったのだ。
そのように聞いたことがあります。
もし興味を持たれたのであれば、少しばかりネット検索してはいかがですか?
物凄い量の情報が出てきますよ。
では始めましょう。
最初はとにかく車内の物を全て表に出し、日と風に当てて乾かすことから始めましょう。
滴るほど雨水を吸い込んだマット、毛布、細い道具類を次々と引っ張り出していくと、先週のキャンプ場から同行してきたカメムシが幾らでも出てきます。
自分は刺してこない限り、あまり虫の類は気にしない達なので、適当に表に放り出しますが、ダメな方はこの時点で挫けるかもしれません。
ここ何年か夏の豪雨が極端になってきていますので、幌を全部外すフルオープンにはしていません。
おかげさまで、車内には砂や土埃が泥状態になってこびりついていますので、一気に洗車です。
少しでも車という物を御存じの方が見たら驚くでしょう。
しかし、心配には及びません。
計器類を始め、JEEPのパーツは防水仕様になっているので、中も外も洗車できるのです。
ナビシートの下を洗っているところです。
この下に燃料タンクが入っています。つまり助手席に座る人は燃料の上に座っているのです。
以前錆びたタンクに穴が開いて、ナビシート下のフットスペースに軽油がたっぷりと溜まっていたことがあります。
自分はタバコは吸わないので問題ないのですが、さすがにあまりいい気分はしませんでしたね。
普通の乗用車なら内装は腐食するわ、匂いが抜けないわで廃車になってしまうのでしょうが、フロアに開いている水抜きから軽油を抜いて洗車してしまえばOKです。
ちょっと見ずらいかもしれません。
真ん中に見えるのが、フットスペースに開いている水抜き穴です。
雨が降れば水が嫌でも入ってくるので普段から開けっ放しです。
ブラシと洗剤で数年分の汚れを洗い流したら乾かしましょう。
幸い今日は程よい日差しとちょい強めの風が吹いているので、すぐに乾くでしょう。
見違えるように綺麗になりました。
さっきまでの畑仕事後の耕運機みたいな車内とは思えません。
コーヒーをたてて一休みしたら、今度は乾くまでの時間を利用してタイヤローテーションもしましょう。
出来るだけ車のメンテナンスは自分でやるようにしています。
とは言っても、エンジンはディーゼルなので、殆どメンテナンスフリーです。
精々オイル交換とエアクリーナーの点検と交換、ラジエター液の補充とバッテリーのチェックくらいしかやれることはありません。
そして四千キロごとのオイル交換時に、駆動系とステアリング系周りにグリスアップが必要で、グリスガン片手に車の下に潜り込むことになります。
先週にオイル交換とグリスアップは済ませましたので、残ったローテーションをやってしまいましょう。
これをサボるとタイヤが偏摩耗して極端に寿命が短くなってしまいます。
ただし、しっかりしたジャッキなどの工具類とそれなりの経験が無いと、ジャッキを倒してしまったり知らぬうちにハブナットが緩んでいたいたりと非常に危険な事になりますので、初めての方はスタンドなどで店員さんにアドバイスを受けましょう。
とにかく自信と知識が無ければ手を出すべきではありません。
車両の整備とは、自己責任が伴う行為だという事を忘れないことです。
さて硬い話はここまでにして、サッサと済ませてしまいましょう。
ま助手席側から外します。
jeepはそちら側のハブナットが逆ねじになっているので、それを知らずにインパクトを使うとハブボルトを折ってしまうことになりますので要注意です。
Jeep乗りにはありがちな話ですが、タイヤ交換やパンク修理の時にスタンドの店員に説明しておかないとやられてしまいます。
以前スタンドでパンク修理を依頼した時に、店員に説明したのにかかわらずやられそうになったことがあります。
信じられないことに、ハブボルトに逆ねじがあることを知らなかったようです。
某大手の自動車部品の量販店で、でオイル交換のついでに、自分がグリスアップをしたい旨を伝えた時もちょっと困りました。
「お客さんを工場に入れられない。グリスアップが必要ならメカニックがやります」
そんな答えでしたが、若いスタッフしか見かけない工場の様子に不安を覚えた自分は、出来ますか?。
そう伺うと、大丈夫という答えが帰って来たので、料金を聞くと五千円という答えが返ってきました。
自分がやれば十分程度の作業に、五千円という法外な料金請求にちょっとカチンときた自分は、店員に、
「伺いますが、三菱Jeepのグリスアップポイントはどこに何ヶ所ありますか?」
すると、分からない。という想像の斜め上な返事が返ってきました。
驚いた自分は、「はっ・・・この会社は作業内容もろくに分からないのに、料金だけは出せるのですか?
どういう理屈でしょう」
すると店員氏は「・・・・・ならばグリスアップの必要な個所を指示していただければ、大丈夫です」
その返答にあきれ果てた自分は、
「それで五千円請求するつもりですか?・・・良いです、5千円は払いましょう。
その代わり整備授業料として自分は一万五千円請求しますが、それで良いですか」
店員氏は黙り込んでしまったので、
「とても安心して任せられないので、オイル交換も結構です、自分でやりますから」
そう言いおいて店を出て、代わりに〇ェームスに寄って同じことをお願いしたら、快くピットを貸してくださいました。
また幾つかのアドバイスもいただきましたので、大変助かりました。
古い車ならでのエピソードの一つです。
以前乗っていた古いジム二ーの時も似たようなアクシデントが何回かあったので、信用できる車屋さん以外は、一切他人に車をさわらせないようにしています。
昔話をしているうちにローテーション完了です。
あとは数十キロ走った後軽く増し締めすれば完了です。
次にタイヤに手をかける時はスタッドレスタイヤに交換の時になります。
ついでのついでにシート下のトランクスペースも開けました。
ここのウエザーストリップが破れると水が溜まってしまい、錆びてしまいます。
最悪底が抜けて工具類がそっくり無くなります。
大昔、友人のjeepの底が抜けてしまい、ベニヤ板で塞いでいました。
えっ、今どき!? なんて言われそうですが、自分はATの運転が大変苦手です。
はっきり言って、古いマニュアル車しか運転できないのです。
今どきの自動車は正に自動車で、様々なアシストシステムが付いていて、気が付かないうちに運転に介入してこようとします。
自分はたまらなくこれが嫌で、代車などを借りた時は出来るだけ機械的なアシストはカットしてしまいます。
特に冬道では車がどんな動きをするか分からないので、恐怖です。
次に自分が乗れるような車が、果たしてあるのでしょうか?
左からトランスミッション、次がトランスファーで左側がスーパーローの切り替えレバーです。
2.7リッターインタークーラーターボと前進八段後進二段のミッションが生み出す大トルクと走破性能は、走る荒れ地を選びません。
更にハイギヤードキットを組み込むと、前進十二段後進三段となるので、唯一苦手な高速走行もこなせるようになり、また面白い車になります。
シフトレバーの根元のふくらみはミッションケースです。
なんとjeepはミッションから直接レバー類が出ているのです。
全くリンケージを介していないいないので、まるでスイッチのようにカチカチシフトが入ります。
ただし、足元がミッションなので走行中はエンジンの音と混じりあってかなりうるさいです。
助手席の人間の会話は怒鳴りあいになるので非常に疲れます。
車内も乾きました。
サッサと装備を積み込みましょう。
次回は普通にキャンプ関係の記事を書きたいと思っていますが、また明後日に曲がってしまいました時はどうかご容赦を。
キャンプの帰りに豪雨に祟られながら拾ってきた山栗です。
小さいのですが、甘くてとても美味しいですよ。
では、また